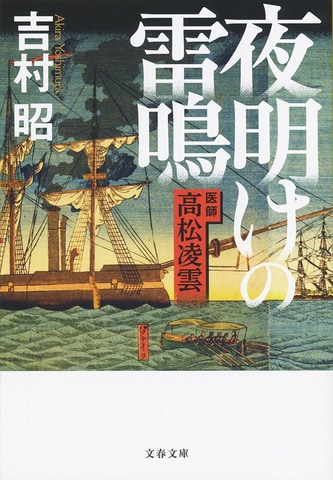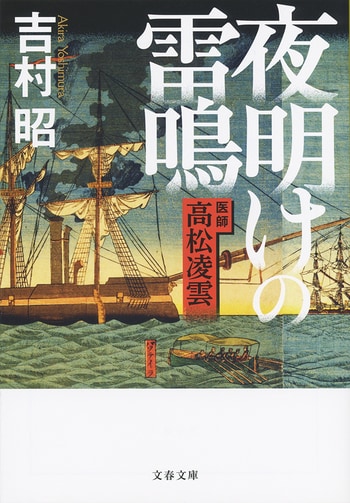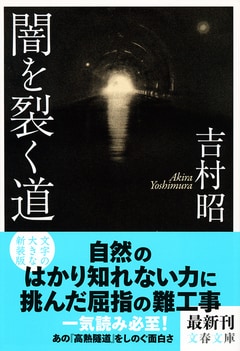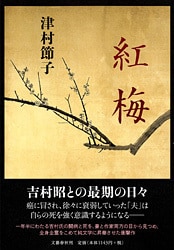吉村昭には、書こうとして取材を始めたものの、途中で執筆を取りやめたテーマがいくつかある。なぜ断念したか。十分な史料が得られなかった、証言の裏がとれなかった、同じテーマを別の人が書こうとしていた、など理由はさまざまだ。ノンフィクションを書く者としては大いに共感するところである。
だが一つ、私には到底理解の及ばない理由で書かれなかったテーマがある。俳人、正岡子規である。中学生の時から肋膜炎を患い、肺結核で死線をさまよっていた吉村は、子規の「病牀六尺」を読み自らを鼓舞したことがあった。死が迫る中で芸術論や時評をつづり、生きる支えとする子規の姿に感動した。母校である私立開成中学の大先輩であり、学友に日本海海戦の時の連合艦隊参謀・秋山真之や、生物学者の南方熊楠がいたことも小説家としての執筆意欲を誘った。同じく肺結核に苦しんだ俳人・尾崎放哉の生涯を描いた『海も暮れきる』をすでに発表しており、子規もまた同じように書けるのではないかと考えたのだ。
ところが、未発表の日記「仰臥漫録」を繰り返し読むうちに自分の不遜さに気づく。子規は肺結核だけでなく、カリエスを患っていた。結核菌に骨まで侵され、脊柱が湾曲する難病だ。
「子規は激しい痛みに狂わんばかりになって、自殺を真剣に考えたりしている。結核患者であった私には腹痛、胸痛はあっても、『タマラン〳〵ドウシヤウ〳〵」というような痛みはなかった」(「私の仰臥漫録」『わたしの普段着』所収)
痛みが違う――。献身的に介護する妹・律にさんざん文句をいい、殺したいと思うほど腹を立てる子規の凄絶な闘病生活は自分の時とは根本的に異なる。それが執筆をやめた理由だった。そんなことをいったら誰も他人の病について書けないではないかと思うのは凡人なのだろう。吉村は幼くして母やきょうだいら愛する家族を病で亡くし、自分もまた病に苦しんだ。痛みに嘘はつけない。たとえ小説であっても、子規の生涯を描くなら「痛み」こそが軽んじてはならない史実。吉村はそう考えたのではないだろうか。
『戦艦武蔵』(一九六六)以来、太平洋戦争を題材にした小説を発表していた吉村は、実戦を知る証言者が激減したことを理由に戦史小説の筆を折り、歴史小説を書くようになった。歴史小説としての最初の作品は「解体新書」を訳出した前野良沢を描いた『冬の鷹』(一九七四)である。戦史から歴史への移行は「水の流れに似た自然のものであった」と、随筆「史実と創作について」(『白い道』)に記している。近い過去を描く戦史と比べ、遠い過去を描く歴史は自由度が高く、作家にとって気は楽だ。点在する史実の欠落を想像で埋めるのは作家の力の見せどころでもある。とはいえ、吉村が自らに課したのは、創作であっても史実を歪めてはならないということだった。一面識もない男女が同衾する歴史小説を例に挙げ、物語を優先するあまり史実を軽んじるのは読者を喜ばせているようで、史実を歪めていることだと断じている。小説になると考えた人物であれば、それだけで生涯は劇的だ。史実を尊重しながら的確に描き出せばそれでいい。「史実そのものに十分なドラマがある」(同前)と考えた。
尊王攘夷論者を弾圧した大老・井伊直弼が暗殺された一八六〇年の桜田門外ノ変から維新までの八年間はとくに、重要な事件が多発して時間の流れが急激に加速したドラマチックな時代である。題材には事欠かず、小説や映画をきっかけに維新の英雄として後世に語り継がれるようになった著名な人物も多い。一方、吉村がこの時代を描くのに採り上げたのは正直なところ、主役級とはいいがたい無名の人々である。
『桜田門外ノ変』の主人公は井伊大老の襲撃を現場で指揮した水戸藩士・関鉄之介。仇討ちを禁ずる復讐禁止令が発布された時代を描く「最後の仇討」(『敵討』)の主人公は、初めて殺人罪で収監された秋月藩執政臼井亘理の息子、臼井六郎。薩摩藩主島津久光の大名行列に遭遇したイギリス人が藩士に殺害された事件を題材にした『生麦事件』に至っては明確な主人公はいない。激変する時代だからこそ、史実に忠実であることが真実を伝える最良の方法だった。
医師を主人公にした一連の作品もそうである。薩摩藩の軍医として戊辰戦争に参加したのちイギリスに渡り、海軍の脚気撲滅に尽力した初代海軍軍医総監・高木兼寛を描いた『白い航跡』、日本人として初めて近代医学を学び、幕末の西洋医学所頭取を務めた松本良順を描いた『暁の旅人』。『日本医家伝』のような短編集もある。いずれも時代の過渡期に自らの為すべきことを為し、困難を乗り越えようとした一途な個人だ。日本赤十字思想の祖といわれる高松凌雲も、本作『夜明けの雷鳴 医師 高松凌雲』で初めてその生涯を知った読者も多いのではないか。凌雲がパリの医学校兼病院「神の館」に目を留め、西洋の臨床医学と博愛精神を学んでいなければ、箱館戦争での凌雲ら医師たちの行動はまったく違ったものとなり、残酷な結末を迎えていただろう。歴史の表舞台にはほとんど登場しない人々を主役に据え、時代を複眼的に捉える。政権中枢に近い場所にいた医師たちはとくに、開国前後の日本人が西洋に何を学び、日本をどんな国にしたいと願っていたかを知るのに、格好の視点を読者に与えてくれる。
もう一つ、吉村は榎本艦隊について興味深いエピソードを発見している。艦隊に参加したフランス軍人が日本女性を連れていたことだ(『史実を追う旅』)。宮古湾海戦を調査した宮古出身の歴史家の史料に記載されていた話で、『幕府軍艦「回天」始末』を執筆する時によほど気になったらしく、ウラを取るための調査を本格的に進めている。男ばかりのむさくるしい空間に彩りを添えるには使いたいエピソードだろう。「箱館戦争仏人調書」などフランス軍人の記録を確認するために、外務省外交資料館や東京大学史料編纂所、国立公文書館に出向いた。新政府軍側の史料を求めて弘前に行き、榎本軍に潜入した密偵たちが残した記録にも目を通している。それでも女性についての記載は見つからず、結果的に『幕府軍艦「回天」始末』には書かれなかった。それから十年、やはり裏付けは得られなかったのだろう。本作においても書かれることはなかった。
吉村のあまりに禁欲的な創作姿勢には圧倒されるが、これをたんに自制心という言葉で片付けてはならないだろう。小説であっても「歴史」と銘打つ限りは史実を歪めてはいけない。人間の真実を書き続けてきた作家の、読者に対する責任ではなかったか。
吉村が世を去って十年になる。この間、東日本大震災、熊本地震など未曾有の災害が続いた。永らく絶版だった『三陸海岸大津波』が再版されて新たな読者を得たのは、時を経ても変わらない人間精神の有り様を伝えてくれるからだろう。戦後七十年を過ぎて戦争を直接知る人が激減する中、実戦経験者の肉声を集めた吉村の仕事はますます貴重な歴史的資料となっている。
世界に目を向ければ、中東、アフリカ、ロシアなど各国で終わりの見えない内戦に苦しむ人々がいる。激戦地では赤十字思想は踏みにじられ、病院までが攻撃のターゲットとなり、医療関係者が殺害されている。徳川昭武一行が訪れたパリではISISによる同時多発テロが起こり、多くの人が犠牲となった。集団的自衛権の限定行使を認めた安全保障政策の転換で、日本においてもテロ対策は喫緊の課題だ。吉村ならこの時代に何を見ただろうか。どんな作品を世に問うただろうか。願っても詮ないこととはいえ、吉村昭の不在が残念でならない。
二〇一六年五月