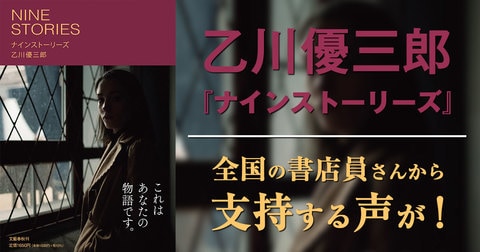岩井俊二が描く、生と死の輪郭線。 モデルが例外なく死に至るという“死神”の異名を持つ謎の絵師ナユタ。その作品の裏側にある禁断の世界とは。渾身の美術ミステリー。
・前回の章
2 オフィーリア
絵は子供の頃から好きだった。けれど本格的に始めたのは高校時代、美術部に入部してからである。油絵の道具を一式買い揃え、初めてキャンバスという布地の上に絵の具を塗った瞬間のときめきは今も忘れ難い。水彩は水を使うが、油彩はテレピン油という油で絵の具を溶く。最初はその匂いに慣れなくて、テレピン酔いとでもいうのか、嗅ぎすぎると頭痛がする時もあった。あの香りも今や懐かしい。いわばタイムスリップの秘薬である。今一度嗅げば忘れかけていた学生時代の想い出が蘇る。
私の通っていた霞ヶ丘(かすみがおか)高校は、横浜駅のすぐ近くに位置する。遠い昔は女子校であったそうで、私が通った時分も八割が女子という、ほとんど女子校と言っていい環境だった。美術部も男子は僅かで、殆ど女子に席巻されていた。部員が各学年に五人ずつぐらいで、それぞれ好きな活動をしていた。デジタルアニメーションを熱心に作っている人もいたし、陶芸に取り組んでいる人もいた。私は、マリー・ローランサンとかシャガールにかぶれたような絵を描いていた。実際のところ本当にかぶれていたのだが。
二年の時、県の美術展で入選して、それに自信を得て、私は大学の進路を美術系と定めた。実技系となると、受験科目がまるで異なって来るので大胆な決断が必要だった。
三年になると、私は横浜駅前の美大専門の予備校に通い、デッサンを本格的に学んだ。ちゃんと学習してみると、今まで何も考えずに絵と向き合っていたことがよくわかった。絵とは多分に技術である。その技術を習得するほど、トレーニングを重ねるほど、絵は格段に上手くなる。それは楽しい時間だった。
予備校中心の放課後生活に変わると、美術部に顔を出す機会も減った。空き時間、部室を覗きに行っては部員たちの創作活動を見物したり、時に横からあれこれうるさい事を言ったりしたものだ。ひとり図書室に籠もり、自習する時間も増えた。この図書室は四階建ての建物の最上階にあったせいか、受験生に人気の図書館が近くにあったせいか、利用者が僅かで、私にとっては居心地のいい安息の場所だった。
加瀬真純(かせますみ)と初めて出会ったのはこの図書室だった。ちょうど夏休みを終えたばかりのまだ残暑の残る九月の初め、彼は入って一番手前の、窓から最も遠い薄暗い机の一隅に陣取り、大きな画集を広げて見入っていた。男子が隅に日陰に位置取りするのは彼に限ったことではない。陽のあたる場所はすべて女子のもの。そのような校風だった。
美術部だった私としては、ああも熱心に画集に見入っている学生を気にしないではいられなかった。ある日、私は教科書や参考書や問題集を抱えて、彼の横を通り過ぎた。その時の彼が広げていた画集がジョン・エヴァレット・ミレーであり、開いていたページが『オフィーリア』であった。一瞬でその絵に魅了された。美しい絵である。ドレス姿の女性が水の中に浮かんでいる。小川だろうか。しかしその川は棺のように狭い。女性の手からこぼれ落ちたのか、赤い薔薇のような花が水面に浮かんでいる。女性は生きているのか死んでいるのか判らないが、恍惚とした表情を浮かべている。瞼はうっすら開いている。
「これ死んでるのかな?」
それが私が彼に語りかけた最初の言葉であった。
「死んでるんじゃないですか」
それが彼の返事であった。
およそ思春期の男女において、その最初の会話にしては、なんとも悍(おぞ)ましい。これが記憶違いならどんなによかっただろうと思うのだが。
この会話は、次にこう続く。
「でも」と私。「よく見ると生きてるみたいだね」
「生きてるんですよ、きっと」と、彼。「このあと死ぬんですよ、きっと」
この彼の言葉、「このあと死ぬんですよ、きっと」という言葉に、どれだけゾッとしただろう。今思い返しても背筋が寒くなる。誰もこの女性を助けに来ないのだろうか。誰も彼女に気づかないのだろうか。そこはどこなんだろう。人里離れた森の中だろうか。案外、その上に橋でもあって、馬車や紳士淑女の往来がありながら、ちょうど死角になって誰も気づかないとしたら……。どちらにしても怖い。怖い怖い。こんな死に方はまっぴら御免だ。あの時私はそう思ったし、その後の人生でこの絵に遭遇する度にそう思った。それほど美しくも悍ましい絵が『オフィーリア』であった。
その『オフィーリア』を私に教えてくれたこの男子生徒を次に見たのは、なんと美術部の部室であった。二年の林田由紀子という生徒が九月から新しい部長になっていた。その前の代の部長は私である。新部長の林田由紀子から彼の入部を聞かされたのは、『オフィーリア』を観た数週間後だった。
男子の入部は珍しかったが、初めてのことではなかった。私が一年の頃は、三人ほどいて、部長も男子であった。二年の時には女子だけになり、三年の時もそうだった。そこに単身乗り込んできたのだから、しかも中途で入部して来たのだから、多少の勇気は必要だったことだろう。
彼は一年生だった。油絵をやりたいのだが、描いたことがないという。道具もないと言うので、ひとまず私の画材道具一式を貸してあげた。卒業生が残した古い十号のキャンバスを白く塗りつぶして、彼に与え、描き方の手ほどきをしてあげた。横浜の画材屋にもつきあってあげた。新品の用具一式を買い揃えるのを手伝い、その後お礼にと、サーティワンのアイスをご馳走になって別れた。
冬が近づくにつれ、私は受験勉強に集中し、部室にも顔を出せなくなった。学校と予備校を行き来し、図書室で自習に励む日々。しかし、あの図書室で再び彼に会った記憶はない。
年が明けて、私は東京の美大を受験したが、あえなく不合格。滑り止めで受けた神奈川美術女子大学、通称カナビジョに辛(から)くも合格し、入学した。油彩科は印象派好きの教授の好みがそのまま指導方針となっていた。学生たちの多くが印象派で絵画を学び、アトリエには、セザンヌやルノワールのタッチを模した絵ばかりが並んだ。私の趣味も決してそこから遠くなかった。相変わらずマリー・ローランサン風の絵を描いては教授や仲間に褒められ、褒められると嬉しくなり、そんな絵ばかりしつこく描いていた。そんな日々を過ごしながら、何かそのまま大学を卒業したら、絵描きにでもなれるような気がしていた。今思えば、あれはあれで素敵なサロンだった。
大学二年の二月。卒業生たちの展覧会があった。私たちはそれを“卒展”と呼んでいた。展示室に陳列された卒業生の作品群は、見事なまでに印象派であった。モチーフは人物画、風景画、静物画のどれかに分類できたし、人物画もタイトルを見ると、『自画像』『母』『窓辺の妹』『友』と、何か中学生の作品タイトルのようである。自分が卒業制作を描く時はもう少しマシなタイトルを考えようと思ったものである。
誰かが“県展”を見たかと言い出した。“県展”というのは県が主催する高校生たちの美術展だった。かつて私も入選した、あの懐かしき美術展である。私たちの隣の展示室では、まさにその“県展”が開催されていたのである。私は仲間たちと連れ立って、この懐かしい“県展”を覗きに行った。会場は高校生たちで賑わっていた。それ以上にこの高校生たちの描いた作品たちが輝いて見えた。これに比べたら自分たちの絵はまるでみすぼらしい。絵の巧さというものは人それぞれ評価も違うだろうし、これが正解というのは難しい。しかし題材選び、となると、それは絵心のない人にも違いはわかるのではあるまいか。高校生の作品はそれぞれに個性的な題材選びが先ず前提としてあった。そういう独創性が悲しいかな我が校にはない。
私が高校時代に描いた作品は、マリー・ローランサンやシャガールかぶれは否めないが、モデルを空に浮かべたり、創意工夫のある空想画であった。そういうアイディアも評価されて入選も果たせたのだろう。しかし、大学に入ってからは、そういう絵を描く人がいなかったというだけの理由で、そういう発想を知らず知らずのうちに封印し、単純な構図の人物画だけを描いていた。言い訳をさせてもらえれば、予備校で石膏デッサンを描く延長線上に大学の授業があり、やはり一年みっちり石膏デッサンをやらされて、二年になると裸婦を油絵で描き、三年も同じく裸婦を描き、四年になるともう卒業制作だ。つまり我々の創作はあくまで絵の学習なのであって、卒業制作はあくまで授業の成果を見せる場であった。
「なるほどね。こういう子達が東京の美大に入って、この世界を牽引してゆくのよね」
そんなことを言ったのは江端さんだった。その落胆した声は今も耳に残っている。
そういう水準に達していない子の受け皿となるのが我らがカナビジョであったかも知れない。この場所では、決してそういう人材は誕生しないし、よく考えたら、ウチの卒業生にプロの画家がいるなんて話を聞いたことがなかった。なのになぜ私は、自分たちは、そんな技量で将来画家になれるなんて思ったりしていたんだろう? 今にして思えば不思議なことである。要するに将来のことなんか少しも真剣に考えていなかったということなんだろう。大学一年や二年の頃とは、特に三月二十三日生まれの私にとっては、まだギリギリ十代で、二十歳過ぎてからの未来は、月のように未知なる世界だった。そんなぼんやりした私たちでも、この高校生たちの絵には打ちのめされた。自分たちの現在地を思い知るには充分だった。
高校生の想像力溢れる作品を見て歩きながら、皆、意気消沈。ひとまず動線を辿りながら出口に向かった。
一番奥に教育長推薦優秀賞という賞のタグが貼られた作品群が並んでいた。その賞は最高位である。油彩、彫塑(ちょうそ)、陶芸など各部門の一番の作品に授けられる。つまりそこがメインイベントのコーナーだった。
油彩画の周りに人が群がっていた。高校生の絵とは思えない、ヤボったい筆遣いのカケラもない、別格の絵がそこにあった。異様な雰囲気を醸していた。
忘れもしない。そのタイトルさえ憶えている。
『遊びをせんとや逝かれけむ』
『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』は、平安時代末期に編まれた歌謡集である。その中に「遊びをせんとや生まれけむ、戯れせんとや生まれけん、遊ぶ子どもの声聞けば、我が身さへこそ揺(ゆる)がるれ」という歌がある。そんなことを後に知った。「遊びをせんとや生まれけむ」とは、遊ぶために生まれてきたのだろうか、という意味である。ならば彼の絵のタイトルは、遊ぶために亡くなったのだろうか、と言ってるわけである。身の毛もよだつタイトルである。
その絵は、怪獣映画の一場面のようであった。建物の悉(ことごと)くが瓦礫と化した廃墟の町。商店街の看板だけが虚しくそびえ立つ。空は煙に覆われ、遠くには火の手も上がっている。一番手前にはひしゃげた瓦屋根が折り重なっていて、その頂上にひとりの少女がこちらに背を向けて立っている。破れ、燃えかけた、ピンクのパジャマを身に纏(まと)い、自分の足元に視線を落としている。そんな絵であった。
私はその描画力に圧倒された。これはもうプロの域だと思った。
これを描いたのが、高校三年の加瀬真純であった。私が油絵を教えてあげた少年は、五十号キャンバスいっぱいに、とんでもない絵を描いていた。
彼は会場にいなかった。いなくてよかった。どんな顔をして彼を褒めていいか判らなかった。
仲間たちと会場から出て、自分たちの会場に戻る途中、美術部の後輩が何人かエレベーター前にたむろしていて、私を見つけると声をかけてきた。
「八千草(やちぐさ)先輩!」
私が三年の頃の一年生たちだった。八千草というのは私の名字である。
彼女たちの中の一人が言った。
「加瀬って憶えてます? 賞取ったんですよ!」
「ああ、憶えてる。私が油絵教えたのよ」
「知ってます」
もう名前も定かではない、あの後輩の無邪気な笑顔を想い出す度、私は心を抉(えぐ)られるような気持ちがしたものだ。偉そうに先輩風を吹かせた自分がどうにも惨めに思えた。
この事件は少なからず私の人生に暗い影を投げかけた。加瀬真純の才能に打ちひしがれ、絵画という世界があまりにも酷に感じられ、私はその荊棘(いばら)の道を先ず避けて通ることから将来設計を考えるようになった。それからの美大生活は、なにか自分が終わりかけの蛍光灯のような、時間潰しのような日々であった。なんとなく周囲の様子に足並みを揃えて、結局卒展に描いた百号はマリー・ローランサンを模した自画像だった。それを以て私は絵の道は最後と決め、普通に就職活動をして、そこでも幾多の挫折を経験しながら、ギリギリ採用されたのが、ウィリアム・ウィロウズという広告代理店であった。
・次章はこちら

岩井俊二
1963年生まれ、宮城県出身。『Love Letter』(95年)で劇場用長編映画監督デビュー。映画監督・小説家・音楽家など活動は多彩。代表作は映画『スワロウテイル』『リリイ・シュシュのすべて』、小説『ウォーレスの人魚』『番犬は庭を守る』『リップヴァンウィンクルの花嫁』『ラストレター』等。映画『New York, I Love You』『ヴァンパイア』『チィファの手紙』で活動を海外にも広げる。東日本大震災の復興支援ソング『花は咲く』では作詞を手がける。映画『花とアリス殺人事件』では初の長編アニメ作品に挑戦、国内外で高い評価を得る。2020年1月に映画『ラストレター』が公開、同7月には映画『8日で死んだ怪獣の12日の物語』が公開された。