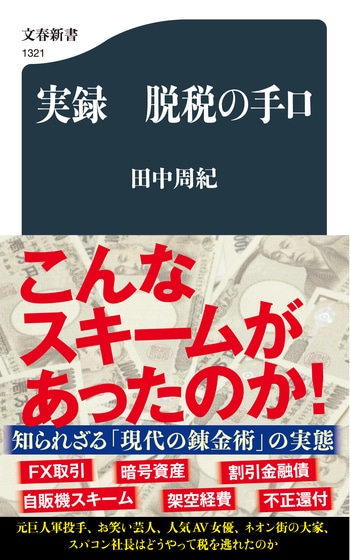もう30年以上も前の話だが、その日のことは今も鮮明に記憶している。日経平均株価が4万円に向けてひた走っていた1989年11月27日、月曜日。毎日新聞の一面トップと社会面にこんな記事がデカデカと掲載された。
「大和証券が“粉飾決算” 『損失保証』で100億円の穴」
「負債隠しにダミー社 昭和59年まで 特定法人客を優遇」
証券業界第2位の大和証券が70年代後半、「損失保証」していた大口顧客約20社から、含み損が発生した株式を簿価(購入価格)で引き取り、損失を穴埋め。その際は自社で引き取るのではなく、ダミー会社を使っていたというのだ。
当時の私は入社5年目の28歳。共同通信社の社会部ではなく、現在は経済部に統合された金融証券部の記者として、東京証券取引所の「兜倶楽部」で証券業界を担当していた。その意味からも毎日の記事は「抜かれ」そのものだった。
私にとってこの記事は、2つの意味で衝撃的だった。
まず70年代後半の古い話とはいえ、損失補填の具体例が初めて表沙汰になったこと。当時はバブル経済の絶頂期で、証券会社の法人営業部門は顧客との間で実質的な利回り保証、通称「にぎり」を交わし、顧客が信託銀行の特定金銭信託(特金)口座に預けた運用資金を好き放題に売買して、手数料を稼いでいた。こうした「営業特金」だけでなく、証券会社が顧客から直接預かった資金の運用を一任される「取引一任勘定」の場合、にぎりは文書に残すなどもっと露骨な形で行われていた。営業特金や取引一任勘定には87年10月のブラックマンデーの際に巨額の損失が発生し、証券会社は事後的に損失を補填したとの噂は確かにあった。だがその具体的なケースが表面化することは一度もなく、損失補填問題もその後の株価高騰で水面下に潜った。ちなみに毎日の記事にある「損失保証」は、正しくは事後的な損失補填のことだ。
2つ目は、この記事の筆者が兜倶楽部担当の経済部ではなく、事件を取材する社会部の記者だったことだ。当時の私は大和証券上層部にそれなりに食い込めている自信があったが、情報の出所が同証券ではない以上、圧倒的な特ダネの後追いほど困難なものはない。私はふと考えた。
「日常的に証券業界を取材しているわけでもない社会部の記者がなぜ、業界担当の自分にさえ手の届かないこんな特ダネを取れるのだろう」
毎日の特ダネの端緒は脱税事件だった
大和証券の「損失保証」に関する毎日の独走はその後も数日続いた。勝ち誇ったように掲載される続報記事を後追いしながら、私には次第に事情が呑み込めてきた。そもそも大和証券の損失補填問題が発覚したのは、中央信託銀行(現・三井住友信託銀行)の元不動産営業部次長による脱税事件がきっかけだった。その具体的な経緯はこんなものだった。
東京国税局査察部が中央信託銀行元次長の脱税に加担した商品取引会社「共和興業」を調査したところ、同社と投資会社「三協エンジニアリング」との関係が浮上。三協エンジ社は共和興業との間で株式を相対取引(市場外での直接取引)し、損失が発生したように装うなどの手口を使って約22億4000万円の所得を隠し、約9億6000万円の法人税を脱税していたが、隠した所得の中には大和から支払われた迷惑料約6億8900万円が含まれていた。実は三協エンジ社は、大和が複数の法人顧客の株式に発生した損失(含み損)を補填する際、その株式の飛ばし先(引受先)として利用していたダミー会社だった。
大和は含み損が発生した顧客の株式を簿価で引き取ることによって補填したが、その際は自社で引き取るのではなく、三協エンジ社に資金を融資し、同社と顧客との相対取引で引き取らせた。その後、大和は三協エンジ社の証券口座に入れたこの株式の運用に失敗し、三協エンジ社の含み損は100億円超にまで膨らんだ。
そこで大和は84年11月、三協エンジ社の口座に入れた前述の株式を売却して損失を確定させるとともに、自社グループの不動産会社の未公開株を三協エンジ社に廉価で売却。三協エンジ社は大和から予め事情を伝えられていた都市銀行などにこの不動産会社の株式を高値で売却し、113億円の利益を上げた。このうち104億円は三協エンジ社が被った損失の補填分で、6億8900万円が前述した迷惑料分だった。三協エンジ社は当然、この所得を全く申告しなかった。
毎日のスクープから1カ月後の89年12月末、東京国税局は三協エンジ社が得た113億円の所得は大和側に帰属するものと判断し、全額を大和の意図的な所得隠しと認定。同社に重加算税を含む約62億円を追徴課税した。
毎日の続報は経済面ではなく、常に一面と社会面に掲載され、筆者は社会部の国税当局担当か、検察担当の記者に違いなかった。かなり後になって関係者に尋ねたところ、社会部遊軍で経済事件を取材している記者が、情報源の東京地検特捜部幹部に示唆され、さらに取材を続けてモノにした特ダネだったという。証券業界関係者から「損失補填は必ず存在する」と聞かされていても何一つ記事化できていなかった私にとって、この事実を社会部の記者に暴かれたことは心底衝撃だった。
ただ、この当時の私には「国税当局の調査力は凄い。いつか自分でも取材してみたい」という程度の想いしかなかった。それが「どうしても社会部で国税当局を取材したい」との強い願望に変わったのは、野村證券など大手証券会社を舞台にした、91年の損失補填問題だった。
読売の瞠目すべきスクープ記事
91年6月20日、予てから「読売が精力的に嗅ぎ回っている」と噂されていた特ダネが同紙朝刊の一面トップと社会面を飾った。
「野村証券 法人損失160億円穴埋め」「債券高値買い戻し」
「昨年の暴落時 証取法違反の疑い」
一面の記事は、野村が90年3月期に計上した約160億円の有価証券売買損について、同年6月に東京国税局に提出した法人税申告書では「自己否認」し、使途や支払い先を明示せずに所得に加算して納税したというもの。自己否認とは、会計上は費用として処理しているものの、税務上の費用には当たらないと自ら判断して所得額を調整することだ。
ただ、これは大口顧客の営業特金に発生した損失の一部について、野村が自身のミスで起きた「証券事故」として現金で補填した金額に過ぎなかった。社会面の記事ではさらに、債券売買を利用した利益供与によって損失を補填した金額が100億円前後あると伝えていた。悔しいけれど、記事の内容は総じて正確だった。
大和の70年代後半の損失補填の発覚を契機に、大蔵省(現・財務省)証券局は89年末、営業特金と一任勘定の契約を翌年3月末までに解消するよう証券会社を指導。これに伴う売り物の殺到で株価が90年初頭から暴落したため、証券局は営業特金を解消する過程で顧客に生じた損失を証券事故として補填することを容認した。
これを受けて野村、大和、日興証券(現・SMBC日興証券)、山一證券(清算)の大手証券4社など証券各社は90年3月期、前述した野村と同様の経理処理と税務申告を行った。しかし、証券各社を税務調査した東京国税局は、顧客に対する損失補填額を「寄附金」と認定し、大手4社だけで合わせて約200億円の申告漏れを指摘し、同90億円を追徴課税した。
私はこの時、「あーぁ、ついに抜かれてしまった……」と脱力感に襲われた。実は共同通信も90年秋、野村の税務調査で損失補填が発覚したことを、当時の国税担当記者が把握した。だが、野村が東京国税局に協力的でなく、調査が捗々しく進展していないこともあって、同局幹部の口はいつにも増して重かった。そこで野村上層部とパイプを持っていた私が、大先輩の社会部の国税担当記者に協力することになった。
私は税務調査の結果が通知される毎月末になると、親しくしている野村の役員の自宅を夜回り取材したが、彼は頑なに損失補填の事実を認めようとはしなかった。終いには「お前、しつこいなぁ。ないものはないんだ」とご機嫌を損ねる始末。ところが国税当局の年度末(毎年6月)である91年6月、噂通り読売の国税担当記者にものの見事に抜かれた。大先輩の何の役にも立てなかった私は、敗北感に苛まれながら、読売の国税担当記者に脱帽するほかなかった。
その翌日、野村と日興が系列ノンバンクを通じて広域暴力団「稲川会」前会長に株式購入資金を融資していた事実が発覚し、世に言う“証券スキャンダル”が勃発する。だが91年7月から大阪支社経済部に異動することが決まっていた私は、後ろ髪を引かれる思いで当初予定通り大阪に赴任した。
「いつか本社に戻った時は、必ず社会部で国税当局を担当してやる」。格好良すぎるかも知れないが、私は自分にそう誓った。そこで大阪支社赴任3年目に社会部に異動して大阪府警記者クラブを2年間担当し、95年5月に本社社会部に配属されると、私はいきなり国税当局と証券取引等監視委員会(SESC)を担当することになった。それまでの金融・証券取材の経験を買われての抜擢だったが、地方から本社に上がり立ての記者が、守秘義務の関係で口が重いことで知られる国税当局を担当するのは、共同では初のケースだった。4年前の宿願が図らずも果たされ、私は奮い立った。
それからは共同通信社会部で1年9カ月間、2000年に移籍したテレビ朝日報道局社会部で06年7月から10年6月までの4年間にわたり、国税当局とSESCを担当し、今も脱税事件や経済事件の取材や裁判の傍聴を続けている。国税当局を担当する「国税庁記者クラブ」に常駐記者として前後6年近く在籍したのは、恐らく私くらいだろう。
国家公務員法と国税通則法に規定された守秘義務(通称「二重の壁」)があるため、国税関係者の口は聞きしに勝る重さで、個別の税務調査の把握は困難を極める。だが首尾よく端緒をつかめたり、取材を重ねて脱税工作のカラクリが解けたりした時の快感は何物にも代えがたく、私はすっかりのめり込んだ。もちろん、抜かれた時の痛みも想像を絶するものだったが。