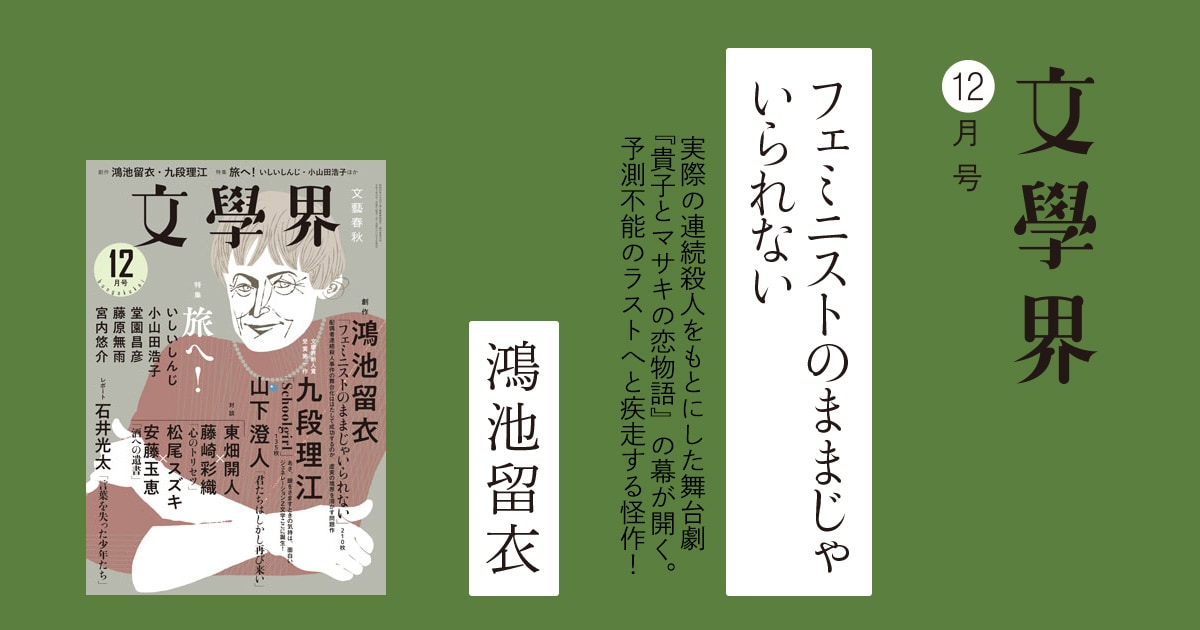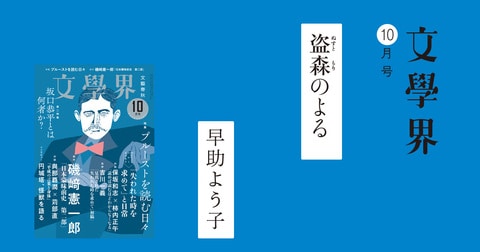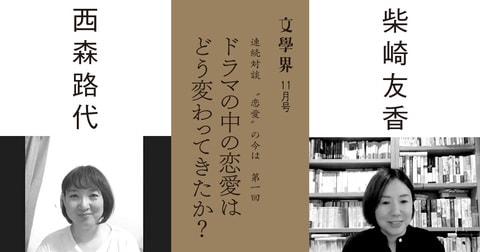第一幕
夛田は、以前働いていた職場で出会って付き合い結婚し、一年で別れた前妻のことを思い出した。いつも心のどこかに彼女のことが引っかかっていて、かつては何かの拍子に思い出して胸が苦しくなっていたものだが、ここ数年はそんなことはなく、このまま遠い過去の傷は癒えるかと言うところで、またその部分をほじくり返された気分だった。
「何読んでるの?」
夛田の手元を覗き込んだ同僚の池谷が訊いた。
「Wikipediaです」
「何の記事?」
「配偶者入れ替え連続殺人事件」
「いつの事件?」
「九〇年代」
「そんなのあったっけ」
もう池谷は興味を失ったようで、夛田の隣の椅子に腰掛けてデスクのPCをいじり始めた。
夛田は調べごとがあると、目の前のPCではなく、ついスマホで検索してしまう癖がある。
夛田が勤務している間、彼がPCではなくスマホを使っていれば、それは業務に関連した何かを行なっているのではなく、まず個人的な好奇心を満たしているに違いない。音楽にしろ、動画にしろ、夛田個人に必要な何かをもたらすための窓口だ。それを知っている池谷だからこそ、Wikipediaを読む夛田を見て「また仕事サボってたな」という嫌味が言えたわけだ。
「池谷さんって、演劇観ないんでしたっけ?」
「観ねえ。何年か前にたまたまチケットが手に入ってライオンキングは観たけど、それ以外で演劇なんて観ないな。キャッツは一度観てみたいけど、でもあれって実際のところ、大して話なんてないんだろ?」
「キャッツはいいですよ。僕はすごく好きですけど。ラムタムタガーっていうスケコマシの猫がイカすんですよ」
「へえ」
「今度行きますか?」
「行かねえよ。なんで男同士でそんなデートみたいなことしなくちゃいけないんだよ」
「奥様とお子さんの分のチケットも取りますよ」
「だったらお前抜きで行くわ。どうせお前と一緒だと、映画の時みたいにまたネチネチといろんなトリビア並べられるんだろ? モグリの役者としてのプライドなのか何なのか知らないけど、蘊蓄垂れるんだよな。勘弁してくれ。観終わった後、お前がいなくなってから俺、奥さんに怒られちゃうよ。何あいつ、すごいウザかったんだけどって」
池谷は笑った。夛田は何も言わず、事件についての記事の続きを読み始めた。
しばらくしてから、池谷は席を立ち、キッチンでコーヒーを淹れ、夛田の分も一杯、デスクに持ってきた。
「お前がキャッツに出られるのはいつなんだろうな」
「出ません。出られません。出たくありません。そういうのじゃないんです」
夛田が副業で役者の真似事をしているのを池谷は知っていた。職場で夛田が次の公演の台本を読み込んでいる姿を、しばしば池谷は目にしている。そういう時は本人の好きにさせるのがこの空間での習わしだった。池谷とて自分の趣味の音楽活動にこの事務所を利用すること頻りであり、彼がエレキギターをかき鳴らしている間、夛田はノイズキャンセルのヘッドフォンをつけながら自分の仕事に集中する。要するにお互い様なのだ。
「そういうのじゃないんだ。あそう。で、また今度、何か出るの?」
夛田の隣に佇み、濃いブラックのコーヒーを啜りながら池谷が尋ねる。
「出ようと思っているのがあるんです」
「じゃあ観に行くわ」
「ありがとうございます。まだ受かるかわからないですよ」
「決まったら教えて。社長と一緒に行くから。夛田の出るやつ、いつか観たいねって前々から話してたんだよ」
そんな池谷の言葉も、彼なりのリップサービスだと夛田にはわかっている。同じセリフを、これまで何度も耳にしてきた。だが夛田の出演作の何をどの回で鑑賞しに来るのか、という具体的な段階までには至らない。そのままこうして、入社から三年経っていた。