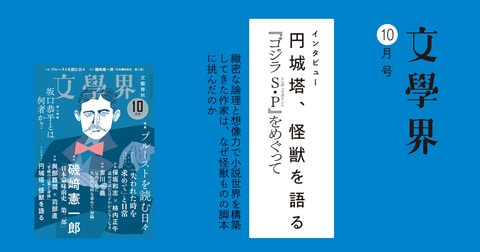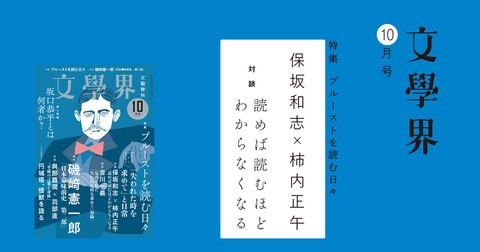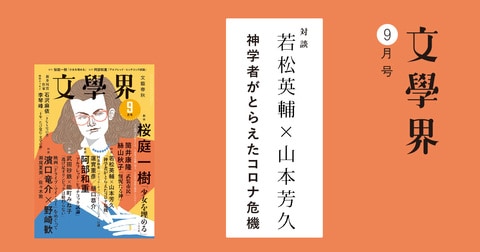十七時二十五分発の便に乗るつもりで保安検査場を通過し、排泄も済ませたけれど、それでもまだ時間が余るので出発ロビーに設置してある券売機で、到着空港から都内へ出る電車の切符を買おうと思った。券売機の前で手提げ鞄から財布を取り出そうとしたとき、
「チケット、買えないでしょ」
と声をかけられた。その声が思い入れたっぷりで芝居がかっていたので、思わず笑って、
「買えないって、どうして?」と聞くと、
「あのね、あの空港は、いま、陸の孤島なんですって」
と楽しげな声が返ってきた。
予想外の答えに驚いているわたしに「昨日、大雪が降って、交通が麻痺しているの。高速道路は不通、鉄道も不通。空港で足止めを食らって出られない人は現在、推定一万三千人」と歌うように続けたのは白髪のおかっぱ頭に真っ赤な口紅をつけ、暖かそうなウールのワンピースを着た老女。
「ほんとうに?」
と言うと老女は目をまん丸にして、「ほんとうよ!」と叫び、わたしにちょうど厚みも大きさもメモ帳くらいの「ふぉん」を見せた。それが皆のいう「あい、ふぉん」なのか、「すまーと、ふぉん」なのか、それとも全く別の何かなのか、一度も所有したことのないわたしにはさっぱりわからない。何しろ、会社にかえろかえろと言われながら、まだPHSをつかっているのだ。差し出された「ふぉん」の画面を横からのぞきこむと、老女は、
「ほら、みんな、ついったーに、書いてるでしょ」
と勝ちほこったような声をあげ、真っ白な平たい爪で画面を下から上へなぞった。すると今、まさにこの瞬間に空港に閉じ込められて出るに出られなくなった人々の、嘆き、驚き、諦めなどのメッセージが次々と、まるで幅広のリボンのように、しなびた指先から繰り出されるのだった。
明日は午前中に会議があるから、今夜はまっすぐ恋人の部屋に帰宅して恋人が作る夕飯を食べ、そのまま会社に近い彼の部屋に泊めてもらって朝はゆっくり目覚め、途中にあるバーガーキングで薄いコーヒーを飲みながら資料に目を通そう、そう考えていた、わたしの計画はどうなるのだろう。
「飛行機は、飛ぶのでしょうか」と尋ねると、
「それは、大丈夫でしょう」
と老女は妙に自信ありげに請け合い、手の中の画面を指して、「ここに、誰かが書いているでしょう? 『空港の外に誰も出られない、でも、空からどんどん人は来る』って」
と言った。
輝くような羽衣をまとった天人がひとり、またひとりと曇天から舞い降りてくる光景は美しいけれど、降りた先に出口がなければ、そこはやがて天人ですし詰めになってしまう。「それでも思い切って、飛び込んでみる?」と言って、いたずら好きの小学生のようににんまり笑った老女は、ひょっとすると空港の精だったのかもしれない。
小さいつづら、大きいつづら。オロオロしながら頭上の物入れにボストンバッグを担ぎ上げるとスーツを着た有能そうな客室乗務員たちが後ろからやってきて、ばちん、ばちんとふたを閉めていく。席に着いてシートベルトを締めるその間も、
「陸の孤島」
という言葉が思い出されて不安になった。でも、他の乗客はどう思っているのだろう。これから皆で一丸となって飛んでいく先の空港が陸の孤島に変わってしまっているということは誰にとっても重要な情報だと思うが、このことを、みんなどのくらい知っているのだろう、と気になって周りを見回しても、どの乗客も、どの乗客も何も語らず、もともと表情に乏しくニヤニヤ笑うばかりで腹の底では何を考えているのかわからないと言われる国民性だからそれは仕方がないにしても、客室乗務員までも警鐘を鳴らす様子がないのは、やっぱりおかしい。そのうちに旅客機はなんの前置きもなくそろりと動き出し、次第に速度を上げ、とうとう北海道の広大な大地を蹴って、空へと飛び立ってしまった。