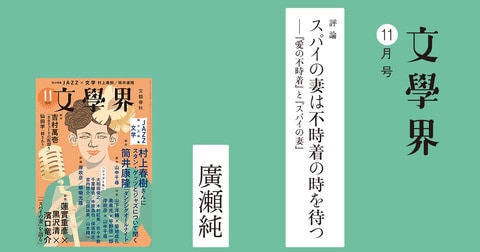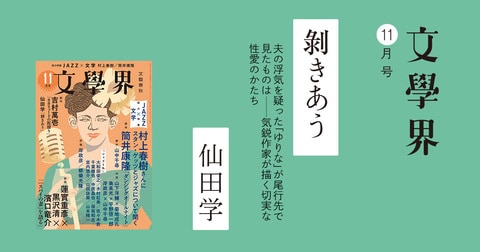妻の機嫌を治すために、男と寝ることになった。
二〇一〇年に私は妻と出会った。当時大学生だった私は、とあるバンドサークルになんとなく所属していた。特に音楽に熱心に関わりたいわけでもなく、酒を飲む相手が欲しくて、知り合った人をいつも手当たり次第誘っていた当時の私にとって、そこの面子は飲む相手として心地よかったのだ。不純な目的を持つ私がいる一方で、サークルには当然、本気でデビューを目指し活動している学生も少なからずいた。
私はそんな仲間がやっているロックバンドが参加するライブを観に、ある日渋谷のライブハウスへ遊びに行った。
彼らの出番は公演の中盤に終わった。フロアに降りてきたメンバーたちは、足を運んでくれた知り合いや、知り合いの知り合いに挨拶して回るルーチンを消化し始めた。私はそれを遠く眺めながらスタンドでタバコと酒を喫んでいた。やがてメンバーらは私のところにも来て、「王子、来てくれてありがとー。あ、オトメちゃんも、ありがとー。王子、オトメちゃんと話してたの? もう知り合いだった?」と声をかけてきた。
この頃はまだプロの小説家としてデビューしていなかったが、私はすでに友人たちに「溜池鴎二(ためいけおうじ)」という筆名でデビューするからな、と吹聴していた。周囲はそれを揶揄するかのように私を、名前の方の響きから「おうじ/王子」と渾名して呼んでいた。
オトメちゃんというのは、先ほどから私と同じスタンドでタバコを吸っていた見ず知らずの女で、つまり後に私の妻になる人だったのだが、その時まではお互いに声をかけずに無視し合っていた。オトメちゃんは、黒く縁取った目の周りを目尻に向かって尖らせたメイクの、赤い長髪の女だった。気になってはいたけれど、小心者の私が気安く話しかけられる容姿の相手ではない。背は私と同じかそれより高く、顔だって年上に見えた。しかしお互いにバンドメンバーの知り合いとなれば、彼らを介して自然と会話するようになっていく。
彼女とバンドメンバーが知り合ったきっかけは、その日に先駆けて行われた彼らの別のライブの打ち上げだった。バンドが利用した渋谷のバーで、当時ホールスタッフをしていたのがこのオトメちゃんだ。バーは監獄を模した内装で、客はそこに収監される囚人の身を体験できる、というコンセプトの店だった。私は行ったことがないのでよくわからないが、店員が客のオデコで茹で卵の殻を叩き割る店らしい。
オトメちゃんはその店で、「へそ出しミニスカナース」の格好をさせられていた。多分、店側が「監獄」と「看護婦」をかけていたのだろう。