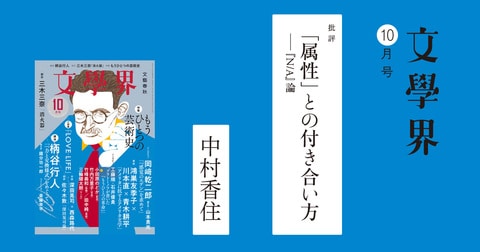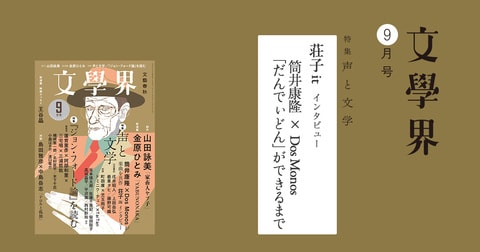1 「国民の物語」としての「閉じていく物語」
三年ぶりとなる新作アニメーション映画『すずめの戸締まり』(二〇二二年)の公開に先立つこと一年前の二〇二一年一二月一五日、監督の新海誠は、最初の製作発表会見の席で、本作のコンセプトについて以下のように語っている。
「扉を開いていく物語」ではなく、「扉を閉じていく物語」を作りたいということ。[…]僕たちの、少子高齢化が進んでいくようなこの国にとっては、いろんなできごとが始めることより閉じていくことのほうが難しいのではないかというふうに感じることが多くなってきました。ですので、いま作るべきは、いまもしかしてお客さんが見たいのは、いろんな可能性をどんどん開いていくような物語ではなくて、一つひとつの散らかってしまった可能性を、もう一度きちんと見つめて、あるべき手段できちんと閉じていく。そのことによって、次に進むべき新しい場所を、本当の新しい場所を見つける、そういう物語をいま作るべきなんじゃないか、いまお客さまは見たいと思ってるんじゃないか。
実家に帰ったり、あるいは各地の舞台挨拶に日本中回ったりすると、少し寂しい風景が増えたなと実感することが多くなったような気がします。[…]かつてたくさん人が歩いていただろう風景が、だんだん寂しくなってきてしまった。コロナ禍でも感じました。[…]僕たちの風景がだんだん寂しくなっていくのであれば、どのようにこの風景を閉じていけばいいんだろうということに興味が向きました。それが、「扉を閉めていくという物語」の発想の起点になっています。
『すずめの戸締まり』は、九州の小さな町に住む一七歳の女子高校生、岩戸鈴芽(声:原菜乃華)が、「閉じ師」を名乗る謎の青年・宗像草太(声:松村北斗)とともに、数多の災いをもたらす元となる「扉」(後ろ戸)を封じながら全国各地の廃墟を旅していくロードムービーである。
周知のように、新海は『君の名は。』(二〇一六年)で国内映画興行収入ランキング歴代第四位(現在は第五位)となる大ヒットを飛ばし、一躍幅広い層から注目を集めた。その後、前作の『天気の子』(二〇一九年)も同じく興行的に成功し、今回の『すずめの戸締まり』もまた、前二作に劣らぬ大ヒットとなっている。土居伸彰は、新著のなかで、前作までにおいて新海は「国民的作家として定着した」と評した(『新海誠』)。なるほど、空前の興行的成功を達成し、日本中の幅広い層の観客からの支持を得たという意味では新海と『君の名は。』以降の作品は、まさに「国民的作家」「国民的映画」と呼ぶにふさわしい。
そして今回の新作は、一言でいうと、前作までで名実ともに国民的クリエイターとなった新海がはっきりと、いわば二一世紀の現代における「国民の物語」を紡ごうとした作品だといえる。もちろんそれはさしあたり、すでに公開直後からさまざまなレビューで言及されている、とりわけ二〇一〇年代以降の新海が好んで参照してきた日本の古典詩歌や神道、記紀神話のモティーフとして表れている。たとえば、明らかに「天宇受売命」の逸話にちなんだヒロインの名前や設定を筆頭に、草太の口にする祝詞の呪文、そして東の要石がその下にあるとされる皇居など、わかりやすい符牒が物語のいたるところにちりばめられている。そして、何よりも、目下本作で多くの賛否を呼んでいる二〇一一年の東日本大震災への明確な目配せだ。
現代の映画史研究には、近代の国民国家のナショナル・アイデンティティあるいは「国民性nationhood」を表象し、またそれを観客に向けて構築する「ナショナル・シネマ」(国民映画)という概念がある。エルネスト・ルナンは、「人々がこれまで払ってき」た「犠牲の感情によって成り立っている大いなる連帯」こそが「国民」の精神的原理だと述べた(『国民とは何か』)。そして、戦後最大の国民映画と称された『二十四の瞳』(一九五四年)に典型的なように、確かに古今の国民映画は太平洋戦争など、しばしば「国民共通の災厄の記憶」をメロドラマ的に召喚してきた。その意味では、震災の描写もまた、――その判断の是非は別にして――本作を一種の「国民映画」に昇華させるための不可欠な要素だったといえるだろう。あるいは、作中で荒井由実の〈ルージュの伝言〉(一九七五年)が流れる場面をはじめ、本作が『魔女の宅急便』(一九八九年)にインスパイアされていることを新海は度々公言しているが、ここには平成以降の日本でまさに最大の「国民的作家」と呼ばれてきた同じアニメーション作家・宮崎駿との結びつき(継承の意志?)も見出せる。
2 起点としての一九七〇年代
では、『すずめの戸締まり』が令和の「国民映画」であり、私たち「国民の物語」を描こうとしているとして、そこで新海が描こうとしている「日本」とは何なのか。
ここで、あらためて先ほどの会見での新海の発言を振り返りたい。「扉を閉じていく物語」という『すずめの戸締まり』の表象する「日本」とは、少子高齢化や世界的パンデミックによって人が消えていき、「だんだん寂しくなっていく」各地の風景そのものである。
この時、本作の想像力の重要な参照先になっているのが、一九七〇年代であることはきわめて興味深く感じられる。二〇一〇年代の震災=「3・11」の記憶を強く喚起する物語の後半は、じつはその一方で、草太を探す東北への旅の途中で、先ほどの〈ルージュの伝言〉を含め、〈夢の中へ〉(一九七三年)、〈銀河鉄道999〉(一九七九年)など、彼の友人の芹澤朋也(声:神木隆之介)が自動車内で流す昭和歌謡に仮託して、七〇年代にも目配せを送る。もちろん、ここで私たちがすぐ想起するのは、東北の原発をはじめ、作中で鈴芽たちが戸締まりをして回る各地の廃墟――リゾート施設の廃ホテルや遊園地跡に象徴される、田中角栄が七〇年代初頭に提唱した「日本列島改造論」に端を発する異常な土地投機熱と首都一極集中、さらにそれが招いた、まさに人が消え、地方の風景が寂しくなっていくにいたる顛末にほかならない。また、震災の年に作られ、同じく『古事記』や神道を重要なモティーフにした『星を追う子ども』(二〇一一年)もやはり七〇年代を舞台にしていた。作中の「ミミズ」という用語に明らかな、村上春樹の参照も「七〇年代的なもの」と結びつくだろう。ともあれ、「日本的なるもの」がこの国から次々に変容していったこの七〇年代に生まれた、いくつもの新たな「国民の物語」が本作と過去の新海アニメの物語世界にこだましていることに気づかされる。
たとえば、『君の名は。』に登場するヒロインの友人の勅使河原克彦(声:成田凌)――彼が愛読する『ムー』などのオカルト雑誌も、むろん七〇年代カルチャーのひとつ――の部屋の壁には、さりげなく一九七〇年に開催された大阪万博の記念旗が掛かっている。この大阪万博が開催された七〇年に、実際に登場人物たちがその開催中の会場に立ち寄るシーンも含みながら、いみじくも『すずめの戸締まり』とほぼ同じように、主人公が九州・長崎の小さな島から北海道の開拓村まで鉄道で日本列島を北上する一本のロードムービーが公開された。この年の『キネマ旬報』ベスト・テンで日本映画第一位を獲得し、主演の倍賞千恵子が演じる役名を冠した「民子三部作」の第一作となる『家族』(一九七〇年)である。監督は、この前年にも主人公が同じく全国各地を放浪する物語の作品を発表していた山田洋次。その作品とはもちろん、その後、戦後を代表する「国民的ドル箱シリーズ」として四半世紀もの間、大衆的人気を獲得し続けていくことになる「国民映画」『男はつらいよ』(一九六九年)。そして、『家族』の終着点や、三部作の最終作『遥かなる山の呼び声』(一九八〇年)の舞台となった北海道も、新海の初期作『雲のむこう、約束の場所』(二〇〇四年)の舞台のひとつだった。
ちなみに、こと新海との関係を考える上ではなおさら、さらにこれら山田の作品群の背後に、写真のネガのように張り付いているような映画が存在する。足立正生、松田政男、佐々木守ら六人のスタッフの共同制作によって、『男はつらいよ』と同年に製作された『略称・連続射殺魔』(一九六九年、劇場公開は七五年)である。この作品は、一九六八年から六九年にかけて、全国各地で連続ピストル射殺事件を起こし、のちには獄中で作家にもなった永山則夫の半生を題材にしている。永山が実際に転々とした逃亡の軌跡を克明に追い、そこで彼が見たであろう風景のみを執拗に映像に収め続けた特異な「風景映画」だ。そして、北海道・網走から神戸まで列島を南下するこの『略称・連続射殺魔』は、『家族』や『すずめの戸締まり』とは奇しくも逆ルートになっている。さらに連想を働かせれば、『略称・連続射殺魔』で題材とされた永山則夫は、新宿で拾った拳銃を発砲したことで警察から追われる身となってしまう『天気の子』の主人公・森嶋帆高(声:醍醐虎汰朗)を髣髴とさせる。『略称・連続射殺魔』がカメラで切り取った風景について、監督の一人である松田は当時、すでに次のように記していた。「私は、この小さな地方の町においても、網走のそれと全く同様の印象を受けないわけには行かなかったのである。すなわち、地方の独自性がいちじるしく磨滅し、中央の複製とでも呼ぶほかはない、均質化された風景を私たちはそこに見たのである。[…]わが独占の高度成長は、日本列島をひとつの巨大都市として、ますます均質化せしめる方向を日々露わにしているのではないか」(「風景としての都市」、『風景の死滅 増補新版』、傍点引用者)。
平沢剛が注意を促すように(「風景論の現在」、同書所収)、むろん、本作を起点に松田らによって提起された風景論(「日本風景論争」)が帯びていたような新左翼的な革命論との鋭い緊張関係は、二一世紀の新海アニメの風景からは雲散霧消している。とはいえ、少なくともここで松田がまなざす、永山が見たであろう数々の風景の持つ「地方の独自性がいちじるしく磨滅し」た「均質化」のイメージは、郊外化(ファスト風土化)が列島の隅々にまで広がった現代の風景と確実に地続きである。山田の『家族』がおそらくそうであったのと同じ意味で、物語世界ではふたたび二年後に迫った大阪万博の時代を描き、やはり特異な生い立ちを持った青年が衝撃的な銃撃事件を起こした年に公開された『すずめの戸締まり』はいわば「裏返された『略称・連続射殺魔』」でもある。
3 「新海的なもの」としての「国民の物語」
大阪万博が開催され、『家族』が公開された一九七〇年、旧国鉄は個人旅行者の増加を目的にしたキャンペーン「ディスカバー・ジャパン」を開始した。「美しい日本と私」をキャッチコピーにしたこの企画は、同時に皮肉にも、それ自体が先の松田のいう、フラットに「均質化された風景」を全国に広げ、かつてあった土着的な風景を消していった資本主義の論理の産物でもある。
このキャンペーンの前年に作られた『男はつらいよ』は、知られるように、渥美清演じる主人公の「フーテンの寅次郎」が故郷の東京・柴又を離れて各地を放浪し、映画は文字通り四季折々の日本の自然を観客に「再発見」させていく。が、そこで描かれる日本の風景は当時まさに失われようとしていたノスタルジックな自然と、それに代わって現れた記号化された消費社会下の風景イメージとの相克を如実に感じさせていた。事実、シリーズ第六作『男はつらいよ 純情篇』(一九七一年)では大学生のサークルが寅次郎の啖呵売り(口上)をテープに録音させてもらうシーンがある。ここからは、物語で描く風景がすでに失われつつある側に属していることに映画が自覚的であることが窺われる。その風景が、旧国鉄最後のキャンペーンソングだった郷ひろみの〈2億4千万の瞳―エキゾチック・ジャパン―〉(一九八四年)が登場する『すずめの戸締まり』にまで遠く続いていることも自明だろう。
そして、高度経済成長による「ゆたかな社会」(ガルブレイス)が到来したこの時期に、この国の戦後史においてそれぞれ特権的な「国民の物語」を発信し、変容する国家と風土についての省察を残したのが、すでに何人もの論者がその対応関係に注目している、三島由紀夫と司馬遼太郎だった。万博が開かれた七〇年に衝撃的な割腹自決を遂げた三島が、その直前に「日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであろう」(「果たし得ていない約束」)と予言的な感慨を残したことはよく知られる。
そして、その三島の死について、翌日の『毎日新聞』の一面で「さんたんたる死」と表現し、三島が目指した吉田松陰のような「政治論的死」に連なるものではなく、あくまでも個人の「狂気」に由来する「文学論的死」(「異常な三島事件に接して」)だと一蹴した司馬は、その一方で、翌七一年一月一日号から、『週刊朝日』誌上でのちに自他ともにライフワークと認めることになる歴史紀行エッセイ『街道をゆく』(一九七一~九六年)の連載を始める。この仕事はある意味で、三島が極度に観念的に捉えた戦後日本の問題を、全国各地に残る風習や風土を自らの足で掘り起こし具体的に跡づけていった試みだといえる。
何にしても、以上を踏まえると、愛媛(『南伊予・西土佐の道』)や神戸(『神戸・横浜散歩、芸備の道』)、そして東京(『本所深川散歩、神田界隈』など)と、かつて『街道をゆく』で司馬がたどった同じ地域をめぐる『すずめの戸締まり』とは、まもなく生誕百年を迎える今日まで「戦後最大の国民的作家」とみなされてきた司馬が七〇年代にたどり始めた「国民と土地の物語」を、令和の現代にふたたび呼び起こす映画にもなっているのだ。「「人を脅かす災害や疫病は、」[…]「後ろ戸を通って常世から現世にもたらされるんだ。だから俺たち閉じ師が、後ろ戸を閉めて回る。戸を閉めることで、その土地そのものを本来の持ち主である産土――土地の神に返し、鎮めるんだ。[…]」」(『小説 すずめの戸締まり』)と、草太は鈴芽に語る。この言葉は、七〇年代から最晩年にいたるまで土地投機問題を憂慮し続け、「枝道には日本のモトのモトのような種子が吹き溜っていて、日本人のなまな体臭が嗅げるかもしれない。/そういうことで、野であれ里であれ、吹き溜りをさがして、あちこち歩いてみたい」(「無題(「街道をゆく」連載予告)」、『司馬遼太郎が考えたこと5』所収)と書いた司馬の言葉とおそらくそう遠くかけ離れてはいないだろう。実際、現在の新海は、『街道をゆく』の連載を始めた当時の司馬と、ほぼ同年齢でもある。
山田洋次、宮崎駿、三島由紀夫、そして司馬遼太郎……。名実ともに「国民的作家」と呼ばれることになった新海誠が手掛けた『すずめの戸締まり』の物語をある種の「国民の物語」たらしめているものとは、震災や天皇制といった表面的な符牒ではなく、その細部に、七〇年代から右に挙げた数多の「国民的作家」が紡いできた「国民の物語」が反響しているからだろう。
むろん、ここには多くの逆説や矛盾が内包されている。たとえばここには、アニメ史的には、もともとはゲーム業界の出身で、パソコンを使った個人制作という徹底してマイナーな分野から出発した新海が、メジャーなヒットメイカーになってしまったという逆説も含まれる。ただ、この点は北村匡平が指摘する、今日「もっとも〈日本的〉な歌手」だとみなされる美空ひばりが、本来は、ジャズからルンバまで「どんなサウンドであっても地域固有の音楽に仕立て上げ」てしまう「無国籍的なポピュラーシンガー」(『椎名林檎論』)だったという逆説にも似ている気がする。福嶋亮大や福間良明がそれぞれ指摘するように、もとより日本の「国民文学」となった司馬作品が頼山陽の『日本外史』のごとく正史とは異なる民間の「野史」であったこと(『復興文化論』)、また新海と同様、じつは司馬のライフコースも、学歴的にも職歴的にも、また文学的にも当時の「正統」「一流」を大きく外れた「傍系」「二流」のものであったことなどを考え合わせると(『司馬遼太郎の時代』)、私たちの国における大文字の「国民の物語」とは、そもそも本来的に、「新海的なもの」であったのかもしれない。だとするなら、これから新海が紡いでいく物語に見られる逆説や矛盾も、今後ますます私たち自身の似姿に近づいていくことになるはずだ。
(初出「文學界」1月号)