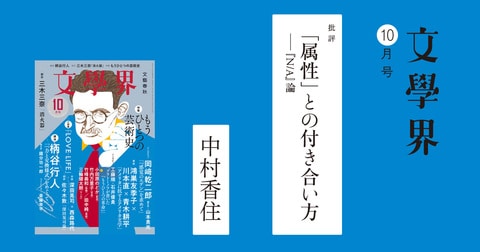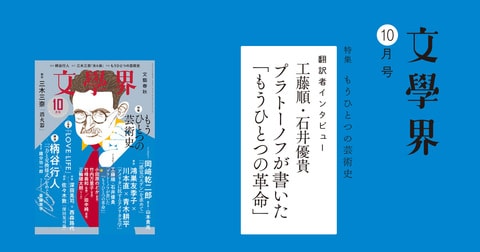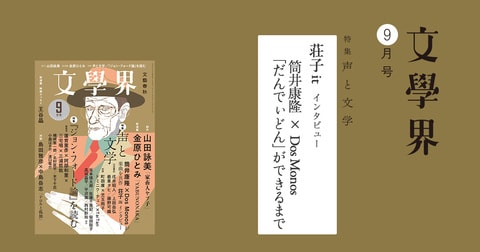ゴダールという名前を耳にして反射的に記憶に甦ってくるのは、三つの断片的な光景である。まず、1962年初冬にパリについてあまり時間のたっていない冬の夕方、サン・ミッシェル大通りとサン・ジェルマン大通りが交差するあたりのちっぽけな小屋で『カラビニエ』(1963)を見たときの寂れた光景は、とうてい忘れることができない。まばらな客席を見まわしながら、『勝手にしやがれ』(1960)で観客を魅了した監督の新作が決定的に無視され、あまつさえ軽蔑さえされていることが腹立たしくてならず、これほど素晴らしい作品に人が集まらない低俗な「文化都市」パリを心から軽蔑した。直後に、この作品の観客動員数が、フランス全土で1800人たらずでしかなかったことを知り、その一人が自分だったことを理由もなく誇りに思った。ゴダールは、パリを軽蔑することを教えてくれた唯一の映画作家である。
二つ目は、マリナ・ブラディのふくよかな太腿の官能的ともいうべき触感である。次回作の主演女優として彼女に出演を依頼するために1966年に来日したゴダールは、ある晩、世田谷に住むさるフランス人の瀟洒な屋敷に招待されたのだが、そのときマリナ・ブラディは、ミシェル・ボアロンの『OSS117/東京の切札』(1966)の撮影で日本に滞在中だった。深夜すぎにホテルに戻るというゴダールにつきそうべくタクシーを呼ぶと、マリナ・ブラディをエスコートしながら、ホテルには自分たちで帰れるから、まず君の家まで送って行くと彼はいう。恐縮だと応じたわたくしは、ぎゅうぎゅう詰めの後部座席に腰を据えて深夜の東京を疾走し、幹線道路をはずれた自宅前で降りたのだが、男二人に挟まれながら窮屈そうにも見えなかった『彼女について私が知っている二、三の事柄』(1967)の主演女優の体温のようなものと、それを無視するかのようなゴダールの饒舌とが忘れられない。その後、二人がどんな振る舞いに及んだのかは知る由もない。題名の「彼女」とは、主演女優ではなくパリのことだと監督は何度も宣言していたが、はたしてそうか。
三つ目の記憶は、より現時点に近いものだ。まだ東京国際映画祭が多少はまともに機能していた前世紀末のこと、ゴダールからいきなりファックスが届き、映画祭参加作品『右側に気をつけろ』(1987)の日本語スーパーをお前がつけろと厳命された。その直前、百は下るまい誰だか身元の知れぬ男女にひたすら電話をかけまくったあげくに成立したゴダールとのインタビュー(『わたしは孤立している だが、憎しみの時代は終わり 愛の時代が始まったと確信したい』季刊『リュミエール』第9号、1987年秋)をスイスのロールで収録したばかりだったので、彼がこちらの質問を気に入ってくれたのだろうと確信し、進んでフランス映画社のオフィスに籠もり、当時の社長だった故柴田駿とともに、無数のフィルム素材が置かれているにもかかわらずひっきりなしに紫煙を立ちのぼらせながら、三日三晩徹夜して仕事を終えた。ゴダールとは、涼しい顔で赤の他人に徹夜を強いる不遜きわまりない男なのである。もちろん、彼から礼状など届くはずもない。
では、ゴダールと呼ばれる映画作家にとって、その後半生の住処としたレマン湖畔のロールと、その前半生の仮の住処であったフランス共和国の首都パリとは、いかなる関係にあったのか。確かなことは、彼が、スイスとフランスのパスポートを巧みに使い分け、その二つの国でともに兵役を逃れることに成功したという事実にほかならない。脱走兵として営倉に監禁されたフランソワ・トリュフォーや、ドイツに亡命してまで兵役を逃れようとしたジャン=マリ・ストローブらと較べて、彼の「特権性」は明らかだろう。
では、パリの大銀行の創設者の一人を母方の祖父として持ち、スイスの町医者を父に持つという、あるときはフランス人でまたあるときはスイス人でもあるゴダールは、みずからのその「特権性」をどう処理していたのか。いうまでもなく、映画を撮ることによってである。『勝手にしやがれ』のジャン=ポール・ベルモンドが、生粋のパリジャンと見えながら、数の数え方からしてスイス人と想定されていたことを見落としてはならない。恐らく、ゴダールは、「特権性」を撮ることの根拠とした唯一の映画作家だといわねばならぬ。スイスだけに存在する法規によって自死同然にその生命をたったときも、彼がおのれの「特権性」を誇示していたのは明らかだからである。だが、人類は、この種の「特権性」をどう処理したらよいのか、いまだ皆目わからずにいる。
(初出「文學界」11月号)