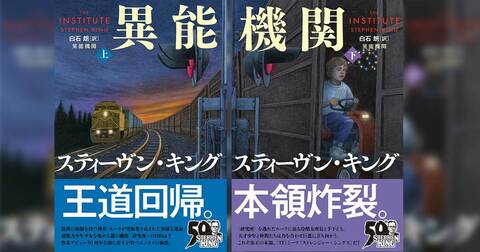今年(二〇二四年)に作家デビュー五十周年を迎えるスティーヴン・キング。
第一長編『キャリー』(一九七四年)以来、“ホラーの帝王”として長年エンターテインメントの世界に君臨してきた彼の影響力は、ますます大きくなっているようだ。特に近年は代表作『IT』(一九八六年)をはじめ、『ペット・セマタリー』(一九八三年)、『ドクター・スリープ』(二〇一三年)など代表作の映像化(再映像化を含む)が相次ぎ、往年のモダンホラーブームを知らない若い世代にあらためてその存在感をアピールした。
この十年は『心霊電流』(二〇一四年)など超自然ホラーの力作を書き継ぐかたわら、ミステリにも意欲を強く示し、『ミスター・メルセデス』(二〇一四年)、『ファインダーズ・キーパーズ』(二〇一五年)、『任務の終わり』(二〇一六年)からなる「ビル・ホッジズ三部作」で高い評価を獲得。退職刑事が大量殺人鬼を追う『ミスター・メルセデス』は、アメリカ探偵作家クラブ賞(エドガー賞)の最優秀長編賞に選ばれている。
キング作品はもともとホラー・SF・ミステリ・ファンタジーなどの手法を融合させたジャンルミックス性に特徴があり、ミステリへの挑戦も『ドロレス・クレイボーン』(一九九二年)などで比較的早くから試みられてきたが、その手腕が玄人筋からもあらためて評価されたということだろう。
二〇一八年に原著が刊行された本書『アウトサイダー』は、恐怖の帝王の貫禄とミステリ作家としての技倆がともに堪能できる、キングの現在形が詰まった長編だ。「結局それってホラーなの? ミステリなの?」と疑問に感じる方もいるだろうが、答えは後ほど述べることにして、あらすじを簡単に紹介しよう(先入観なく作品に接したい方は、ここで一旦解説ページを閉じていただきたい)。
物語の主な舞台はオクラホマ州フリントシティ。犯罪とはほぼ無縁のこの地方都市で、住人たちを震撼させる凶悪事件が発生した。町に住む少年フランク・ピータースンが何者かに殺害され、無惨な死体となって発見されたのだ。
事件の容疑者として浮上したのは、地元の高校で英語教師を務めるテリー・メイトランド。少年野球チームの指導に熱意を注ぎ、多くの人に慕われる人物だった。多くの目撃証言や指紋などの物的証拠から、テリーが犯人であることがほぼ確実となり、刑事ラルフ・アンダースン率いる捜査チームは、衆人環視のもとテリーに手錠をかける。
逮捕されたテリーは動揺の色を見せるが、取り調べでは一貫して犯行を否定。というのも彼には鉄壁のアリバイがあったからだ。事件が起こった日、テリーは高校の同僚たちと、遠く離れた町での会議に出席していた。その証言に嘘がないことが、当日の映像などから徐々に分かってくる。一方でDNA鑑定の結果は、テリーが事件現場にいたことを物語っていた。
この絶対的矛盾に、関係者それぞれの心は揺れる。同日同時刻に、一人の人間がまったく異なる場所に現れることなど可能だろうか。ラルフの妻ジャネットが言及したポーの怪奇小説「ウィリアム・ウィルソン」のように、テリーと同じ顔をもつ男がどこかに存在しているのか。
キングはこの不可解極まる事件を、強烈なサスペンスをもって描いている。サスペンスとはそもそも“宙吊り”の意だが、読者は文字通りふたつの矛盾する可能性の間で宙吊り状態にされ、もどかしい思いを味わうことになるのだ。物語の緊迫感を高めるのに大いに役立っているのが、キングが好んで用いる多視点描写である。
本書には序盤だけでもテリーをはじめ、夫の逮捕にショックを受けたテリーの妻マーシー、テリーを救おうと奔走する弁護士ハウイー・ゴールド、テリー犯行説を信じて疑わない検事ビル・サミュエルズ、そして逮捕劇の責任者でありながらテリーの人格を否定できないラルフなど、数多くの関係者が登場するが、ひとりひとりがキングの筆によって命を吹き込まれており、読者の眼前で事件の印象はめまぐるしく変化する。
そのことが事件の奇妙さをいっそう強調し、読者に分厚い本のページをめくらせていく。視点の切り替えによってここまで読者を翻弄するキングの語りはやはり圧倒的だ。そして訪れたテリーの罪状認否手続の日、フリントシティにまた新たな悲劇が降りかかる──。
本書の構成上のひとつの特徴は、探偵役にあたる人物がリレーのように移り変わっていくことだ。最初は弁護士ハウイーの依頼を受けた調査員アレック・ペリーがテリーの足跡を追い、その後ラルフが妻ジャネットとディスカッションしながら、事件の真相に迫ろうとする。それを引き継ぎ、調査を一気に進展させるのがホリー・ギブニー。「ビル・ホッジズ三部作」にも登場する探偵社〈ファインダーズ・キーパーズ〉の調査員だ。
つまり本書は「ビル・ホッジズ三部作」と同一の世界を扱っており、時系列的には第三作『任務の終わり』の後に位置している。とはいえ本書から読んでもまったく問題はない。ホリーがいかに有能で、しかも愛すべき女性であるかはすぐに伝わるだろうから。
テリーの父親が入所しているオハイオ州デイトンの施設を訪ねたホリーは、そこで重要な手がかりを得、とうとうおぞましい真相に到達する。どうやら一連の事件には、フリントシティの人々が知らないまったくの部外者=アウトサイダーが関わっているらしいのだ。ではアウトサイダーとは何者なのか。本編を未読の方のために、ここではある種の超自然的な存在、とだけ書いておこう。そのようなものの存在にホリーが気づくことができたのは、彼女は過去にも超常的な事件に関わった経験があるからだ。
ここで「本書はホラーかミステリか」という先ほどの問いに立ち戻るなら、ある時点まではサスペンスと緊迫感に満ちたミステリ、そこから先は超自然的存在の脅威を扱ったホラーということになる。この中盤での不意打ちめいたギアチェンジが、本書の大きな読みどころだ。これに「ミステリじゃなかった」と腹を立てるか、「待ってました」と拍手するかで本書の感想は変わってくるだろう。
しかしこの展開がご都合主義に思えないのは(といっても少々唐突ではあるが)、前半の調査パートが実に丁寧に描かれているからだ。作中、読書好きのジャネットが引用するシャーロック・ホームズの名台詞「不可能なものをすべて除外したあと、そこに残ったものがどれほど突拍子がなくても、それこそが真実だ」を、キングは本書で実践してみせているのである。人の仕業でないなら、それは人ならざるものの仕業というわけだ。ちなみにこのミステリからホラーへという転換は、「ビル・ホッジズ三部作」を通して試みられたことでもある。もしかするとキングの脳裏には、「これと同じことを一作の中でもできないか」というアイデアが浮かんだのかもしれない。
後半はオクラホマからテキサスへと舞台を移し、ホリーとラルフを中心にした調査チームと、人知を超えたアウトサイダーとの死闘が描かれる。こうなるとホラーの帝王の独壇場だ。結末に向かってフルスピードで突き進んでいく波瀾万丈の物語に、読者は身を委ねればいい。齢七十を超えてもまったく衰えることのない筆力で、ホラーエンターテインメントの醍醐味をたっぷり教えてくれる。
なおキングファンならご存じのとおり、共通の秘密を抱えた者たちが一致団結し、強大な敵に立ち向かうというクライマックスは、『IT』などにも見られるキング作品お得意の展開だ。殺人事件をきっかけに出会った“旅の仲間”が、悪夢の連鎖を止めるために奮闘する姿は、定番といえば定番なのだが、やはり胸を打つものがある。とりわけ事件を通して信頼関係を深めていくホリーとラルフの姿は、多くの人にとって忘れがたいものとなることだろう。
同じ顔、同じ名前をもつ人間が異なる場所に現れる本書の主要テーマは“分身”である。それはドッペルゲンガーを扱ったポーの「ウィリアム・ウィルソン」が再三言及されることからも明らかだ。これ以外にも分身の恐怖を扱った作品には、E・T・A・ホフマン『悪魔の霊薬』(一八一五~一八一六年)、ジェイムズ・ホッグ『悪の誘惑』(一八二四年)、オスカー・ワイルド『ドリアン・グレイの肖像』(一八九一年)など数多くの例があり、ホラーの歴史においてひとつの流れを形成している。キング自身も過去に『ダーク・ハーフ』(一九八九年)でこのテーマに挑んでいた。
分身譚が私たちを不安にさせるのは、“自分は自分である”というこの世界を生きていくうえでの大前提を、呆気なく崩壊させてしまうからだ。しかも物語の中に現れる分身は、普段目を背けている自らの影の部分であることが多い。ロバート・ルイス・スティーヴンスンの『ジキル博士とハイド氏』(一八八六年)の結末に象徴されるように、主人公と邪悪な分身は二人で一人というべき存在なのだ。
本書の冒頭でテリーは自らの犯罪を強く否定する。身に覚えがないのだから当然だ。しかし車に残った指紋などの動かぬ証拠を突きつけられた彼の胸には、(ひょっとして自分がやったのでは……)という疑念が一瞬過ぎらなかっただろうか。はっきりとは書かれていないが、キングの筆はその微妙な怯えを確かにとらえている。自分が自分でなくなる恐怖を描いた本書の前半は、後半とまた違った意味で怖ろしい。
それと関連して注目しておきたいのが、『アウトサイダー』という表題である。本書におけるアウトサイダーは部外者、秩序の外側にいる者を意味しており、そのニュアンスを補強するため、キングは巻頭に「盲人の国」の一節を掲げている。イギリスの作家・評論家コリン・ウィルソンの評論集『アウトサイダー』(一九五六年)に含まれる文章だ。同書においてウィルソンはニーチェやゴッホ、ニジンスキーなどを例にあげ、社会秩序の外側で生きたアウトサイダーたちの栄光と孤独を描いた。
この往年のベストセラーを引用しながら、キングの脳裏にはもう一冊の『アウトサイダー』の存在も浮かんでいたのではないだろうか。そう、アメリカンホラーの巨匠、H・P・ラヴクラフトの作品集『アウトサイダー、その他』(一九三九年)である。その表題作である「アウトサイダー」(一九二六年)では、長年暮らしてきた廃墟の城を抜け出した語り手が、人間の住む世界に足を踏み入れ、そこでおぞましい怪物を目にする。それこそは鏡に映った彼自身の姿に他ならなかった。一種の分身譚でもあるこの怪奇小説の古典を、ラヴクラフトからの影響を公言するキングが、まったく意識しなかったとは考えにくい。
本書をラヴクラフトへのオマージュと呼ぶのはさすがに言い過ぎだが、キングは『アウトサイダー』というタイトルを通して、この長編が分身テーマの怪奇譚であることを、ホラーファンに向けてさりげなく宣言しているのだ。そして往々にして実存的・心理的恐怖に終始しがちな分身テーマを、大興奮の娯楽ホラーに仕立て直したところにこそ、キングという作家の資質がよく表れている。
冒頭でも述べたとおり近年はキング作品の映像化が相次いでおり、本書も二〇二〇年にHBO製作で連続ドラマ化されている。ラルフを演じるのはベン・メンデルソーン、ホリー役にはシンシア・エリヴォ。各種配信サービスで観ることができるので、興味がある方はチェックしてみてほしい。
デビュー以来、精力的に執筆を続けてきたキングは作品数が多く、どこから手を付けていいか分からないという方もいるだろうが、個人的にはどこから読んでも構わないと思う。確かに『シャイニング』(一九七七年)や『IT』はホラー史に燦然と輝く傑作だが、近年のキングも文句なしに面白いのだ。人物描写は円熟味を増す一方で、エンターテインメント性は相変わらず高く、現代アメリカ社会への切り込み方にも信が置ける。
本書でキングとの幸運な出会いを果たした方は、ぜひ他の作品にも手を伸ばし、歩みを止めない帝王の凄みに触れていただきたい。キング世界の全貌を把握するには、文藝春秋電子書籍編集部が無料配信している冊子『デビュー50周年記念! スティーヴン・キングを50倍愉しむ本』が、大いに役立つことも言い添えておこう。