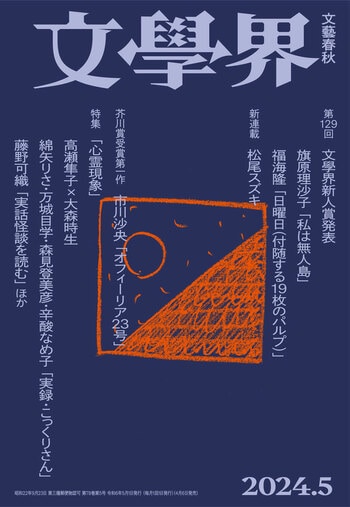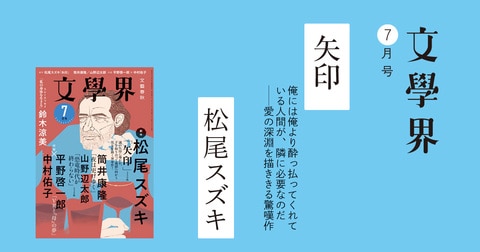とにかくつねになにかにせっつかれ、ずっと軽度か中程度のパニック。そんな精神状態が続いていた。
今、思い起こせば、なかなか明るいパニックではあったけど。
そのパニックの中でわたしは、希望を感じたり、絶望したり、人を疑ったり、次の日に信じすぐまた疑ったり、笑ったり怒ったり、10年分ぐらいの高カロリーの感情が毎日のように噴出し、不安と恐怖と、それでも隠しきれないエンターテイメント感の中で、なんとか喚き散らさず60歳の人間らしくふるまおうと、ひきつった笑顔でおのれを律していた。
分別。フンベツ。流氷の上を寒風が吹きすさぶ北海道の地名のようなこの言葉だけが、当時、わたしの初老の人間としてのぎりぎりの体面を守るよすがなのだった。
2023年11月。これから、身内が大麻で逮捕されることも日本最大級のテレビスターが下半身スキャンダルの裁判で休業することも能登の方で大地震が起きることも政治家たちが次々と記憶をなくしていくことも、知るよしもなかったあの頃。
わたしは60歳にして人生14回目、そして最大級の引っ越し作業に溺れそうになっていた。
8年暮らしたマンションからの引っ越し。しかも期限は一ヶ月を切っている。多大なる本。多大なる家具、家電、衣服、DVD、資料、映画や舞台の脚本。2年前からわりと本格的に絵を描き始めていたので、仕事部屋でひしめくさまざまな画材。それらの間や下から無限に湧き出してくるゴミ。そしてゴミなのかなんなのかわからない膨大な書類の山。それを選別し、捨て、あるいは梱包し、あるいは業者に二束三文で売り払い、3LDKの部屋を空っぽにするまでに、いったいどれほどの時間と労力がかかるのか。正直、やってみないとわからない。そういえば、ベランダにも家庭菜園をやろうとして頓挫し、その残骸の土というものが積み上げられている。土は、燃えるゴミか燃えないゴミか。それもわからない。
なにしろ東京に越してきて37年もたつが、8年も同じ町で暮らしたことなどなかったからだ。13回引っ越しているのだから、それはそうなるだろう。
13回。と、口にして空を仰ぎ見る。借りた仕事場も含めれば、引っ越し回数はさらに増える。さすがに引っ越し過ぎだ。
などとおのれにあきれている場合ではない。退去の日は刻々と近づいている。11月29日である。
もう解約手続きをすませてしまっているのである。すませたからには後には引けないのである。やっぱりやめましたはないのである。そういう契約なのである。
部屋の外からは轟音が聞こえる。
重機の作動音。地面を掘る音。石を砕く音。金属を切り刻む音。コンクリートを破壊する音。
これが始まったのは、同じ年、2023年の夏のことだ。
マンションの隣の土地に3台の大型ショベルカーが配置され、毎日、土日以外絶対休まずに建造物を解体し、土地を掘り起こしている。なんと呼ぶのかわからない巨大なハサミのついた重機もときに現れ、鉄骨を切ったり運んだりしている。
パワーショベルが地面をうがち、掘り起こした土と石をふるいにかける音がすさまじい。
がっひょん、がっひょん、がっひょん、がこがこがこがこ……。
ビルの鉄骨を切り刻む音は、発狂した歯医者を表現するかのようにヒステリックだ。
ぎゅううううういいいいいいいいんん……。
朝9時から始まり、昼、1時間休憩し、そして5時まで。そういうのがえんえん。
わたしは仕事部屋のベランダからそれを見下ろし、日々ドラマチックに形を変えていく大地を眺めながら、まるでこの世の終わりに立ち会っているような気分だった。タバコというのはこういうときに吸いたいものだと、ヘビースモーカーだった頃の感覚が蘇ったりする。わかっている。君たちはわたしの心を殺そうと思って、音を立てているわけじゃない。君たちが生きるための音だ。
わたしが住んでいたのはマンションの5階の角部屋で、仕事部屋と寝室、そしてリビングの一部が面する土地は、某バス会社が経営するバスの待機所であった。なのでそこは広い。事務所もあれば、ガソリンスタンドも洗車場もある。その隣には子供が集まる公園があり、さらにその先は墓地だ。つまり視界が開けている。窓から東京タワーも見えるし、なんならスカイツリーまで見える。見晴らしの良さが気に入って住み始めたと言ってもいい。
そして実際8年住み続け、この町がとても気に入っていた。
結婚して代官山や笹塚に住んでいた頃は、醜い喧嘩をしじゅう繰り返していたものだが、じょじょに争いごとが少なくなり、近頃はほとんど喧嘩をしなくなっていた。子供や学生が多いこの町に流れる穏やかな空気というものが、それに関係しているとふんでいた。部屋の間取りもよかった。北向きの玄関を入れば隣は7畳の仕事場。その奥が5畳の寝室。さらにその奥に大きな押し入れの付いた4畳半の和室。南のどんつきに15畳のリビングダイニング。日当たりがよく、二人暮らしには十分過ぎる広さで、和室をむしろもてあまし、ダンベルやフィットネスバイクなど置いてコロナ下はトレーニングジムにした。仕事場とリビングが離れているのでテレビの音が気にならない。和室とリビングはつながっていて、正月などに人を招けば開き戸を開けて20人ぐらいは収容できた。
東京に来たときは真の一人ぼっちだった。正月をひとり家で過ごすのが嫌で、深夜のマクドナルドの清掃のバイトを入れていた。正月手当はハンバーガー1個だった。それが三十数年の時をへて、20人の客が自宅に集まってくれるのである。
穏やかなのに活気がある。理想の環境ではないか。
コロナ禍をまるまるこのマンションで過ごした。それで夫婦仲がこじれる人もいたようだが、むしろ夫婦の絆は深まった。うまくは言えないが、代官山や笹塚ではだめだった気がする。
2022年の秋だったか冬だったか。
マンションのエレベーターに突如張り紙がなされた。
バス待機所を取り壊し、10階建てのマンションを建設します、とのことだった。
さらにその工事は2年続きますと。
脳が震えた。
2年である。
わたしは知っているのだ。寝起きする場所に隣接する土地で始まる工事の、最大ボリュームで聞かされるヘビメタじみた狂乱を。
10年以上前、三宿の一軒家で一人暮らしをしていた頃、裏手の古い大きな家を取り壊し、新たな家を2軒建てるという大掛かりな工事が始まった。それは半年かかった。しかもその半年間、わたしはまったく関係ない理由で、自宅で病に臥せっていたのだ。木造で窓に防音性はない。ダイレクトな騒音をただただ布団をかぶって耐えていた。正直泣いていた。
やり場のない怒りというのはこのことかと身をもって知った。おのれが住む三宿の家だって、それと同じ騒音の中で生まれ、裏手の家に住むじじばばをせいぜい悩ませていたのだ。復讐の連鎖、ユダヤとアラブの……などという言葉がよぎるが、もちろんただの転居と土地の売却である。
まあ、この話は長くなるのでのちのち。
しかし、当時は半年。この度は2年。当時建ったのは家。この度は10階建てのマンション。この違いがわからない人とは生涯友だちになれない。
とはいえ、始めはたかをくくっていた。たかをくくったまま年を越し2023年になった。我がマンションの窓は、かなり防音性の高い二重サッシである。実際、ベランダから手を振りたくなるような距離を電車が走っているが、窓を閉めれば走行音など一切気にならない。大丈夫。外からの物音で目覚めたことなど、8年間一度だってないのだ。妻と二人でおのれらに言い聞かせた。まあ、大丈夫でしょうと。
ところが夏に工事が始まったとたん、その心の慰みは瞬時に消えた。
わたしは、コンクリートを粉砕する音で目が覚めた。やつらの度を越した騒音レベルを前に二重サッシなどはまったく無力であることを思い知ったのだ。
わたしはその日から仕事場難民となった。とにかく考え事ができるレベルの場所に移動しなければならない。
実はじゃっかん心の問題を抱えていた。
50を過ぎたあたりから、雑音に非常に敏感な人間になってしまったのだ。
最初にそれに気づいたのは、雑誌でインタビューをうけているときだった。取材中に、インタビューカットといって、喋っている姿を写真に撮られることが多いのだが、カメラのシャッター音がすると、とたんに言葉に詰まるのだ。なにを話しているのか忘れてしまうのである。最初、それに気づかず、「あれ? 喋るの下手になったな」ぐらいに思っていたのだが、毎度確実にそうなるので、ついにインタビューカットをどうしても撮らなければならないのであれば、最初の5分間、インタビュー内容とは関係ない雑談をしているところを撮ってくれ、という要求をせざるをえなくなった。したがって、わたしのインタビューカットはすべて茶番である。なんにも考えてない。芝居の演出中でもスタッフが隅で喋っていたりすると、パツンと思考が止まる。逆に演技の最中に話し声が聞こえても台詞を噛んでしまう。あるドラマの撮影時、わたしの長台詞の最中に相手役が「ふっ」とため息を漏らした。それだけで「変なタイミングで雑音を出すな!」という殺意で胸がいっぱいになり薄っぺらい芝居をしてしまった。居酒屋の喧騒も耐えられない。人の声が気になって目の前にいる相手の話がうまく聞けないのだ。聴覚過敏という病気があるらしいが、一度医者に診てもらったほうがいいのかしらと思う。
そんなわけなので、工事の騒音の中、仕事場で物書きの仕事などできるわけもなく、照りつける太陽の下自転車漕いでカフェを梯子し、芸術監督をしている渋谷Bunkamuraの会議室を借りたりしてしのいでいた。大人計画にも会議室はあるが、そこには星野源や宮藤官九郎がなにやかにやで受賞した輝かしい賞状やトロフィーがいくつも鎮座していて、それはそれでなにかしらの雑念を生む部屋なのである。♪あとから来たのに追い越され 泣くのが嫌ならさあ歩け……。水戸黄門の主題歌がつい頭の中を流れゆくのである。
書物の仕事はそれでなんとかしのいでいたのだが、コロナ禍で始めた絵で12月に個展を開こうという話になって、ことは深刻さを増していった。絵は、キャンバスを使ったアクリル画、画用紙に描く鉛筆やペンでの線画、毎日とにかく一枚小さな画用紙になにか描くという「一日一枚絵」、個展で展開するアニメーションのためのキャラクターデザイン等、多岐にわたる。青山スパイラルホールという分不相応にでかいホールをギャラリーとして借りたため、膨大な絵数が必要となったのである。あまたある画材を外に持ち歩くのは無理だ。
わたしは大騒音の中、奥歯を噛み締めながら絵を描いていた。趣味で始めた絵なのに、なぜ奥歯を噛み締めなければならないのか。情けなくて涙が出そうだった。結局その年のうちに200枚以上の絵を描いたのだが、今となっては、どうやってそれをなしえたのか、記憶が朧である。
気がつけば、街に出て不動産屋を前にすると物件の張り紙に釘付けになっている自分がいた。つい間取りと家賃と築年数をつぶさに見てしまう。あとで聞けば、妻もそうしていたという。今の町を出ていくのは嫌だ。リビングに仕事場が隣り合わせる間取りもだめだ。そもそも3LDKは広すぎるのじゃないか。おりしもマンションの値段が爆上がりしている最中。価格に対する文句が止まらない。等々、勝手に言いがかりをつけられるかわいそうな物件の数々。
騒音の中、季節は秋になっていた。
ある日の昼、仕事から帰ると一枚の不動産広告がポスト投函されていた。
ある日と言ったが忘れもしない2023年10月5日。
その一枚の広告に載っていた新築の家に、我々夫婦は住むことになる。
11月29日からである。
購入したのである。
チラシを見た2日後に不動産屋に手付金を払っていたのである。
〈つづく〉
(初出 「文學界」2024年5月号)