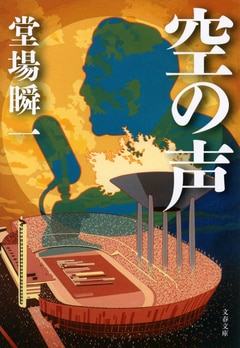オリンピックを殺す、とは物騒なタイトルだ。数々のスポーツ小説や警察小説で世の人々の血を熱く滾らせ、心を震わせてきた堂場瞬一の作品名は象徴的な短い言葉のものが多いが、本書は珍しく、ずいぶん直截的である。二〇二二年九月に刊行された単行本版では、オビに「五輪を潰せ! 祝祭の意義を問う衝撃のサスペンス!」「新たなスポーツ大会『ザ・ゲーム』の計画が浮上した。果たして黒幕は誰なのか。記者が、たどり着いた真相とは⁉」と記されている。書名とこれらオビの文字情報だけでも、どうやら一筋縄ではいかない作品であろうことは容易に察せられる。
まずは本作に関わる背景を整理しておこう。二〇二〇年に開催が予定されていた東京オリンピックに合わせ、堂場瞬一は〈DOBA2020〉というプロジェクトでオリンピックに関連したスポーツ小説を立て続けに発表した。二〇二〇年三月、あの「チーム」シリーズの最新作『チームIII』(実業之日本社)の刊行を皮切りに、四月にはNHKアナウンサー和田信賢を題材に採った『空の声』(文藝春秋)、五月はラグビーと円盤投げの“二刀流”で五輪出場を目指す『ダブル・トライ』(講談社)。そして六月には、デビュー作の野球小説『8年』の藤原雄大がアメリカ代表の監督になり東京で金メダルを目指す『ホーム』(集英社)。各作品について言及し始めると紙幅がいくらあっても足りないので控えるが、いずれも堂場スポーツ小説の魅力が遺憾なく発揮された名篇揃いだ。
さて、これらの作品が刊行された時期に、じっさいの東京オリンピックはどうなっていたのかといえば、ご存じのとおり新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延で一年先送りとなり、二〇二一年に無観客で開催されることになった。さらには、開催前からロゴの盗用疑惑や関係者のパワハラめいた言動などが発覚して開閉会式の演出案が二転三転したり、大会終了後には談合・汚職事件で何名も刑事訴追されたり、うんざりするほどのスキャンダルが次々と起こった。それらの出来事を経て、二〇二二年秋に書き下ろしとして刊行されたのが本書『オリンピックを殺す日』だ。
この時系列からも想像できることだが、本書は直球のスポーツ小説というよりも、むしろジャーナリスティックな視点からスポーツを描いた小説、という特徴を備えている。作品の冒頭では、パンデミック下で開催された東京五輪の放送中に金権体質やメダル至上主義、礼賛一色の報道を辛辣に批判した大学教授が姿を消す。数年後、ある世界的IT企業がオリンピックに対抗するスポーツイベントを仕掛けているという情報を摑んだスポーツ紙記者が真相を追い始める。IT企業関係者や様々な競技の元オリンピアンたちを取材していくと、やがてその大会の全貌が徐々に姿をあらわしはじめる……。
世に数あるスポーツ小説の中でも、このような角度からオリンピックを取り上げた作品はきわめて珍しい。視点人物となる主人公に新聞記者を設定しているところにも、作者の意図が窺える。しかも作者は、この主人公に、ハードボイルド小説の伝統に則った観察者の役割を与えるだけではなく、彼のスポーツやオリンピックに対する考えや行動原理に、いかにも日本のメディア業界人らしい、ある特徴を付与してもいる。マスコミ企業の旧弊な装置産業的側面や、オールドメディアにありがちな無自覚で無邪気な特権意識、というその特徴が折々に挟まれることにより、読者が彼の思考や価値判断を無批判に受け容れて感情移入するのではなく、作品の奥に横たわる主題に対してさらに俯瞰した批評的視点と距離感を持つように作り込んでいる。じつに巧妙な仕掛けだ。
では、著者がこの作品で読者に問いかける主題とは何なのか。それは、世の人々が東京五輪関係者に何度も何度も訊ねながらも、ついぞ明快な答えが返ってこなかった問い――「オリンピックとはいったい誰のために、何のために開催するのか」という疑問だ。
じつはそのあたりについて、堂場さんご自身に話を伺ったことがある。拙著『スポーツウォッシング』を集英社から刊行した際に推薦文をお寄せいただいたことがご縁で二〇二三年秋に対談をさせてもらったのだが、その際に本書の成立事情を訊ねたところ、堂場さんはこんなふうに明かしてくれた。
「オリンピックをこれからどう見ていけばいいのだろうということがわからなくなりかけていて、その自分の気持ちに折り合いをつけて総括してやろうという気持ちで書きあげました。要するに、オリンピックは一人の作家のスポーツに対する純粋なマインドを歪めてしまった、ということですよ」
商業主義に傾く一方のオリンピックに対する批判は、たとえばすでに沢木耕太郎氏が一九九六年のアトランタを取材した『冠 廃墟の光』(朝日文庫、後に新潮文庫)のなかで、様々に辛辣な指摘をしている。また、マクロ経済学者のポール・クルーグマンも、経済性から見ればオリンピックの開催は合理的ではなく特定の利害関係者に利益をもたらすだけ、と厳しい評価をくだしている。堂場さんも上記の対談の際には、「そんなオリンピックに対する拭いきれない疑問、『今の形のままでいいのだろうか……』という違和感を小説に昇華させた」のが本書だったと話している。さらには、
「カタをつけるというか、決着をつけようという気持ちは確かにありました。そう考えて作品を書いていくと、今まで(の作品に)出てきた個性が強めのキャラクターたちに助けてもらわないと、ただの救いがない話になっちゃうんです(笑)」
とも述べているのだが、この言葉にもあるとおり、本作には堂場スポーツ小説を読んできたファンなら思わずニヤリとする人物が数名、いかにも、といった場面で登場する。それが誰と誰でどこに現れるのかをここで明かすのは未読の方々の興を削ぐことになりかねないので、まずは読んでからのお愉しみ、と言うにとどめておく。
それらの登場人物以外にも、本書とつながりを持つ作品がある。長距離ランナーと元オリンピアンの官僚を主人公にして、アスリートにとってメダルと国家の意味とは何なのか、と問うた『独走』(実業之日本社)がそれだ。二〇一三年に刊行されたこの作品で、オリンピックに対抗するイベントとして設定されている大会が、本書の冒頭にも登場するUG(Ultimate Games)だ。その作中には、アスリートが競技中に独白する次のような一節がある。
オリンピックのように派手に演出され、何万人もの目が見守る中で走ることこそ、祝祭――お祭り騒ぎなのだと思っていたのだが。
違う。
祝祭は、自分の体の中から溢れてきて、周囲をその色に染めるのだ。
この独白を敷衍し、オリンピックはいったい何のため、誰のためのものか、という大きな問いを小説として我々読者に投げかけた作品が、『オリンピックを殺す日』だ。
本書が第一級の娯楽作品であることは言うまでもない。ただし、他の堂場スポーツ小説群を読み終えたときに感じるカタルシスは、ここにはないかもしれない。それどころか、読者は容易に答えが見つからない問いを投げかけられて、むしろ複雑な思いを抱えてしまうかもしれない。だが、それこそが著者がこの作品に託したかったものであるはずだ。
容易に見つからないその答えは、本書を読み終えた我々ひとりひとりがこれからスポーツと向き合いながら見いだしていくべきものだ。また、堂場さん自身もきっと、今後の作品でその決着をさらに昇華させてゆくのだろう。
堂場瞬一という作家は、スポーツと小説に対して誠実な人だな、とつくづく思う。