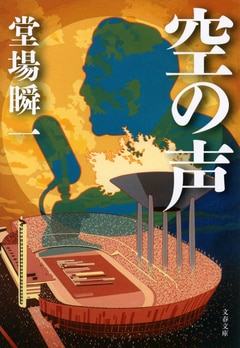これは青春小説ではないか――読了後、そう感じた。
本書の主人公である滝上亮司は三十六歳。青春というにはかなり年齢を重ねてしまってはいるが、父親に反発し、地元から逃げるように上京してきた彼が、父親を中心とする故郷と再び対決する姿はまさしく、二十年遅れの青春まっただ中にあり、反抗期をずっと続けているようにも思える。
滝上の青春が歪んでしまったのは、本人自身の選択の結果であるのも確かだが、その背景には大きすぎる父親の存在があった。もともとは建設会社で働いていた父親は政治家を志すと、手始めに地元の市議選に立候補し当選。さらに県議を務めたあと国政に出て見事当選し、衆議院議員を務める。その後、地元静岡の知事が急逝したのをうけ、静岡県知事選に出馬して当選、という経歴を持っている。二世ではない、まさに成り上がりの政治家だ。そんな父親の元で、滝上亮司は帝王学をたたき込まれるはずだった。
はずだった、というのは父に反抗し、大学進学とともに実家を出て上京したからだ。
滝上の心には母親の死にまつわる父親への憎しみが深く刻まれている。だからこその反抗だが、父親の方は息子が米国留学中にしでかした出来事が原因で勘当した、というような認識を持っている。そんな父との確執は亮司が警察官になったあとも続いている、というわけなのだ。
物語は銀座のビルで放火殺人が起きたところから始まる。
その捜査に向かった滝上はクラブのオーナーと容疑者の女性が焼死していたことを知る。容疑者はただ自殺したかっただけなのか、あるいはオーナーに殺意があったのか。事件の背後関係を捜査していくうち、滝上はある薬物にたどり着く。それをきっかけに事件は彼自身の過去とも繋がっていくのだが、その一方で県知事である父親と事件との接点も明らかになっていく。さらに、父親の元秘書が殺されるにいたり、滝上はかつて捨てた故郷へと戻り、ひとり捜査を進めていく。だがその目的は恨み続けてきた父親を破滅させるためで――。
ソポクレスが戯曲「オイディプス王」を書いた古代ギリシアの昔から、父と息子との確執・対決は現実においてもフィクションにおいても存在し続けてきた。それはフロイトがエディプスコンプレックスを提唱して以降も変わらない。「STAR WARS」におけるダース・ベイダーとルーク・スカイウォーカーとの確執を筆頭に、小説・マンガ・映画・ゲームなどと、様々なエンターテインメントにおいて採用され続けている普遍的なテーマとなっている。
乗り越えるべき壁を設定し、それを乗り越える過程を描くのが青春小説のセオリーだが、父親という存在は読者にとって身近であり、人生で最初にぶち当たる壁となることも多いため、テーマとして使われやすいのかもしれない。だが多くの作品で扱われているということはすなわち競争が激しいことを意味している。それでも堂場瞬一はそのような状況などお構いなしのように青春小説的テーマを取り上げ、警察小説の枠組みの中へと組み込んで見せた。通常であれば主人公が未熟な中高生である青春小説と、複雑な大人の世界を描く警察小説とは相性が良くないのだが本書ではその難題をしっかりとクリアしている。それを可能とした背景には本書刊行時にちょうどデビューから二十年を数えた小説家としてのキャリアがあるに違いない。
堂場瞬一は二〇〇〇年、野球小説『8年』で第十三回小説すばる新人賞を受賞して翌年デビューしている。デビュー作こそスポーツ小説だったものの、二作目として警察小説を発表し、そのまま警察小説の第一人者として走り続けている。ドラマ化もされた「刑事・鳴沢了」シリーズを始め、「ラストライン」「警視庁追跡捜査係」「警視庁犯罪被害者支援課」といった警察小説のシリーズを続けつつ、野球や陸上、ラグビーなどを主題としたスポーツ小説も多く手がけてきた。速筆なため発表された作品数は百を優に超えており、あと数年内に二百冊の大台へと到達するだろう。
そんな堂場がデビュー二十周年という節目の年に出版するべく連載を始めたのが本書『赤の呪縛』だ。
本の発売にあわせ、文藝春秋のウェブサイト「本の話」にて公開されたインタビューで、堂場は次のように答えている。
「20周年の記念の年の発売に向けて、『オール讀物』で連載をすることになったときに、『父と子の諍い』を書こうという発想がありました。設定は、マフィアの父と、その息子でもいいかな、と考えたのですが、日本を舞台にして書く小説としてはリアリティがない。だとすれば、警察小説でいこう、と」
マフィアを選ばなかった理由がリアリティという点は実に興味深い。
小説家としてデビューする前は新聞記者として働いていたためか、取材などに裏打ちされたリアリティのある描写を基本とし、その上で人間ドラマを展開していくところに堂場作品の大きな特徴がある。それは本書でも遺憾なく発揮され、刑事の捜査、火災現場の状況、あるいは捜査で向かった街の情景など、現実の状況を知らない読者に対しても「実際こうなんだろう」と思わせる説得力に溢れた描写となっている。
中でも、作中に登場する政治家の元側近が起こしたとされるマネーロンダリング事件に関しては、現実の事件が頭をよぎった。現実に政治資金規正法違反で有罪判決を受けた元秘書自身は本書内の展開とは真逆の人生を歩んでいるようではあるが、堂場が小説内で現実を描こうとしている一例ではないかと思う。
もちろん、本書のすべてが現実に沿っているわけでもない。
作中に登場する薬物・スヴァルバンは現実には存在せず、物語展開にあうような設定で生み出された架空のドラッグだ。そのような非現実的な要素も堂場の手にかかれば違和感なくリアリティのある物語へと溶け込ませられるのである。
その一方で、日本におけるマフィアの暗躍が報道されることはほぼなく、フィクションの題材としても読者にあまり共有されていないためか、日本が舞台でマフィアの親子が対立する物語を堂場は選ばなかった。それはそれで読んでみたい気もするが、どこまで非現実を物語に組み込むかという点でベテランならではのバランス感覚を持っているのは確かなのではないだろうか。そして、二十周年作品の物語として本領が発揮できる警察小説というフィールドを選んだことで、政治家の父親と、警察官の息子という対立構造が際立ち、青春小説的な反抗期の物語と、大人の世界=警察小説との融合に成功しているのである。
前述のとおり、そのふたつのジャンルは本来、水と油と言っても良いかもしれない。
基本的に青春小説は若者向けに書かれており、学校などの閉鎖された環境を舞台として物語が展開されることが多い。その一方で、警察小説の多くは現実の警察組織に立脚し、開いた社会を舞台とした小説だ。相反する特徴をもっているはずなのだが、堂場は父親を憎み続けている警察官を主人公にすることで、両者をひとつの物語にすることに成功している。
堂場がこれまでに警察小説を数多く書いてきたことに加え、野球小説でデビューしており、その後もスポーツ小説を定期的に発表していることが理由だろう。スポーツ小説は主人公こそ若者ではないものの、アスリートの“終わらない青春”を描いたものが多いからだ。“終わらない青春”に対し、中高生の頃から父親への憎しみを抱いていた本書の主人公が、三十半ばになってから巨大な権力を持つ父親に立ち向かう姿はまさに、“遅れてきた青春”そのものだろう。
堂場作品が警察小説として優れていることは改めて述べるまでもなく周知の事実だが、それに加え、青春小説としての側面は若者にも十分にオススメできる、ということを示したのが本書ではないだろうか。
滝上の父親への感情は、父親の地位が高すぎるなど、特殊な環境であったこともあり、読者が身近に感じるのは難しいかもしれない。しかし彼が故郷に対し抱いている感情については、身近に感じるひとも多いのではないだろうか。古くさい商店街に立ち並ぶ低いビル、時を経ても変わらない住宅街、移動するには自家用車、幹線沿いの巨大なショッピングセンター……そして東京に行くまでの時間的金銭的コスト。
一方で、東京が持つ魅力は底知れない。
出会いも娯楽も文化も勉強も仕事も、その魅力には果てがない。だから東京への憧れを抱いたまま大学進学を理由に上京し、そのまま得体の知れない東京の一部になってしまうひとは実に多い(筆者のように出戻ってくるケースもあるが)。
だがもちろん、故郷を嫌っているだけでないのも確かなのだろう。
毎年毎年、年末年始やお盆に帰省ラッシュで渋滞が起きたりするのも、せめて年に数回は故郷へ戻りたいという欲求の表れであるし、おそらく大半のひとは故郷に対して愛情と憎悪という相反する感情を抱いているのではないだろうか。
そのような感情は滝上亮司も同様らしく、それを象徴しているのが次のように独白するシーンだ。
携帯は怖いものだな、とふと思った。機種変更で何度替えても、電話帳のデータは引き継がれる。ただ番号交換して、一度も連絡を取ったことのない人間の番号が、いつまでも残ってしまうのだ。別に悪いことではないが、時々、自分が携帯電話によって過去につながっていると実感させられる。
電話帳のデータ自体を消すのは容易だ。消したい連絡先を選んで削除すればいい。だが滝上はめんどくさいというそぶりをしながらもそれを実行せず、過去との繋がりを断つのをためらっている。実際、故郷で暮らしているかつての知り合いから電話がかかってきたあと、番号を改めて登録していたりもする。彼もまた故郷に対して嫌悪を抱きつつも完全には憎みきれなかったに違いない。そんな彼が刑事としての経験と誇りをかけ、故郷と父親とに戦いを挑む様にぜひ注目して欲しい。
いくら故郷と縁を切ったつもりで天涯孤独を気取っていても、故郷への愛を捨てきれない滝上の姿は読者からの共感も得られるのではないだろうか。
それゆえに。
故郷を愛しつつも、故郷を嫌うすべてのひとに――赤の呪縛から逃れようとしたことのあるすべてのひとに、本書を捧げたい。