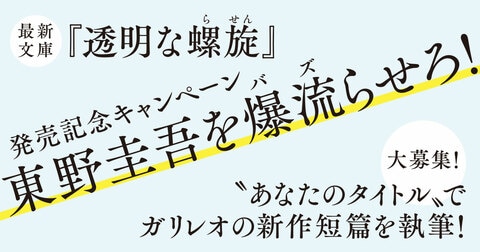日本文藝家協会・編の年間アンソロジーの最新刊『夏のカレー 現代の短篇小説ベストコレクション2024』をお届けする。二○二三年の一月から十二月までに、ウェブ雑誌を含む小説誌や出版社のPR誌などに掲載された短篇小説から、優れた作品を選出したものである。
二○二三年は、新型コロナウイルス感染症が五類に指定されたため社会は表面的には元の状態を取り戻したように見えたが、コロナ禍自体が消えたわけではない。国内では政権与党の不正が次々と明らかになり、海外ではロシアのウクライナ侵攻が始まって一年を超えた一方、ハマスからの攻撃へのイスラエルの過剰な報復にアメリカが肩入れし、民主主義国家も権威主義国家もエゴと不公平をそれまで以上に剥き出しにするようになった。
まことに不安な揺らぎに満ちた世相だが、無論、小説はそうした世相を反映するとは限らない。特に短篇小説は、枚数が少なく、描ける事柄も登場人物の数も限定されるため、身近な世界を描くことが多い。このアンソロジーの編纂委員として、一年間に発表される短篇小説の殆どに目を通しているけれども、大部分は身近な領域の物語である(本書はテーマ別のアンソロジーではないのだが、結果的に収録作は、家族のありようや、元同級生との関係を描いたものが多くなった)。
しかし、善悪の基準がわからない、正しい価値観がわからない、人間の本質がわからない、どう生きればいいかわからない――そんな混沌の世において、小説は、ささやかながらもそのヒントを読者に授ける。たとえ枚数は少なくとも、そこには作家たちの大胆な空想と、魂を削るような思索が籠められている。それは、読者である私たちの空想や思索を刺激し、新たな価値観に目覚めさせるかも知れない。読書とはそんなスリリングな体験であることが、本書収録の十一篇からも窺える筈だ。
江國香織「下北沢の昼下り」(初出「小説新潮」一月号)
語り手の「私」は、七十二歳の母や高校一年生の娘とともに下北沢のヴェトナム料理店を訪れている。「私」の妻は三度目の家出中だ。母と娘は年齢が大きく離れているが、まるで親友同士のように仲がいい。
読んでいるうちに、どうやら「私」は相当な浮気性で、しかもそれにあまり罪悪感を覚えていないらしいことが判明する。周囲の女性たちからは意志がないと評される男性の内面を、ある昼下りの家族のスケッチを通して描き出した試みである。
三浦しをん「夢見る家族」(初出「小説すばる」一月号)
両親と兄と暮らす少年・ネジ。彼の家庭には、よそとは違う習慣があった。朝、夢の内容を母親に話さなければならないのだ。母親が期待するような夢を語る兄と、そうではないネジの扱いに差が生まれてゆく。
最初は少し変わった家族らしいぐらいの印象で読んでいると、次第にこの一家の異常さが浮上してくる。だが、普通とは、異常とは何を基準にして決めるものなのか。そして夢と現実の境界とは――読者の中にそんな不穏な問いを残してこの作品は閉幕する。
乙一「AI Detective 探偵をインストールしました」(初出「STORY BOX」六月号)
AI探偵の「僕」は、妹を殺した犯人を捕まえたいという依頼を受ける。といっても、容疑者自体は既に浮上しているけれども、証拠が不十分なのだという。AI探偵が推理によって導き出した結論とは?
今や、ミステリの世界でもAI探偵が登場する作品は珍しくなくなったけれども、AIの一人称で展開する作例は稀有と言える。いかにも著者らしい切れ味鋭いどんでん返しも読みどころだが、人間を模倣しつつ人間ではないAIの思考回路の描写にただならぬ説得力を持たせた点も見事である。
澤西祐典「貝殻人間」(初出「小説新潮」八月号)
海から貝殻とともに上陸し、生きている人間と瓜二つで、本人の生活を乗っ取ってしまうという「貝殻人間」。彼らに人生を奪われた八人の男女が夜の海辺に集まり、それぞれの境遇を語り合う。
八人の中には、貝殻人間に人生を奪われたことを嘆く者もいれば、逆にそれまでの人生を捨てられてすっきりした気分の者もいる。同じ不条理な目に遭っても、人間とはそれぞれ異なる思考や感情を紡ぐ存在だということが、奇抜な発想の中で語られる幻想小説だ。
山田詠美「ジョン&ジェーン」(初出「小説幻冬」八月号)
何度も死にたいと訴えるジョンを、バスタブに沈めて溺死させたジェーン。良家の生まれながら歌舞伎町のトー横で過ごすようになった彼女と、ホストだったジョン。二人はどのように出会い、この結末に至ったのか。
歌舞伎町で生きる男女の刹那的な生き方に、『野菊の墓』などの文芸趣味を絡ませた作品。破滅的な結末が冒頭で明かされているだけに、そこに至るまでの決して暗いばかりではない経緯が哀しい。ジョンとジェーンというネーミングも効いている。
小川哲「猪田って誰?」(初出「STORY BOX」九月号)
「猪田の告別式、どうする?」というLINEが届いたが、「俺」は猪田が誰なのかを思い出せない。かつての同級生たちに連絡を取り、情報を集めてゆくが、それでも猪田のことがさっぱりわからないのは何故なのか。
昔の体験や知人の名前などが思い出せないという経験は、ある程度歳をとれば誰にでもある筈だ。そんな時に自分の記憶力に対して感じる不安を、この小説はまざまざと思い起こさせる。コミカルさと、読者を宙吊りにするような恐ろしさを同時に漂わせる語り口は比類がない。
中島京子「シスターフッドと鼠坂」(初出「オール讀物」九・十月号)
夏休みで富山に帰省中、「わたし」は母の珠緒の出生に隠されていた事情を聞いた。珠緒の実の母は祖母の澄江ではなく、東京に住む志桜里という女性だった。澄江と志桜里は学生時代からの親友なのだという。
シスターフッドという言葉はあまり肉親のあいだでは使われない印象があるが、「わたし」が一見平凡な珠緒の非凡さを見抜き、珠緒が苦手な実母の志桜里をあるきっかけで好きになるなど、肉親間の同志的感情を細やかに描いた点に本作の美点がある。
荻原浩「ああ美しき忖度の村」(初出「オール讀物」九・十月号)
二十年前に今の村名になった忖度村。だが、忖度という言葉に悪い印象がついてしまったため、「忖度村イメージ向上委員会」が結成された。ところがメンバーが村の有力者の意向を窺うため、会議は一向に進まない。
主人公の若手村議会議員・黒崎美鈴は、忖度が蔓延る村の空気に抗おうとするが、その結果は……。コミカルなタッチで日本社会のありようを諷刺した快作であり、こういう短篇を書かせれば絶品である著者の本領発揮作となっている。
原田ひ香「夏のカレー」(初出「小説新潮」九月号「冴子」を改題)
葬儀から帰宅すると、冴子が家の前で待っていた。二十歳で初めて出会い、その後、人生の節目で何度も再会と別れを繰り返した冴子。彼女との結婚を望んだこともあったのだが、叶わぬまま互いに六十歳になっていた。
互いに愛し合いながら、ボタンの掛け違いのように結婚には至らなかった男女の人生を、しみじみとした哀感とともに綴った傑作である。意表を衝く結末によって、それまで見ていたつもりの光景が別のニュアンスで読者の前に浮上する技巧も絶品だ。
宮島未奈「ガラケーレクイエム」(初出「小説現代」十月号)
解約したつもりで忘れていたガラケーに、元同級生・葉月からの「渡したいものがあります」という二年前のメッセージが届いた。それほど親しかったわけでもない葉月が、「わたし」に何を渡したかったのか。
皆がスマートフォンを使うようになった今、ガラケーはもはやレトロ感を漂わせる存在だ。そんなガラケーのイメージに、かつての同級生との再会にまつわる感傷とを重ね合わせた点が巧みで、短篇小説のお手本のような完成度を示している。
武石勝義「煙景の彼方」(初出「小説新潮」十二月号)
小学生の頃、「私」は祖父が煙草の煙で作った輪の中に、その場にいない母の姿を浮かび上がらせるのを見た。成人した「私」は、かつての祖父のように、煙の輪に見たい光景を浮かび上がらせようとしたが……。
煙の輪の中に見たいものを見る能力というのは、恩寵なのか呪いなのか。人生は不可逆であるからこそ、禁忌を犯してでも戻りたいと願う地点がある。奇想天外な短篇も得意とする著者だが、本作は幻想的な設定ながら、しみじみとした味わいが特色だ。
世界は悪意や絶望に満ちており、同時に善意や希望も溢れている。短篇小説は、そんな矛盾だらけの世界を、ある切り口から捉えようとする営為だとも言える。この国の作家たちが、そんな世界からいかなる切り口を見出したか――その優れたサンプルである本書を、是非手に取っていただきたい。