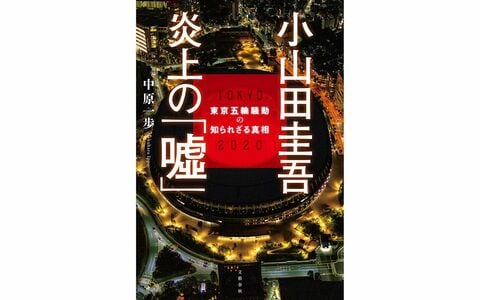〈病気や障害に感謝なんかしていない。後悔と反省をしながらそのまま生きています〉から続く
スタンリー・カヴェルという哲学者がいる。2018年に亡くなっているから、まぁほぼ現代において活躍した人物といってもよい。カヴェルは、かなり特異な哲学者だ。もしその特異さを垣間見たければ、ちょうど「翻訳不可能」と目されていた主著『理性の呼び声』の邦訳が、講談社選書メチエにて空前にしておそらく絶後になる分厚さで今年刊行されている。物理的に手にとって任意のページを開いてもらうだけで、その特異さの一端は伝わるだろう。
カヴェルの特異さは色々あるが、ここで注目したいのは、「一種の哲学は、一種の自伝としてしか語ることができない」という彼の謎めいたテーゼである。哲学が自伝だって? たしかに彼は、現に論文と自伝とが混淆した、類例をみないスタイルをとった哲学者だった。しかし、その「自伝としてしか語れない」ものとは、いったいなんなのだろう。

石田月美『まだ、うまく眠れない』(文藝春秋)を読みながら、私はこの問いをずっと反芻していた。本書もまた、一種の自伝であるのだが、たしかに“このようにしか語りえない何か”を体現していると思われたからだ。そして、何度か読み返していて、その「何か」に迫るヒントを見つけたような気がしている。それはつまり「移動」と「変容」の経験そのものなのではないか、と。
『まだ、うまく眠れない』は特異な本だ。語られている内容、つまり著者がたどってきた人生それじたいも数奇で波乱に富んでいるのだが、そればかりでなくその語り方、すなわち“文体”が独特なのである。本書は、著者みずからの半生をその時々の観点からふりかえり、当時の事実やエピソードを経由して、またいまに立ち戻っていく――そんな構成のエッセイ集である。
ふりかえる過去は、いち早くルッキズムに晒された幼少期から、「ワルっぽい仲間」とつるんだ団地での思春期、摂食障害やウツ、ひきこもりを経験した青年期まで。それぞれの時期にそれぞれの苦悩があり、その時々をともに生きた仲間がいる。著者は、それらをくぐって「妻」になり「母」になった現在から、過去をかえりみる。しかし、その筆致は「乗り越えたいま」から当時の「渦中」を覗きこむようなものでは、まったくない。
ときにファニーな表現や当時のことばづかいを交えながら、あくまで事実とエピソードがおさえた筆致でつづられる。そこではある種の自己憐憫はおろか、当時の自分を理解したり、いまここに至るために必要だった過程として意味づけたりするようなそぶりさえ、徹底して排されている。みずからの過去と仲間を語るさいの端正で真摯、慎重な言い回しと、いまを笑い飛ばすかのような軽妙でポップな表現とが混淆し、この本にしかない文体というものが立ち現れる。
著者は、ぎりぎりまで、かつての自分や仲間たちがいだかざるをえなかった「当事者性」の引力圏に危ういところまで慎重に迫りながら、そこでスイングバイして高速で遠ざかっていく。この緩急のリズムと絶えず移動しつづけるスピード感が、本書を推進している。切実さと諧謔。どちらの極にもいってしまわぬよう、そのあいだで往復をし続ける、そんな文体だ。
文体が物語るように、著者は「移動」の人物でもある。障害と健常。団地の街と大都市。当事者と非当事者。その間での移動とはしかし、一方向的な「克服」や「成長」「卒業」などではない。あえていえば一種の「回復」なのかもしれないが、このことばは字面からわかるように一種の循環的な構造をもっている。すべては人生の円環のなかで起こる、一連の出来事なのだ。

プロフィール 1985年大阪生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。大阪大学社会技術共創研究センター招へい准教授。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。著書に『<公正(フェアネス)>を乗りこなす 正義の反対は別の正義か』『100分de名著 ローティ「偶然性・アイロニー・連帯」』など。
作家とは移動の人物である
ある場所にずっといるとき、ひとはその体験を語る必要がない。そこには仲間うちでの符号と一種の方言があり、そこから「外」に向かう契機はない。ある場所から別の場所に移動したとき、自分がどこから来たのかを説明するために、はじめてことばが必要になる。それは、かつての自分を他者として、かつての仲間たちをいまの自分から切り離し、客体化することである。そういうことは「新しい場所のことば」でもって、おそらくできる。
以前のことばでも新しいことばでも語ることができないのは、かつてからいまに「移動」したという私自身の経験であり、そこで起きた「変容」そのものである。移動した前後、そのはざまの距離に囚われざるをえないように生きているという事実そのものを、――説明ではなく――表現することはむずかしい。そのためには、自分にしか書けないようなことばが、いや、そんなものはないのだから、ことばの組み合わせと連ね方、要するに「文体」が必要になる。この意味での「自伝」を描くということでしか表現できないのは、そういう“生きざま”だ。
哲学にも、ときにそういうふうにしか書けないことがある。思想的立場や主義主張のだいたんな変容というものが、人生には起こる。かつて擁護することをめざした思想を、もはや無価値どころか有害なものとしてしりぞける――そんなことが起こりうる。それは、かつての立場がたんにまちがっていたのでも、いまの立場がたんに正しいのでもない。ある立場から別の立場に移動せざるをえなかったという、その切実さそれじたいがある。
『まだ、うまく眠れない』の著者にも、この切実さがある。著者は、かつての自分や仲間たちに、いまの自分を擁護したりしない。かつての自分や仲間たちを批判したり、論駁したりもしない。しかし、その渦中にある危うさを否定せず、そこにぎりぎりまで迫る。そして、かつての自分と自分とともに生きていたひとびとを表現、つまり「代理」して語ることの危うさをも、乗りこなしてみせる。
危うさとは一種の身体感覚である。だからこそ「自分だけの、身体になじむ(なじまさせたい)文体」が、必要になる。独自の文体をもつことが作家の条件であるならば、作家とは移動の人物である必要があるのかもしれない。そして、本書はその意味において作家の手になる、したがって「文学」と呼ばれるべき自伝なのだ。