
CREA2025年夏号「1冊まるごと人生相談」の発売を記念して、7月3日・4日の両日にわたり、代官山 蔦屋書店で、2夜連続のトークイベントが開催されました。第1夜に登壇したのは脳科学者の中野信子さん。(第2夜は画家でモデルの浅野順子さんと、音楽評論家の近田春夫さん)
初の人生相談本『悩脳(のうのう)と生きる 脳科学で答える人生相談』を上梓したばかりで、CREA夏号にも登場された中野さんに、「人はなぜ悩むのか?」をテーマにお話をお聞きしました。(後篇を読む)
“科学に基づいた”お悩み相談とは

――新刊『悩脳と生きる』の元となった「週刊文春WOMAN」の連載では、6年間で100人近い方の相談に乗っていただきました。中野さんにとって人生相談の連載は初めてのことだったそうですね。
中野 まさか自分が人生相談に乗る立場になるとは考えたこともなかったです。子どもの頃から、私が相談しなければならない側だと思っていましたので。連載のお話をいただいたときは、お引き受けするのはなんだかおこがましいのではないかという思いが先に立ちました。
でも、科学者の一員として、科学で分析されている結果に基づき「このように行動した方が後悔はしづらいですよ」「あなたが心配されていること現実に起こる可能性は極めて低いですよ」とお伝えすることはできる。そう思ってお引き受けしたんですね。
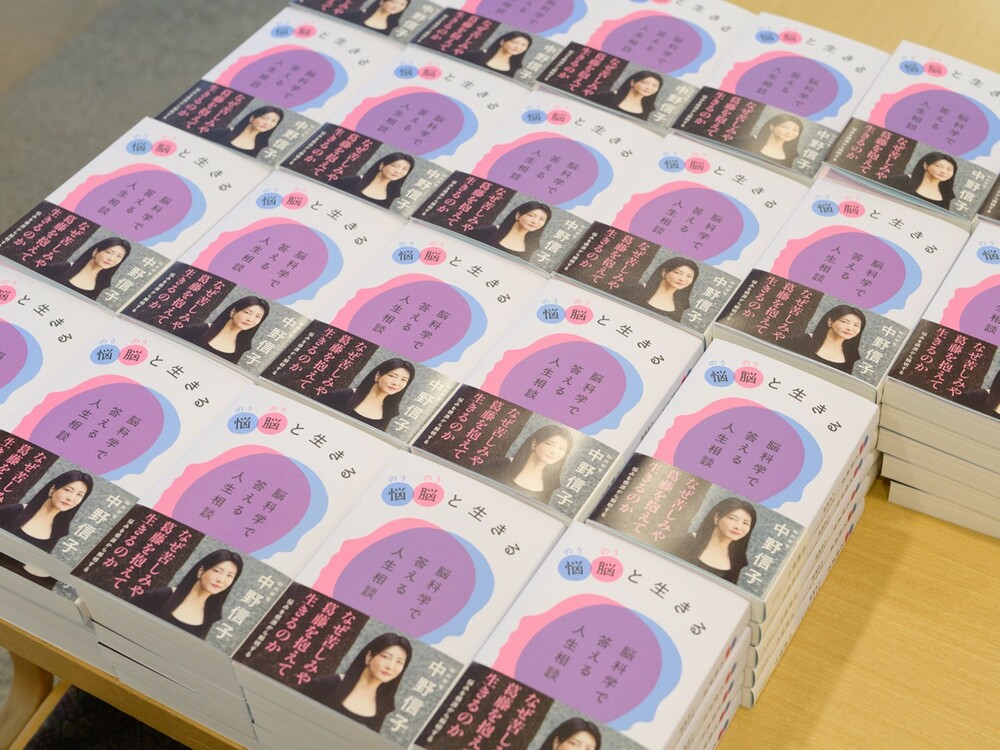
――もう連載の初回から、「私は話し始めると止まらないんです」というお悩みに対する回答が非常に科学的で感嘆しました。先ほどやや長めの挨拶をした司会役、「CREA」と「週刊文春WOMAN」2誌の編集長からの相談だったのですが。
中野 話が長いということは、言語運用能力が高いということなんです。だから、文章を書いたり編んだりするお仕事に就いたんですよね。優れた能力を活かしているわけです。
側頭葉に上側頭溝(じょうそくとうこう/STS:Superior temporal sulcus)という場所があって、そこが空気を読んだり、文章を構成したりしています。このSTSをコンピュータでボリュームメトリー(容積計測)すると女性のほうが若干大きい。
ですから言語運用能力は女性のほうが高いと考えられるんです。きっと紫式部さんや清少納言さん、和泉式部さんのSTSも大きかったのではないかと思います。

――このように中野さんの人生相談では、科学的な知見を分かりやすく翻訳してくださるわけですが、もう一つの特徴は作りこまないこと。どんな相談も、初見で、その場ですぐ回答されていましたね。
中野 作りこんだものは、しらじらしく感じませんか? 私自身はインプロビゼーション(即興)のほうが好きで、ライブ感を大事にしたいという気持ちが強いんです。決して怠けていたわけではないんですよ(笑)。
――本日もこの後、お悩みにお答えいただきますが、中野さんには何もお見せしていません。ぜひライブでお楽しみください。
悩みを切るか、悩んでいる人を抱きしめるか

――中野さんは脳科学だけでなく、心理学もご専門ですね。
中野 私は、カウンセリングはロジャーズ流を旨としています。ロジャーズ流というのは、まず傾聴する。「こういうふうに思っていらっしゃるんですね」と、相手の言うことを否定しない。日本の方は、否定されたくない、自分を認めてほしい気持ちが強い。だから私はご相談にはロジャーズ流を基本としてお答えしてきました。
かつての人生相談、例えばみのもんたさんなどは「そんな男とは別れなさい!」と言って、よく相談者が怒られていましたよね。実は回答者に切りまくってほしいと思っている人が一定数いらっしゃって、そういう方にはロジャーズ流は向きません。……そういう方向けに、私が相談者を切ってみるという別仕立てのご相談をやってみてもいいかも?
――お悩みを厳しく切っていく?
中野 なぜそんなことを考えるのかというと、先日、ベネチア・ビエンナーレ国際建築展に行きまして、パラッツォ・グラッシという16世紀の建築は天井が美しかったので、それを写そうと、下から煽った自撮り写真をインスタに上げたのです。以前から「中野さん、僕のことを踏んでください」というメッセージが定期的に来ていたので、一括でお返事するつもりでアップロードしたら、Yahoo!ニュースになっちゃったんです(笑)。
――(会場笑い)
中野 そういう需要も一部あるかもしれませんが、『悩脳と生きる』は、踏んでほしい人ではなく、抱きしめてほしい人向けの本です。
人間は事実より嘘を好む生きもの

――寄り添う姿勢と言えば、悩んでいる人を否定しない。「つい嘘をついてしまう」という44歳の公務員の女性のお悩みへの回答は驚きました。
中野 印象に残るご相談でしたね。私たちは初対面の人とお話をするとき、10分間の間に平均3回嘘をつくということが知られています。例えば、自分の経歴についてよく見せようとして盛ったり、逆に省いたりしてしまう。
ただ、この相談者の方は罪のない嘘をつくんですね。「空港で香取慎吾さんを見かけた」という作り話をしたり、みんなをちょっと楽しませる嘘なんです。
ところで、みなさまは昨年、小説や漫画、映画といった「フィクション」に支出した額と、学術誌、ノンフィクションやニュースといった「事実」に支出した額とでは、どちらが多かったですか。おそらく、フィクションに使うお金の額の方が大きかったのではないでしょうか。
私たちは、どちらかといえば嘘のほうが好きで、事実はそんなに好きじゃない。嘘のほうが面白くてみんなの気持ちを惹く。そういう才能があるなら、なぜ公務員という、嘘が許されない仕事に就いたのか? エンタメの世界に進めば、超大作を作ったかもしれないのに、もったいない。今からでも遅くはないのではないかというお答えをさせていただきました。
有名人からの深刻な悩み相談

――読者からだけでなく、俳優、漫画家など有名人のみなさんからも相談が寄せられました。イメージを大事にしないといけない職業と思われるのに、全力で相談された方がいましたね。
中野 俳優の要潤さんですね。スラッとしたイケメンで、ちょっと自虐的なところもあって面白く、悩みなんてなさそうな印象ですが、深刻に悩んでいらっしゃいました。
――騒音に悩まされやすい、すぐにびっくりするなど、「繊細さん」チェックリストにことごとく当てはまる。自分が繊細さんだと分かって気が楽になったという人が多いが、自分は気が楽になるどころか繊細ぶりに拍車がかかってしまったというお悩みでした。
中野 自分は繊細さん(HSP/Highly Sensitive Person)かどうかを知ろうとすることがバズった時期がありました。その結果、自分は繊細さんだ、そういう自分ではいけない、だから不安にならないように自分を鍛えなければいけない、不安にならないためにセロトニンを増やそう、セロトニンを増やすためにハグしよう、そうすれば不安が消えますよというのがすごく流行ったんです。
はたしてそれでHSPが治ったでしょうか? 何度やってもうまくいかなくて、むしろさらに自分を責めたり、あるいは自分を安心させてくれないパートナーに詰め寄ったりする人も多かったのではないかなと想像します。
不安や悩みは人として輝かしいこと

中野 私たちが不安になりやすいということは、そんなに悪いことではないんです。それは、自分のフィードバックが定期的にできて、明日は今日よりよくなろう、明後日はもっとよくなろうという気持ちが強いということの表われでもあるのですから。
ただ、不安な気持ちがあるのは辛いですよね。その不安な気持ちはどういう機序で起こるのか、日本にはなぜ不安な人が多いのか――ということも交えて回答しました。
――続きは本でぜひ(笑)。そもそも「人はなぜ悩むのか」、本イベントのテーマで、みなさまも興味があると思うのですが。
中野 本当に興味ありますかね……?
――(会場笑い)
中野 「人はなぜ悩むのか」、クリアカットに答えたほう爽快だし、面白いというのもわかります。でも私たちはそれをやるには大人になり過ぎてしまって、人生がもっと複雑であることも知っているし、なんなら、こんがらがっているほうが面白いような気すらしている。
そして悩まないことは「強さ」でも「優秀さ」でもありません。悩みを持っているということは、人として輝かしいことなんです。
本当の「自己肯定感」とは


中野 いっときブームになった「自己肯定感」についても、悩んでいる人は自己肯定感が低い、「自分がはすごいんだ」と思うことが自己肯定感だと思っている人が多いようですが、それは違います。どんなにみじめな自分でも生きていていいと思うのが自己肯定感なんです。
私が理事を務めている森美術館では、本年1月まで「ルイーズ・ブルジョワ展」を開催していました。ルイーズ・ブルジョワはフランス生まれのアーティストで、幼児期に父親から虐待されて育った人で、インスタレーション、彫刻、ドローイング、絵画など多くの作品を遺しました。夫のハンカチに刺繍した作品があるのですが、何が刺繍されているかというと、
I HAVE BEEN TO HELL AND BACK. AND LET ME TELL YOU, IT WAS WONDERFULL.
/地獄から帰ってきたところ。言っとくけど、素晴らしかったわ。
これこそ自己肯定感。偽の自己肯定感でキラキラした人生より、地獄に行って帰ってきて、「地獄も素晴らしかったわ」と言えるような人が、私は素敵だと思います。
定価 1,650円(税込)
文藝春秋
失敗が怖い、恋ができない、SNS疲れ……。ままならない悩みを科学目線で解明する「週刊文春WOMAN」の人気連載を書籍化。読者と有名人の悩みに答えるほか、森山未來、二階堂ふみらとの対面相談も収録。
中野信子(なかの・のぶこ)
1975年東京都生まれ。脳科学者、認知科学者。東日本国際大学教授、京都芸術大学客員教授、森美術館理事。東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻博士課程修了。医学博士。2008年から10年までフランス国立研究所ニューロスピンに勤務。著書に『サイコパス』(文春新書)、『新版科学がつきとめた「運のいい人」」(サンマーク出版)、『新版人は、なぜ他人を許せないのか?」(アスコム)、『児の脳科学』(講談社+a新書)など。「大下容子ワイド!スクランブル」(テレビ朝日系)他テレビ出演も多数。




















