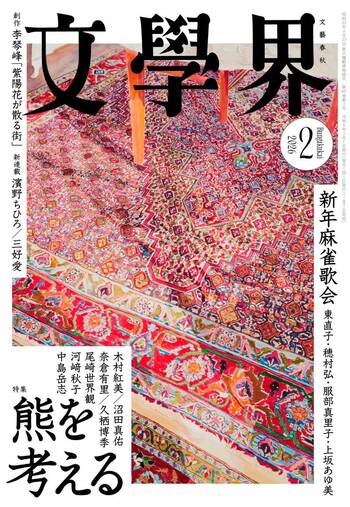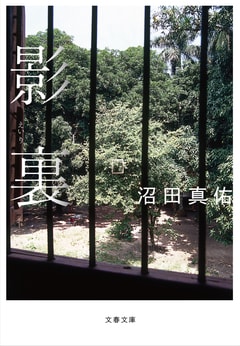昨年の「今年の漢字」にもなった「熊」について、近くから、遠くから、考える。「文學界」2026年2月号の特集「熊を考える」より、作家・沼田真佑さんのエッセイ「サバーバンのベア」を特別に公開します。
◆ ◆ ◆
玄関を出たら、クマと鉢あわせするかもしれない地域に住んで、この原稿を書いている時点での話だけれども、早一カ月になる。東北は岩手の盛岡市郊外、部屋の窓から見えるのはすでに収穫を終えた畑と冬田、そして川水のきらめき。その川というのは二本あって、ひとつはたっぷりした水量のある大きな河川、もうひとつはその支流に当たるさらさらした小川だ。木立ちもちらほら見える。裸木の根方にすがれた草の穂が揺れていたりして、ひなびたいい景色だ。気温はこのごろだと朝晩は氷点を下回る。十一月のあたまには初雪も観測された。

それでも晴れた昼間には窓からぽかぽかと日がさし、ストーブもつけているから暖気で眠くなったりもするのだが、この日は朝から集中が途切れず、机を離れたのは午後の二時過ぎだった。仕事に欠かせないのが音楽とタバコで、CDはもう十数枚消費していたが、タバコのほうは、部屋では吸わないことにしているので、そのつど台所に移動しなければならない。それが億劫で、今日はまだ寝覚めの一本しか吸えていないことを思うとむやみに吸いたくなってきて、ところが台所へおりてみると、あるはずのタバコがない。箱だけあって中身が空になっている。外出の必要に迫られたわけだが、そこは田舎町で、たったそれだけの買い物にも車を使うことになる。部屋着の上からジャンパーを羽織り、おっかなびっくり外へ出る。玄関のドアをあけ、タバコ買ってくるとか何とかひと声かける。屋内にではなく、むしろ戸外へ向けて。周囲をざっと見渡してから、わざと足音を立てて車まで歩く。
最寄りのコンビニは、車だと二、三分で着けるのだが、気分転換もかねて川向こうのコンビニまで足をのばすことにした。橋のたもとで信号につかまり、その信号待ちのあいだに車外の風景に目を走らせた。何も異常はない。どこにも黒い影はない。いや、遠くの農道にひとつあった。助手席から双眼鏡を取りあげ、目標物へピントをあわせる。廃タイヤらしかった。双眼鏡なんて持ってきたのはクマに対しての備えで、早めの発見を心がけているわけだ。コンビニの駐車場に車を入れても、すぐにはドアをあけない。まずはルームミラー、それから両サイドミラーに目をやって、しかるのち目視で周りの安全を確認したうえで車をおりるようにしている。けれどもそれは、本当に危機意識からの行動だろうかと、買い物を済ませて再び車に乗りこもうとしたところで、自問した。興味本位からのことなんじゃないかと。
そう、私はクマが見たいのだ。ここで私のクマへの思いをわかってもらうために、書いておかなければならないことがある。自分の来歴についてだ。私は北海道で生まれた。生後半年ほどで親の転勤で神奈川に引っ越し、それからは千葉、埼玉と中学にあがるまで関東の町々で過ごした。そしてその幼少年期をとおして誰しもがそうなるように私も動物好きになった。図鑑が一番の友達みたいな時期もあった。どこに行きたいかと大人に訊かれてリクエストするのは、野毛山動物園やマザー牧場、サンシャイン水族館だった。
小学二年くらいのころだったか、自分は動物のなかでも、とくに食肉目に属する動物が好きなのではと思うようになった。図鑑のそのあたりのページがよれよれになっていたからだ。ことにイヌ科とクマ科、さらにいうと日本の野生環境下で見られる動物に不思議な愛着をいだいていた。そこからニホンオオカミとニホンツキノワグマ、そしてヒグマの三種に興味がそそがれていったのは、私が男の子だったというのもあるかもしれない。それから少しして、ニホンオオカミがすでに絶滅していたと知ると、標的はクマに絞られた。そのあこがれに似た思いもあってのことだと思うけれど、小三のときの学級劇では金太郎のクマ役を買って出たりもした。
関東地方で幼少年期を過ごした私だが、母方の親戚が北海道に住んでいた縁もあって、北海道にはよく行っていた。夏休みには数週間滞在することもあり、そんなときには車であちこち連れて行ってもらい、キタキツネやトドなどといっためずらしい動物も見ることができた。野生動物がうようよしている印象の北海道だったが、どの大人の口からもヒグマを見た話は出なかった。そのころの私は、図鑑で得た知識を誰彼なくつかまえてはひけらかしていた。日本本土と北海道に生息している動物の違い、とりわけほ乳類について、北海道にはカモシカもニホンザルもいないこと、本土のクマはツキノワグマで、北海道のヒグマとはまるで違うことなど得々と語っていた。当時その町内にいた子供のなかでは、ブラキストン線に対する意識は高いほうだったと思う。
その後は中学から約二十年間、九州で暮らした。九州にもかつてはクマがいたようだけれど、私が住みはじめた九〇年代には、すでに九州にはクマはいないことになっていた。それに九州といっても、私が住んだのは九州地方第一の都市福岡市の、それも中央区内にかぎられてしまっていたので、そればかりが原因というのでもないだろうけれど、だんだんと野生動物に対する関心は薄れていった。代わりに射程に入ってきたのは、音楽や映画、文学といったいわゆる芸事の世界で、それでも何かの作品でクマが登場すると、幼なじみとでも再会したようで胸がおどった。
先ほど私は、九州にはクマはいないみたいなことを書いた。ところがその九州で、たとえば居酒屋なんかで男同士で話していると、ちょくちょくクマの目撃談が出た。河童やツチノコと似たような扱いではあったものの、そんな話を耳にするたび、クマは泳ぎが得意だから、山口県での目撃情報がある以上、関門海峡を泳ぎ渡ってくる個体がいてもおかしくないだろうと思うのだった。その九州時代に私は川釣りをはじめ、シーズンになると対象魚であるヤマメを求めて単身山に入っていたが、そこでも私はまだ見ぬクマとの出会いの期待から、竿を置いてしばらく周囲を探ったりもしていて、思えば悠長なことだった。
私は失業し、岩手で生活することになった
環境省が九州のクマの絶滅宣言を出した二〇一二年、私は失業し、岩手で生活することになった。実家に逃れたのだったが、実家といっても、ほんの数年前に親が終の棲家にさだめたようなところだったので、息子の私からしてみたらほとんど未知の土地だった。一人の知り合いもなく、ただし無職で、時間は無尽蔵にあった。それで覚えたのが自然とのつきあいで、岩手は自然の宝庫だった。虫捕り、植物採集、バードウォッチング、川釣り三昧の日々で、多くの野生動物を目撃したが、クマとは出会えなかった。しかしそのころにはもう、クマというものはそうそう見られるものではなく、山で何か獣の強い臭気を嗅いでも、仮にそれがクマのものだったとしても、向こうは周到にこちらを避けているものと信じこむようになっていた。爆竹も熊鈴も持たずに山に入った。森を歩いていて視線のようなものを感じても、ピッと笛を鳴らすくらいで済ませていた。キノコが気になって毎日山に行くようになる、冬眠をひかえたクマたちのほうでは食い溜めで忙しくなる、九月から十一月にかけても、私はかなり軽装で、どうかすると部屋着のまま出かけていた。
そんな私がクマと最接近したのは、九州から岩手に移住して、たしか三年目の、四月のことだったと思う。渓流釣りというのは三月が解禁で、四月の山は麓でもまだ雪が残っている。場所によっては雪が深すぎて、車を乗り捨てて川までの結構な距離を歩かされることになる。その雪というのが膝まで積もっていたりするからなかなかしんどい。今日はもう帰ろうと足をとめたとき、釣り人のものらしい足跡を見つけた。ためらいなく真っすぐ川へと続いている。これさいわいと私はその足跡をたどって歩きはじめた。踏み固められた道を行くのはずいぶん楽ですいすい歩けたが、少し進んで、それが人間がつけたものではないことに気づいた。クマの足跡なのだ。冬眠明けの顔でも洗いに行くのかと思うと微笑ましかったが、それよりはやはり身の危険を感じて、私は踵をめぐらした。
その数年後、私は実家を出て、仙台にアパートを借りて住みはじめた。丸六年住んで、十月の終わりにそこを引き払った。貯えが底をついたのだからどうしようもない。仙台での最後の夏は長かった。空きっ腹を抱えて終日ぼうっとしていることも多かった。九月に入り、退去日が近づいてくると、今のうちに仙台の町をよく見ておこうと思いはじめた。コロナ禍もあって行けずに終わっていた場所が多かったのだ。それで九月十月は足しげく外出し、市内を中心に歩き回ったが、なかでも気になっていた台原森林公園と東北大学植物園へは、結局行けなかった。そのころにはもう仙台の住宅地でもクマが目撃されるようになっていたのだ。あれほどクマを見たがっていたくせに、それがいざ現実味を帯びてくると及び腰になるのは、情報に毒されているようでいかにも情けなかったが、よしたほうがいいと親身にいってくれる人もいたので自重した。
そういうしだいで、私は再び岩手の実家に寄生することになった。移って最初の二週間くらいは驚きの連続だった。近所の防災無線から三日に一度、ときには日に数回、クマの出没情報が聞こえてきたからだ。A保育園の駐車場、B公園の体育館裏、C橋の北側の河畔と、いずれも耳慣れた場所だった。Z神社の参道下など、自宅から四百メートルたらず、人間の足でも走れば一分ちょっと、クマならその半分以下のタイムでやって来られそうな近距離だ。用心に越したことはないと台所で喫煙しながら双眼鏡のレンズを拭いていて、異臭が鼻を打った。見れば生ごみ用のポリバケツのふたがわずかにあいて中身が溢れ出そうになっている。今日は水曜日で、生ごみの回収は木曜だった。この地区ではごみ出しは朝にすることになっている。私はそんな時間には起きていないから、前夜のうちに出すようにしているのだが、何だか今日は夜の闇のなかを歩ける気がしない。日のあるうちに出しておこうとポリバケツから袋を引き出し、口を結んで、玄関を出た。
何かがうずくまっているのが見える
ゴミステーションまで、おおよそ百歩の道のりを歩いていく。あの雪の釣行の景色がよみがえり、いつにもまして警戒の目を配りながら、ゴミステーションにたどり着いた。重い引き戸を引いて、その物置のような小屋のなかへ入ると、ポリ袋を置き、隅に目をやった。あいた引き戸からさした外光を受けて、何かがうずくまっているのが見える。ずっと捨ててある段ボール箱で、サイズからいって幼獣だった。どうしてこんなところに、そんなに痩せて。今すぐここを出て、田んぼにおりたら川辺に柿の木がある、来年までの辛抱だ。しかしブナだっていつまでも実をつけてくれるとはかぎらない。ブナばかりじゃない、ミズナラもコナラも。山のドングリが凶作のときには早く冬眠するようにするとか、発情を抑えられるようになるとか、そっちも何か戦略を持ったほうがよさそうだ。
こっちも対策は打つ。境界線をはっきりさせる、うまくやっていこう。昔うちにいたポメラニアンとだぶらせて、クマにいい聞かせるところを思い描きながら自宅までの道を引き返した。いつも思うのだ、人間と同じように、言葉がつうじたなら。人間と違って憎みあうことにはならないんだろうに。木枯らしが吹いてきた。玄関まで、あと五十歩くらいか。