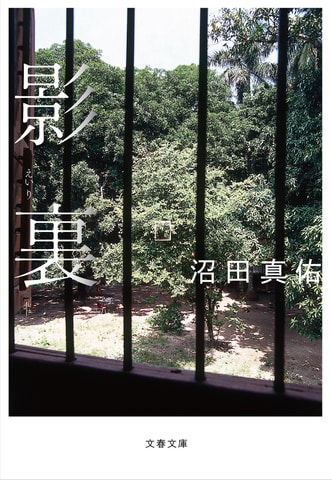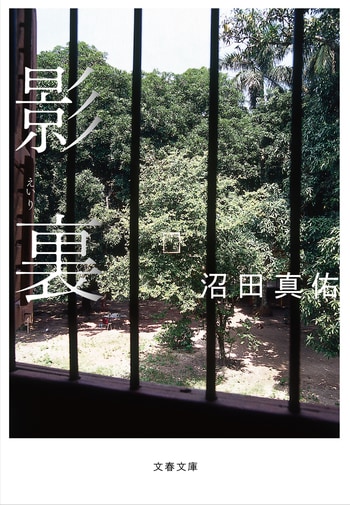見つめつづけていると、ふいに光と影が反転するようなくすんだ金色の屏風の前で、沼田さんは時おり筆を置いて、手を握ってはひらき、握ってはひらきを繰りかえした。勤務先の書店で、第一五七回芥川賞受賞記念のサイン会を催した際、参加者の整理券を受けとりながら、後方でわたしはその様子を見ていた。くりかえされる自動ドアの開閉や断片的な会話、題名を知らないクラシック音楽の合間に深く息を吐きながら、何度も閉じてはひらかれる手のひらへ、まぎれこんだ夜が小さく放射した。
サイン会を終えたあとの控室は、静寂につつまれていた。挨拶のため部屋に入ったわたしは、その静寂の濃密さにたじろいだ。上座にあたる席で鈍(にび)色のスーツにかこまれ、うなだれるように沼田さんが座っていた。それは喧騒ののちの息つぎのような、わずかな沈黙だったのかもしれないが、わたしは何か話さなければと焦燥にかられた。「影裏」の文体や、梅崎春生について話したことを覚えている。芥川賞受賞後のインタビューで、影響を受けた日本文学について、沼田さんが最初に名前を挙げた作家が梅崎春生だった。