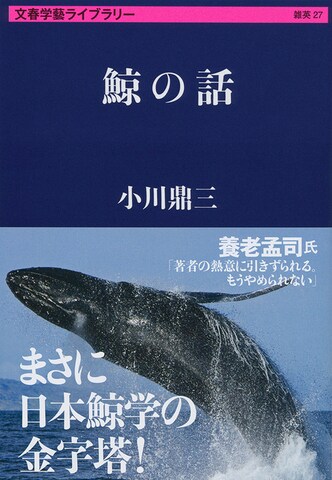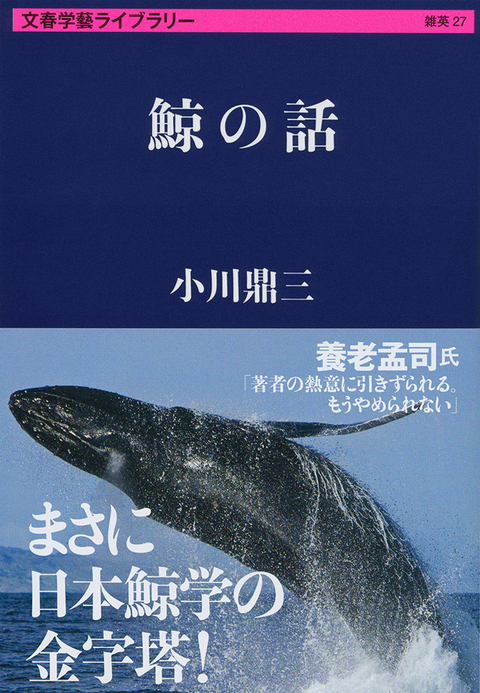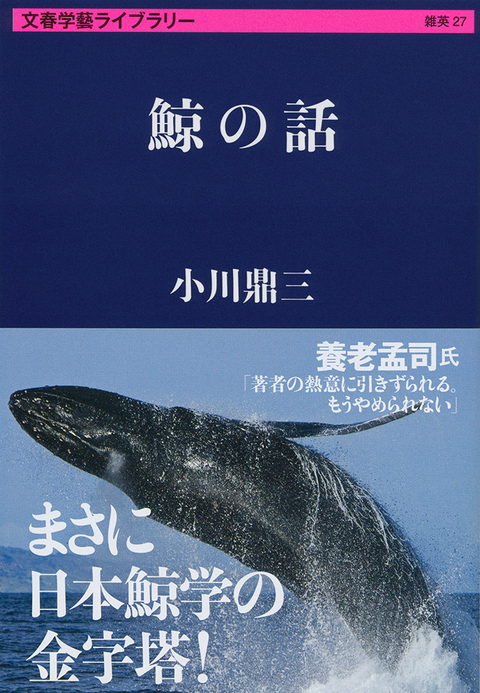
この本を読み始めると、たいていの人がそのままつい読み続けてしまうのではないかと思う。クジラはだれでも知っている動物だし、現代では世界中で人気が高い生きものの一つでもある。
そのせいで読んでしまうのかといえば、もちろんそれだけではないと思う。なにより著者の熱意に引きずられる。二十代の気鋭の学徒がさまざまな種類の動物の脳を研究しようと思っている。そこにマイルカの頭が持ち込まれる。それはいいが、次に持ち込まれた同じマイルカの頭を見ると、どうもなにか違う。ハテ、どれがマイルカなんだ。
そこでイルカの種類を正確に知りたいと思う。調べ始めて一つ問題が片付きそうになると、次の問題に気が付いてしまう。次から次へと問題が生じてくる。その追究が面白くなり、やめられなくなってくる。ついにクジラの分類学になる。江戸時代から日本各地で漁師がクジラを捕まえて、おかげで網元には成金までいる癖に、日本近海にはどういう種類のクジラが生息しているのか、それがまったくわかっていない。それもわかってくる。新知見の連続である。後年著者はこの頃のことを思い出すと、「血わき肉おどる」感があると書く。
著者がそこまで面白いと思ったことが、読む人に伝わらないはずがない。それにつられて、読者もつい読み進んでしまう。著者はクジラの専門家ではない。脳の解剖学を専攻している。だから本業からの抑制がかかるのだが、それでもともかくクジラ、になってしまうのである。
この気持ちはとてもよくわかる。自然の探求とはこういうことで、この種のことにいったん引き込まれると、もうやめられない。