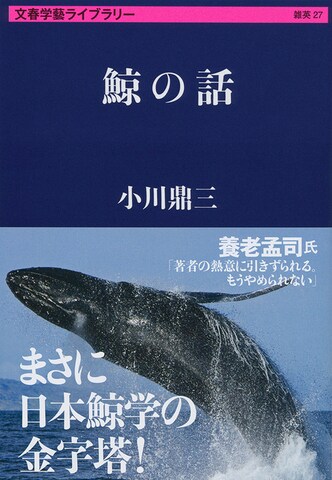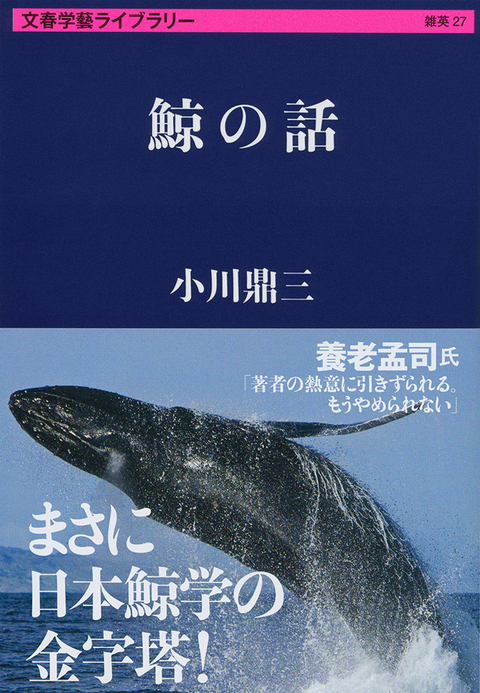こういうクジラの研究って、いったいなんなのだ。小川鼎三は自分の本業は脳の解剖学だと信じている。だからクジラばかりにかまけていられない。実際に小川は一九五一年、小細胞性赤核の研究で学士院賞を受賞、東大医学部に脳研究所を創設したメンバーの一人である。脳の比較解剖学研究という立場からすれば、クジラの研究も当然その視野に入るから、問題はない。さらに小川はそれを「ヒト山とクジラ山」という表現でのちに合理化する。それは本書にもあるから、おわかりいただけると思う。
ただし、である。クジラ学そのもの、クジラ自体の研究は、そこに含まれにくい。比較解剖学という立場からすれば、クジラ研究だって問題はない。でも小川はそこにどこか、後ろめたさを感じていた節がある。なにしろ医学部なんだから、ということである。この種の微妙な圧力は、当人にしてみると強圧である。著者がクジラ学を心置きなく研究するためには、他方で脳研究上の大きな実績を上げる必要があった。それをそれなりに果たしたことが、小川鼎三の偉さなのである。
ではそのクジラ学とはなんなのか。クジラの自然史 Natural History である。京都大学系なら自然「誌」、中村桂子さんなら「生命誌」。私は生物学は自然史で、それに尽きると思っている。八十近い爺さんなんだから、私がどう思おうと、世間の通念とはもはや関係はない。勝手に思わせておいてもらう。ファーブルは九十歳を過ぎて虫を観察していた。でもそれは、いったいいかなる行為なのか。
自然史とは、自然という世界を情報化する行為である。現代社会は情報の受け渡し、情報の処理と流通の時代である。人々は情報化されたもの、つまり情報を扱うことに狂奔している。そこで「なされていないこと」は、まだ情報化されていないことを、情報「化」する行為である。テレビでクジラを見るのは簡単である。多くのことを学べるであろう。でもその映像を撮ったカメラマンは、どれだけの時間を費やしたであろうか。報酬はその努力に見合っただろうか。いったいクジラのどこをどう撮影すればいいのだろうか。
自然史は自然科学の一次産業である。一次産業は都市社会では、価値的につねに低次の産業になる。気の利いた人はやらないほうが普通である。頭のいい人は情報を動かす方が率がいいことをよく知っている。でも結局は情報「化」が根本である。あらゆる経済統計でも、実態から数字をまず起こさなければならない。それはつまり百姓の仕事である。まさに「百姓は国の基」だが、仕事はきつくて、しばしば貧乏である。偉い人はそんなことはしない。代わりに考える。実験とは情報化の方法を組織化することである。大規模農業といってもいい。自然史は違う。小さな自営農民、さらに狩猟採集民を兼ねている。