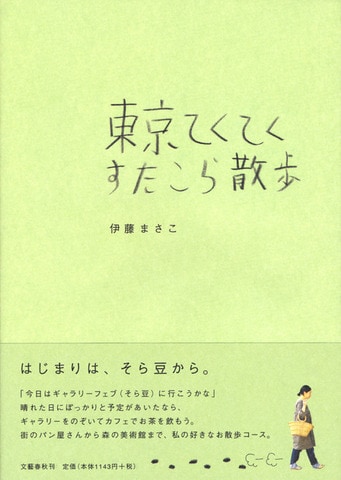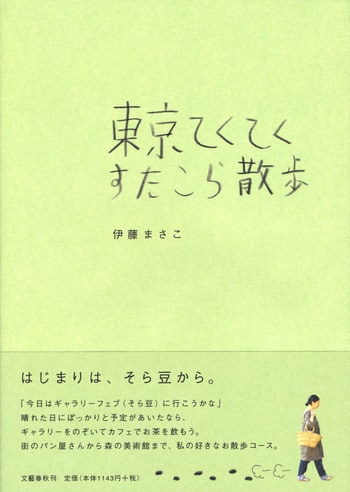僕の住んでいるこの場所は、能登半島の奥の方の山の中で、隣の家が1キロ向こうにあって、いちばん近いお店屋さんは、ずんずん山を下りて、4キロほど行った所にある。田んぼのまんなかを流れる川のほとりに一軒ぽつんとあって、いちおう「新谷酒店」という看板がかかっているけれど、地元の人には「えば」という謎の名前で呼ばれている。お酒だけではなく、お菓子やら缶詰やらの食品、雑貨、文具など、田舎の生活に必要そうなものはひととおりそろっている。とりあえず、村のコンビニなのだ。夕方には、農作業を終えたおじさんたちが、カップ酒と缶詰を買って、そのまま隣の土間に移動、立ち飲みでいっぱいやっている。棚を見ると半分食べ残したマグロ缶が、キープされていたり。もちろん、おしゃれなもの、かわいいものなど何もない。そんなお店屋さん事情の僕に、伊藤まさこさんのお友だちらしいという理由で、彼女の本の書評を書けというのだから困ってしまった。送られてきた本には、まさこちゃんがいつも通っているという、東京にあるおしゃれでかわいいお店屋さんが満載で紹介されている。じっくりと目を通してみたけれど、僕が行ったことのあるお店は美術館とか以外には一軒もない。といっても、全く知らないわけではない。ペリカンのパンとか、オーボンヴュータンのお菓子とか、何度か伊藤さんから送られてきて、うちの奥さんや子どもたちは、世の中にこんなにかわいくておいしいたべものがあるのかと、うれしくって泣きながら食べていた。
いつかまさこちゃんに「赤木さんのいちばん好きなたべものは何ですか」と聞かれて、「そりゃあ、鳥やら魚やら自分で捕まえて、殺して喰うのがいちばんウマイさ」と答えて、目を丸くしていたのを覚えている。その時彼女は、僕のことをなんて「野生的(ほんとうは野蛮)」と感じたかもしれないけれど、実は僕が彼女のことを気に入っているのは、彼女の中にも同じ野生がひそんでいるのを知っているからだ。理屈も何もなく、ほんとうにおいしいものを本能的にかぎ分ける能力というのかな。たまたま住む世界が違うだけで、彼女がもしもここみたいなド田舎に暮らしているとしたら、僕と同じように獲物を追い、殺戮に走っていたことだろう。その逆もまた然り。僕がもしも東京に住んでいたら(その方が恐いな)。