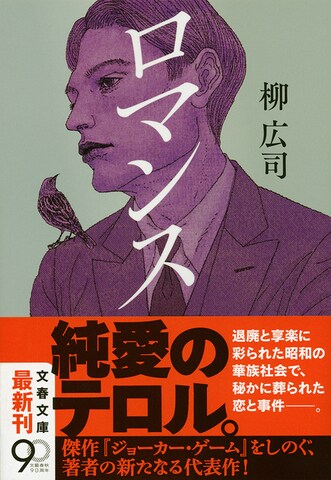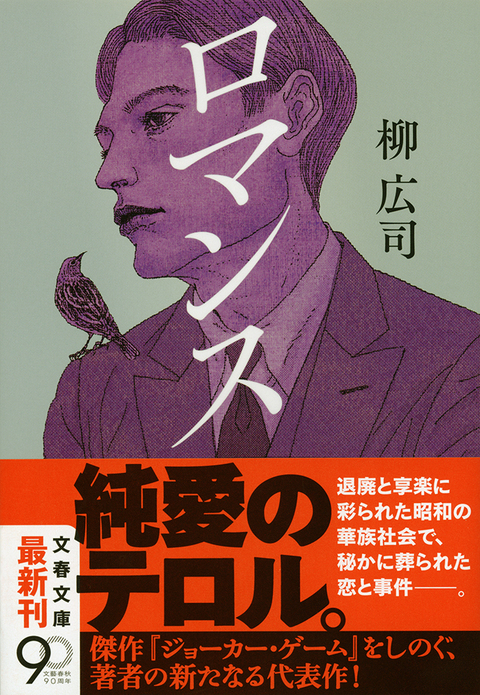“ロマンス”という言葉から思い浮かぶ景色が、この一冊で変わってしまった。
それまでは、ほのかな恋心や美男美女が繰り広げるメロドラマ的なイメージ、あるいは気品の感じられる紳士淑女の外見やたたずまいを想起していたものだが、理解が足りなかったようだ。いささか大時代的なニュアンスをまとい、真正面から受け止めるには気恥かしさをともなっていた言葉が、読み進めるうちに極めて真摯で胸が締めつけられるような切実な意味合いを増し、人間の根源的な“求め”を表したものであることに気づかされた瞬間は、目から鱗が落ちる思いであった。
――目の前に広がる、突き抜けるようにどこまでも続く青空。
――地上から憧れの失われた、即物的な灰色の世界。
一見“ロマンス”とは結びつき難いこのような景色が、いかに“ロマンス”を象徴し、本質を捉えたものであるか。もし本稿から目を通されている方で、真相を知りたいなら、いますぐこのページを離れて本編に移るべきだ。細やかな仕掛けが随所に施され、読み手の先入観をも逆手に取る精巧な物語は、タイトルからは想像もつかない方向へ大きくカーブを切り、何度も意表を突きながら、それでもやはりこのタイトルでなければならない結末へと着地する。ゆえに、現役ミステリ作家屈指の技巧師である柳広司が、そこに至るまでに盛り込んだ数々の妙技を余すところなくご堪能いただくためにも、ただちに本編に向かわれるべきだと強く念を押したい。とはいえ、なかには本書が初めての柳作品という方もいるだろう。なので、物語の入口を少しだけご紹介しておこうと思う。
柳広司の著作としては十八作目となる本書『ロマンス』の舞台は、昭和八年の東京である。物語は、ロシア人の血を引く眉目秀麗の青年子爵――麻倉清彬(きよあき)が上野のカフェー〈聚楽〉の一室に入ってくるところから幕を開ける。
部屋には、多岐川伯爵家の長男で帝国陸軍中尉――多岐川嘉人(よしひと:彼もまた、長身で浅黒い顔に、きりりとした眉が印象的な美男)、駆けつけた巡査、そして首の後ろにナイフが突き立つ男の死体――。嘉人が酒を飲もうと予約したこの部屋に入った際、すでに死体は転がっていたのだという。
だがそうはいっても、警察も第一発見者である嘉人を、そう簡単に帰すわけにはいかない。帰るなら身元保証人が必要だ――というわけで、結果、友人である清彬が突然呼び出されたのだが、清彬は状況を把握するや身元を保証するだけでなく、たちどころに嘉人のアリバイをも成立させてしまうのだった。
こうして友人の危機を救い、屋敷に戻った清彬だったが、思わぬ来客が彼の帰りを待っており、さらに後日、特別高等警察――“特高”が現れ、上野のカフェーで起きた殺人について尋ねてくるのだった。なぜ、反体制活動全般を取り締まる“特高”が殺人事件の捜査を? しかも清彬は、にわかには信じ難い驚くべき提案を持ち掛けられる……。
〈以降の文章は物語の核心に触れております。本編読了後のお目通しをお願い致します〉