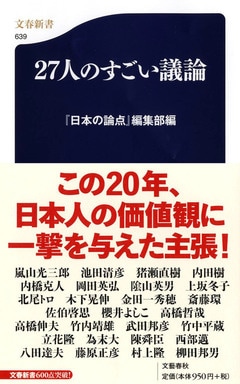安楽死や脳死など、長きにわたり、人の「死」をテーマに追い続けてきた立花隆さん。新刊『死はこわくない』(12月5日発売)は、最新の脳科学の知見を得て到達した理想的な「死」について語りおろした一冊です。がん、心臓手術を乗り越え、75歳になった「知の巨人」はいま何を思っているのでしょうか。その心境についてうかがいました。

――「死がこわくない」のはなぜですか?
自然にそういう気持になったんです。そのことに自覚的になったのは、今回の本を書き終えたときですね。気持的に、自然に死がこわくなくなったんです。だから、自分でいろいろ取材して調べた結果、ロジカルな結論としてそのような考えに至ったということではなくて、自然な気持の流れとして自然にそうなっていたということです。ぼくは今年75歳で後期高齢者になったんですが、その要素というのがいちばん大きい背景だと思います。
今回の本のなかでは触れていませんが、ロバート・カステンバウムというひとが、人間は年をとるとどういうふうに心境が変化するのか、年齢に応じてそのひとのこころがどういうふうに変わるのかについて書いています。そして、キケロも61歳のころ、『老年について』を書いています。この本は、大カトーが将来有望な若者二人を自宅に招いて老年論を対談形式で語るという体裁になっていますが、いま読んでも非常に面白い本です。とにかくいろんなひとが「老年」について書いていますが、そういうのを読むと、自分もそういう年齢になったこともあって、なるほどと思わされることが多いですね。
人間というのはおのずから、過去の蓄積の上にあたらしい日々を迎え、年をとっていくわけで、その蓄積が自分のなかで生きたものとして醸成され、そのひとの「いま」を作っているという側面があります。
やっぱり後期高齢者になってみないと、わからないことが相当あると思いますね。つまりあなた方はまだ若いから、後期高齢者になるのに何十年も必要でしょう。そういうひとは、自分では「死」を知ったつもりになっていても実は全然分かってない、というか分かりようがないということなんです(笑)。
――若い頃には、こうした心境に至るとは思いもしなかった?
そうですね、偉そうなことを若い頃から書いてきましたが(笑)、いま若いときに書いたものを読み直すと、チャンチャラおかしいという感じの部分が相当ありますね。
やっぱり年齢を重ねると、年をとっただけのことは自然とあるんですね。とくに人間が年をとったときにどうなるかとか(心身ともにですが)、それから死ぬことについてどう思うようになるかとか、そのあたりは自分が本当に年をとって死が近く見える年齢にならないと、本当のことはわからないと思います。
死がこわい、こわくないという話で言えば、もっぱら若いときは「死」がこわくて当然なんです。若さにとって死はアンチテーゼそのものですから。さらに、世の中にはいろんなひとがいて、敏感なひとと鈍感なひとがいるから、一概には言えないけれども、人間の生理的な思考におよぼす影響からして、若い頃はやはりこわいに違いないんです。ぼくにも事実、死というのを簡単には考えられないという時代がありました。
しかし、いまは慣れ親しんでいるという感じですね。ある程度の年齢に達したひとがどんどん死んでいくという、そういう年齢に入るわけですから、自然と「死」というものが慣れ親しんだものになってくるんです。だから、自然とこわくなくなりました。
――人間が死ぬときはどういうふうになるのでしょう。
今回の本や、20年あまり前に発表した『臨死体験』(文春文庫)でも書いたことなんですが、そのひとが死ぬ状況によってずいぶんちがうと思います。そのひとの肉体的条件、あるいは短い人生の時間幅のなかで、どういう時間帯のなかに位置しているのかっていうね。そういうことがものすごく影響すると思います。ただ、基本的に年をとったひとであれば、自然と落ち着いた気持で死にアプローチできるようです。
最晩年にいろんな出来事や状況変化があって、精神的に混乱をきたすようなことに遭遇したひとには当てはまらないかもしれませんが、ごく普通に後期高齢者を迎えたひと、そういうひとは自分自身の人生をルックバックすると、60代後半だとまだでしょうが、70歳を超したあたりからすごく安定した気持になるものなんです。そしてさらに5年たって後期高齢者になる。この5年は大きいですね。ぼくもそうですが、周囲に亡くなる人がふえて、そのたびに落ち着いて全体を振り返れるようになる。
自分の人生全体を過去のものとして振り返る。いろんなことがあったにしても、気持として全体を見渡せる心境になったときというのはね、個人差があるにせよ、大半のひとはすごく安定した気持で振り返ることができるんではないでしょうか。
ある意味で「死にどき」と言うことができると思いますが、そうした「いつ死んでもおかしくない」時期に自分自身が差し掛かったんだ、ということでしょうね。