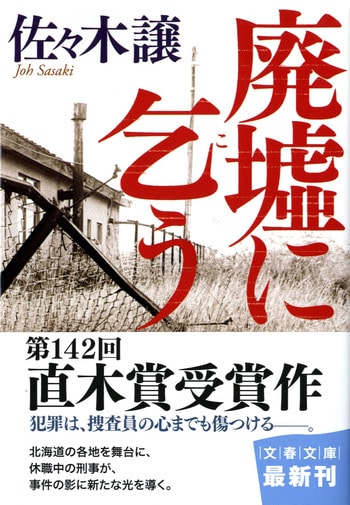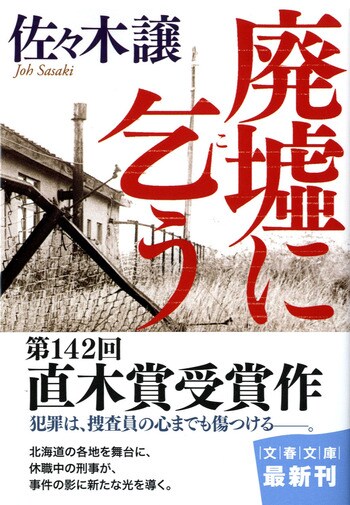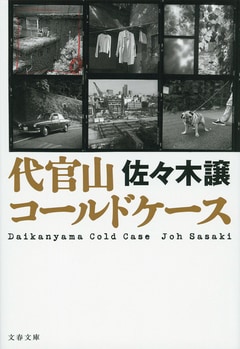──佐々木譲さんの新作『廃墟に乞う』は、この秋映画が公開されます『笑う警官』などと同じく、北海道警察の刑事が主人公です。しかし、他の作品と大きく異なるのは、主人公である道警本部刑事部捜査一課の仙道孝司は、「休職中」という特殊な立場であることです。なぜ、「休職中」としたのか、その理由を教えてください。
佐々木 小説の依頼を頂いたとき、北海道という舞台をうまく使えれば、過去の作品とは角度の違う警察小説が書けると思ったんです。北海道の場合、広大な面積ですから、各方面によって担当が分かれています。つまり、道警本部に在籍していても、北海道全域の捜査に関わることはできないんです。そうすると、書ける地域が限られてしまう。これを打開するような設定はないかと悩んでいたんですが、ある日「休職中」にすれば、そのような組織の縛りなしに、動き回れることに気がついたのです。
矢作俊彦さんの小説に、「二村永爾シリーズ」というものがあります。二村刑事の場合、非番の日に捜査をします。このシリーズは、警察官の話ではありますが、一方で、「プライベート・アイ(私立探偵)」小説としても、とても面白く読めます。ならば、私は「休職中」という立場にして、「プライベート・アイ」小説に挑んでみようと思いました。「休職中」ですから、私立探偵同様、拳銃も警察手帳も持つことができません。捜査権も逮捕権もないけど、警察官ですから、人脈はあります。仙道には自分の刑事の経験と、その人脈をフルにつかって、北海道のさまざまな街に登場してもらおうと思いました。
──休職中という立場は、書く上でも大きな制約を与えますね。どの点にご苦労なさいましたか。
佐々木 どこまで事件の解決に寄与できるか、ということですね。何しろ、捜査権がないんですから。試行錯誤しながら書き進める中で、この主人公にできることは、初動捜査の段階で、捜査の方向がずれていることを示唆する、あるいは、新しい方向を教える、そのくらいのことだと気付きました。事件が起こった直後、現場が混乱しているときに、別の視点からほんの少しヒントを出して、初動の混乱が終わり、みなが冷静になったあたりで、去っていく。この設定、悪くなかったな、と思っています。

──「オール讀物」二〇〇九年六月号に掲載されている元道警釧路方面本部長の原田宏二さんとの対談で「いま警察小説を書くとしたら、警察官個人と警察組織の対立。ここに最大のドラマがある」と佐々木さんはおっしゃっています。『笑う警官』の佐伯シリーズなどはそのような図式に当てはまりますが、本作はそのような視点とは全く異なるところから生まれているんですね。
佐々木 私の中の位置づけとしては、『笑う警官』の佐伯シリーズは地方公務員小説、『制服捜査』の川久保篤シリーズは保安官小説、そして『廃墟に乞う』の仙道はプライベート・アイ小説です。本作では、事件の解決が主人公である仙道を幸福にしません。真相を暴(あば)くことで主人公は傷つき、打ちのめされます。一九九〇年代になって、アメリカの私立探偵小説も、そのような傾向になってきました。事件が解決して、ああよかったねと幸せになる小説が少なくなりました。『廃墟に乞う』はその流れにあると思っています。私立探偵を出すことが難しい日本のミステリー界で、私なりにこの分野の小説を書くことができました。ほら、こんな手があったでしょ、という気持ちです。
──仙道は、ある事件がきっかけで心に傷を負い、道警本部人事課から療養するようにいわれています。警察官のPTSDという設定は、佐々木さんの小説に度々出てきますね。
佐々木 実際に捜査に携わる人たちは、本当に大変だと思っています。犯人が自供したから、自宅で美味(おい)しく晩酌ができるなんて単純な話ではない。事件に深く、真剣に関われば、加害者や被害者が負った傷と同じだけのものを捜査員も負うことになると思います。だから、PTSDという設定が出てくるのでしょうね。
──警察官を単なるヒーローとして描くのではなく、一人の人間として見つめているところが、多くの読者から支持を受けているところなんだと改めて思いました。 さて、本作は六篇からなる連作短篇集です。いずれも北海道が舞台ですが、全て異なる街で、その土地特有の問題が事件につながっています。それぞれの短篇についてお聞きします。まず、「オージー好みの村」です。大勢のオーストラリア人が住んでいるニセコを舞台にした小説ですが、第一話をニセコにしたのは、何か理由はあるのですか。
佐々木 編集者と打合せをしていた場所が、ニセコだったんですね(笑)。小説でも書きましたが、本当にオーストラリア人は増えているんです。一昨年、打合せをしていた頃は、歩いている人たちの九割が白人。オージーが行ける店が多くなって、ウェイトレスも多少の英語を使えないと仕事にならない。札幌の求人誌には、「英語を使えるお仕事」として、ニセコ特集をよく組んでました。私がいたニセコの家のお隣も向かいもオージーで、一緒にお酒を飲むようなお付き合いをするようになりました。定住している人も多くなって、小学校の生徒の半分がオージーなんですよ。観光客が来るから、その人たち向けの商売をするために定住しているんですね。
──なぜ、そんなに多くのオージーが来るのでしょうか。
佐々木 オージーにしてみると、時差がない、雪はいいのに寒くない、というのが魅力なんですね。ニュージーランドの高山でも雪は降るけど、とても寒いそうです。ニセコは暖かいのに、毎日雪が降ってパウダー・スノーを滑ることができます。
──オージー資本の開発がなされる一方で、それを面白く思わない現地の不動産業者との確執がこの小説で描かれてますが、このような事例は実際にあったのでしょうか。
佐々木 確執はあると思いますが、実際に起きたことを小説にしているわけではありません。いろいろな要素を織り込んで、物語にしていますから。
──表題作の「廃墟に乞う」は、夕張を彷彿(ほうふつ)とさせる街が舞台です。極貧の中で育った加害者ですが、その母親は売春をしていたという背景があります。実に目を引くタイトルだと思いますが、どのような思いが込められているのでしょうか。
佐々木 タイトルは早くから思いついたんですね。何となく、スッと降りて来たんです。このシリーズの中で、夕張の風景は書いておきたいと思っていました。見捨てられた炭住街があり、ダムがあり、発電所も取り壊されようとしている街です。この風景と、釧路で実際に起きた事件が混ざり合ってこのような小説になりました。実際の事件の犯人も本当に貧しい環境で育ってきました。永山則夫を思わせる極貧ぶりです。その母親が、石炭拾いをしていたと聞いて、物語が固まりました。ラストシーンも書くときに決まってました。仙道にとって、試練ともいえる厳しいラストシーンですね。
──どのようなラストになるかは、是非小説を読んでいただきたいと思います。「兄の想い」は北海道の漁村が舞台。漁師町だけが持つ独特の雰囲気が伝わってきます。潮風に晒(さら)され続けたような、ザラリとした感触が残る小説です。
佐々木 漁師町は、酪農の町と違って、不漁・豊漁で町の雰囲気が変わってしまう。豊漁のときは消費生活も派手になるし、不漁が続くと、みんなしゅんとしてしまう。酪農の町は一年間の収入が計算できるので、消費生活が非常に堅実なんですが、漁師町というのは違うんですね。遊ぶときは無茶苦茶派手に遊ぶ。そういう町にはドラマがありますからね。また、漁師たちが営んでいる組合、仕事のシステムというのも、あまり読んだことがなかった。ならば、きちんと書いてみようと思ったんです。
──この短篇のラストも、とても物悲しいものです。先ほどおっしゃったように、事件の背後を暴くことが、果たしてみなの幸せになるのかと仙道は悩みます。それでも仙道は、警官として自分がするべきことをして町から立ち去っていきます。次の「消えた娘」は札幌という都市が舞台です。風俗嬢を監禁し、死体を遺棄した犯人。本作は、この加害者と被害者、二人の生い立ちが丁寧に描かれています。
佐々木 被害者の父親みたいな人はどこにでもいると思います。娘の教育に熱心になればなるほど、娘が離れていってしまう家庭ですね。また、この犯罪は、札幌という都市ならではのものだと思います。監禁する倉庫のような建物も、札幌ならば安い値段で借りることができる。だから、犯人のような若い男でもこのような犯罪に手を染めることができるんです。
北海道という土地のさまざまな顔
──「博労沢の殺人」は、独裁者ともいえるワンマンな父親とその家族の悲劇です。厩舎の経営という北海道を代表する産業を扱いながらも、家族の相克というものが大きなテーマになっていると思いました。
佐々木 これも実際に起きた事件からヒントをもらっています。まだ未解決の事件です。この短篇では、男家族の物語を書きたいと思いました。それで思いついたのが、『カラマーゾフの兄弟』なんです。粗暴な父親、父親とよく似た長男、斜に構えている次男、そして父親殺しの犯人像……。タイトルも音感を意識してつけました。
──最終話は「復帰する朝」です。復帰目前の仙道の前に、女性の強敵があらわれますね。
佐々木 怖い話を書きたかったんです。人間の内面の怖さですね。そのために、中産階級以上の家庭を出しました。
──なぜ、中産階級と怖さが結びつくんですか?
佐々木 落差ですね。人間というのは、生活に苦労がなければ、健(すこ)やかに育つという単純なものではない。その逆の例は、世の中には多々あるわけです。一見健やかであればあるほど、ギャップが生まれたときの怖さがあるんだと思います。また、舞台にした帯広という街は、まださほど疲弊が目立たない地方都市で、小説のような中産階級がいても不自然じゃないんです。
この小説で、北海道という土地の多様さを分かってもらえたら嬉しいですね。街ごとにそれぞれ異なる性格があって、そこに起こる犯罪も多様なんです。その辺は、楽しんで頂けるところだと思っています。そして、捜査員の「心の傷」というか、事件に携わることは、たとえ刑事であっても平気なことではないという点。犯罪は、被害者だけではなく、捜査員の心まで傷つけてしまうものなのです。