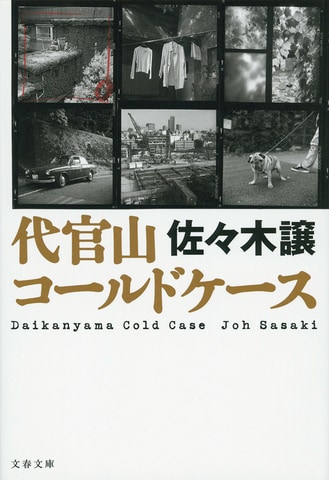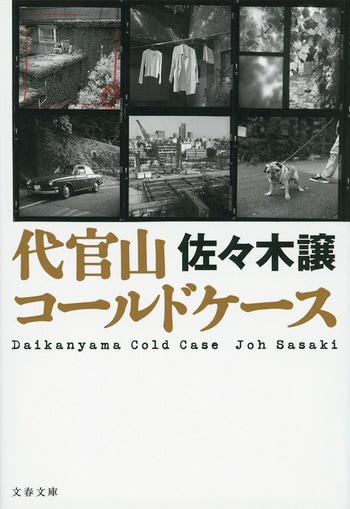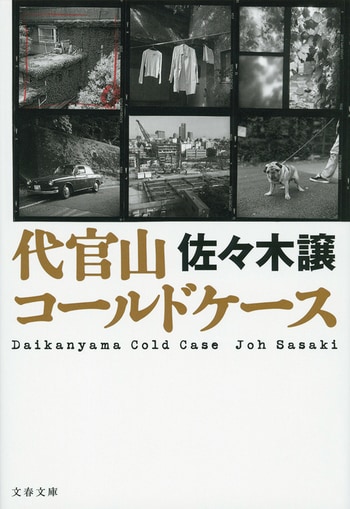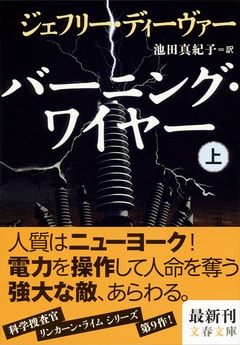記憶の中には、もはや時や場所も判然としないほどにぼやけてしまった景色がある。
ある日の午後、だらだらと続く坂を歩いているときに見た、眼下の屋根の連なり。
街が夕闇に沈む頃、自転車にまたがってぼんやり開くのを待っていた私鉄の踏み切り。
繁華街から一歩入ったところに突然現われた、静かな住宅地の家並み。
佐々木譲『代官山コールドケース』のページを繰るうちに、そんな風景が幻の如く眼前に甦ってきた。作家の引き起こした魔法であろう。
本作は「週刊文春」二〇一二年五月三・十日号から二〇一三年四月四日号に連載され、二〇一三年八月三十日に文藝春秋より単行本が刊行された。今回が初の文庫化である。
主役を務めるのは警視庁捜査一課特別捜査対策室の水戸部裕警部補だ。特命捜査対策室は捜査一課内に実在する、未解決事件の継続捜査を受け持つ部署である。彼の初登場作は二〇一〇年から翌年にわたって佐々木が「オール讀物」に連載した長篇『地層捜査』(二〇一二年刊。文藝春秋→現・文春文庫)だ。同作の水戸部は二ヶ月の謹慎明けから復帰したばかりだった。不祥事があったわけではなく、事情もわからずに現場を混乱させるキャリア警官に暴言を吐いたため、冷却期間をとらされたのだ。復帰後最初に担当したのが、一九九五年十月に新宿区荒木町で起きた殺人事件の追跡調査だった。退職刑事で現在は警察署の相談員として働いている加納良一という人物と組み、水戸部は十五年という時間の地層を掘り返していったのである。その事件から二年後の二〇一二年に『代官山コールドケース』の物語は始まる。今回彼に任せられたのは、荒木町の事件とは比べものにならないほどに厄介な代物だった。
事件が起きたのは一九九五年五月のことである。渋谷区代官山のアパートで若い女性が扼殺された。一人の男性が被疑者として特定されたが、逮捕を目前に控えたところで死亡する。被疑者死亡、不起訴処分ということで捜査は終了したのである。それから十七年が経過したあとで、警視庁にとっては青天の霹靂(へきれき)と言うべき事態が出来(しゅったい)した。事の発端は、川崎市中原区で強姦殺人事件が発生したことである。捜査を担当した神奈川県警が遺体から採集した精液のDNA鑑定結果を科学警察研究所に照会したところ、一九九五年の「代官山女店員殺害事件」の現場遺留資料と一致することが判明したのだ。実は代官山の現場からは、死亡した人物を含めて三種類のDNAが検出されていた。死亡した被疑者以外の二人については特定が行われずじまいになっていたのである。もしその人物が川崎の事件を引き起こしたのだとしたら、警視庁の重大な失態である。杜撰(ずさん)な捜査で真犯人を見落としていたことになるからだ。しかも死亡した被疑者の遺族からは、過酷な取調べが原因となった自殺であるとして国家賠償請求訴訟まで起こされていた。
捜査方針に誤りがあったことが明るみに出れば、警視庁の威信は地に墜(お)ちる。水戸部はそれを未然に防ぐために起用されたのだ。当然、神奈川県警との連係はありえない。また無用の軋轢(あつれき)を防ぐため、渋谷署員に接触することも許されない。公式には誰にも助力を求められない状態で、誰よりも速く真相に達しなければならないのである。組織から離れた遊軍の立場を取り、水戸部は捜査を開始する。
少し回り道になるが佐々木の過去作について触れておきたい。作者には膨大な警察小説の著書があり、その出発点は少年犯罪を扱った二〇〇三年の『ユニット』(文藝春秋→現・文春文庫)である。以降の作品にはシリーズ化されたものも多い。もっとも作品数が多いのが二〇〇四年の『うたう警官』(角川春樹事務所→現・ハルキ文庫。文庫化に際し『笑う警官』に改題)に始まる通称〈道警〉シリーズだ。第一作の『うたう警官』は、主人公である佐伯宏一刑事が、ある理由から自身の所属組織であるはずの北海道警察と対立せざるをえなくなり、孤独な闘争を強いられるという緊張感溢れる内容だった。
警察官が個人として組織と対立するという構造の原点にはスウェーデン作家マイ・シューヴァル&ペール・ヴァールーの〈マルティン・ベック〉シリーズがある(第一作の改題『笑う警官』は、同シリーズの第四長篇の題名を借りたものである)。このシリーズは、スウェーデンの首都ストックホルムの警察官マルティン・ベックを主人公とし、彼の眼から見た祖国の十年間の移り変わりを長篇十作で描くという壮大な構想のものだった。背景には社会主義的理念によって福祉国家制度を樹立したスウェーデンが、経済・国際的諸因からそれを維持できなくなり、ついには国策転換を余儀なくされたという一九六〇年代後半から七〇年代にかけての国家情勢がある。その中でベックの所属する警察組織も大きく揺れ動き、同僚たちの中には絶望のために職を辞する者も現われるのだ。
警察組織を正義の機関として盲信するのではなく、権謀術数が複雑に絡みあった伏魔殿として描くという手法は、日本の警察小説の中にも存在し、一つの作品群を形成している。たとえば逢坂剛は、第一長篇『裏切りの日日』(一九八一年。講談社→現・集英社文庫)に始まる〈公安警察〉シリーズで、法の番人である警察官が時の権力者と結びついたときの恐怖をくり返し描いている。警察官を組織人という観点で捉えなおして警察小説に新風を吹き込んだ横山秀夫〈D県警〉シリーズ(一九九八年。『陰の季節』他。文藝春秋→現・文春文庫)なども同じ系譜に属するものといえるだろう。
『うたう警官』は、そうした作品の歴史に新たな一ページを付け加えた。佐伯が結成した少人数のチームが道警という巨大な組織に闘いを挑むという図式は冒険小説の定型を応用したものであり、そのことによって「個人対組織」という構造はより明確化された(これは余談になるが、同作から私が連想したのは、ニューヨーク市警の現職警官であるウィリアム・J・コーニッツが自身の見聞した権力闘争をモデルにして書いた一九八四年に発表した『燃える警官』だった。興味がある方はぜひご一読を。文春文庫)。こうした組織内のダイナミズムを描く作風は第三作の『警官の紋章』(二〇〇八年。角川春樹事務所→現・ハルキ文庫)までが特に顕著であったが、その後も作品で扱う領域を広げながらシリーズは継続されている。
佐々木は一九七〇年代末から書き続けている息の長い作家であり、二〇〇〇年代に警察小説作家としての地位を確立する以前の作品は冒険小説と呼ばれるものが多かった。もちろん『うたう警官』で軌道修正が行われたわけではなく、冒険小説の原点にある独立不羈(ふき)の姿勢、個人が自身の信念のために存在を賭けて闘うという人間賛歌の精神は、警察小説の作品群の中にも形を変えて引き継がれている。
二〇〇六年に発表された連作集『制服捜査』(新潮社→現・新潮文庫)の主人公・川久保篤は、道警内で不祥事が暴かれたために人事異動が活発化し、弾き飛ばされるような形で十勝平野の端にある僻村(へきそん)の駐在所に赴任することになる。それまでは道央で犯罪検挙に当たっていた男からすれば新しい勤務地は平和そのもののはずであった。だが、農村には農村ならではの事情による、別種の事件が待ち構えていたのである。『制服捜査』が描くのは、閉鎖的な土壌ならではの社会問題で、これに立場上捜査権を制限される主人公が立ち向かうという構造だ。横溝正史以来、日本のミステリー作家が繰り返し取り組んできた課題だが、別の見方をすることもできる。誰一人味方がいない鄙(ひな)の地に、自らの腕のみを頼りに捜査官が乗り込んでいく物語という図式は、ダシール・ハメットが私立探偵〈コンティネンタル・オプ〉を悪の支配する地方都市へと潜入させた「新任保安官」(一九二五年。『フェアウェルの殺人』他所収。創元推理文庫)の物語の変奏版なのだ。さらに遡(さかのぼ)れば、胸につけたバッジによって悪漢たちのコミュニティに割って入り、正義を遂行する西部小説の保安官たちの肖像が川久保の背後に重なって見える。『五稜郭残党伝』(一九九一年。集英社→現・集英社文庫)他の作品で幕末から明治にかけての北海道を描いた佐々木は、西部小説に描かれた開拓精神を日本小説に移植するという試みを行った作家であり、この連想は決して無茶なものではないはずだ。
この『制服捜査』の延長線上には第百四十二回直木賞受賞作にもなった連作集『廃墟に乞う』(二〇〇九年。文藝春秋→現・文春文庫)がある。主人公の仙道孝司はとある理由から精神を病んで休職中の警察官であり(この設定はタッカー・コウの生んだミッチ・トビンや、ローレンス・ブロックの創造したマット・スカダーなどの元警官探偵を連想させる)、彼が非公式な立場で刑事事件を解決に導くという私立探偵小説的なプロットを採用した作品だ。私立探偵小説には個人が自身の限界を知りながら社会問題とその歪みが生み出した悪に向き合うという側面があり、佐々木が個としてのヒーロー像を警察小説よりもさらに突き詰めた作品が同書なのである。
同時に佐々木には、社会の動態を年代記形式で小説に書き留めるという作品群が存在する。ここでは詳説する余裕がないが、第二次世界大戦を描いた諸作、前述の『五稜郭残党伝』他の蝦夷地(えぞち)を舞台にした作品群などは、歴史の流れに抗(あらが)う個を描くというロマンティシズムと同時に、経過していく時間そのものを主題にした小説として読むこともできるだろう。こうした系譜に属するのが『警官の血』(二〇〇七年。新潮社→現・新潮文庫)だ。清二・民雄・和也と三代にわたって警察に奉職した安城家の男たちは、それぞれ駐在・公安・刑事と立場は異なるもののその職務を全(まっと)うする。こうした年代記形式の警察小説にはスチュアート・ウッズ『警察署長』(一九八一年。現・ハヤカワ文庫NV)という前例があるが、本書には戦後昭和から平成に至る現代史の流れを背景として描きつつ、その中心で一つの謎解きを展開していくという構造があり、先行作とは別種の柄(がら)の大きさを感じさせる。主人公の動向を描いていくことによって社会の各層をスケッチする全体小説を実現することもその企図にはあったはずだ。
創作者としての佐々木の土台には、ミステリーというジャンルに限定されない、豊穣な作品群が存在する。先に挙げた〈マルティン・ベック〉シリーズは、ミステリーであると同時に、ストックホルムの十年間を描く都市小説でもあった。ジェイムズ・ミッチェナー『センテニアル 遙かなる西部』(一九七四年。河出書房新社)のような、都市を一個の生命体として描くような小説が一つの理想形として作者の中にあるのではないだろうか。おそらく『地層捜査』『代官山コールドケース』と続く水戸部裕シリーズは、巨大な都市の一隅を〈街〉として切り取り、事件発生から解決までの一続きの時間の中でその変化を記述するという性格がある。都市小説の書き手としての佐々木譲の特質が如実に現われた作品なのだ。
文芸評論家の川本三郎氏が文庫版『地層捜査』に、同作を四谷荒木町の地誌を描いたものとして読み解く解説を寄稿しておられるので、どうかそちらにもお目通し願いたい。四谷荒木町を舞台として『地層捜査』で描かれたのは、現在では消失寸前の花街文化の残滓である。一九八〇年代の地上げによって一帯は歯抜けにされ、住民たちも一部は離散した。つまりバブルによって終止符を打たれた昭和の記憶を小説の形で再生したのが『地層捜査』という作品だったといえる。
それに対して『代官山コールドケース』の主舞台となる渋谷区代官山は、昭和から平成への移行期に大きく性格を変えた地域である。作中にも出てくる同潤会アパートなどの日本のマンション建築の草分けとなった建物が存在し、一九八〇年代までは完全な住宅街だった。東京と神奈川の繁華街を結ぶ東急東横線は、渋谷から一つ目である代官山で編成の増加に対応できず、一九八〇年代中盤までは一部のドアを閉じたままにしていた。代官山駅はそんなローカル駅であり、駅周辺でも昭和の空気を残す店屋がそのまま営業を続けていたのである。一九九六年に同潤会アパートが解体されたことでそうした旧時代は終焉(しゅうえん)し、再開発期を迎える。一九八〇年代後半から九〇年代にかけての代官山は、何か新しいことが起きそうだという期待感に溢れた街であり、それゆえに時代の先端を行こうとする若者を引き寄せてもいた。佐々木は一九九五年に起きた事件を描くことにより、その空気感を本書の中に封じ込めているのである。『地層捜査』が「失われた昭和」を描く作品だとすれば、本書は「昭和から平成への移ろい」を描いたものなのである。直接その時代を描いたわけではないのに、二〇一二年という〈現在〉から当時を振り返るひとびとの証言だけで、その情景が鮮やかに甦ってくる。
この連作で描かれる過去の事件がいずれも一九九五年に設定されているのは、二〇一〇年四月に刑事訴訟法が改正され、殺人などの重大犯罪については時効が廃止されたためだ。一九九五年四月二十七日以降に発生した事件にそれが適用されるため、日付が問題となってくる。この日付が重要で、本書では同年三月二十日に起きたオウム真理教による地下鉄サリン事件が影響してくる。その捜査に人員が割かれたために手が回らず、代官山の事件は不満足な結果に終わったという設定なのだ。昭和から平成への転換期の節目を考えるとき必ず浮上してくる事件を背景に重ね合わせたのは当然のこととして、本書にはもうひとつ重要な出来事が描き込まれている。その出来事を借景として眺めることにより、昭和から平成への転換期の事件として近過去に見えていたものが、一気に現代のこととして切迫した印象に変わるのである。長い時間経過を描くミステリーとしては理想形というべき叙述の仕方と言うしかない。
叙述といえば、『地層捜査』からの進化についても触れておきたい。基本的に水戸部の一視点で通されていた前作に対して、本作では複数視点が用いられている。水戸部以外にもう一人捜査の経過を眺める役割の人物が出てくるのだが、それは代官山女店員殺害事件という過去の事件(コールドケース)以外にもう一つ、現在進行中のホットな事件の捜査が描かれるためである。二つの捜査模様が交互に描かれるカットバックの手法が実に効果的に用いられている。ここで意識されているのはモンタージュの効果だろう。水戸部が見ていたものが読者の意識から消えないうちに場面は移り変わり、もう一人の視点人物が別の角度からそれに関する事物や光景を眺めるというように、カットの切り替えに意味が持たされている。単に作者の都合で場面転換が行われるのではなく、切り替えによって読者の脳裏に確固としたイメージが形成されるように意図されているのだ。その二つを結ぶブリッジとして、前作にも登場した警視庁科学捜査研究所の中島翔太の視点が採用されている。『地層捜査』では単なる変人としてしか描かれなかった中島の人間らしい一面が垣間見えるのも本作の嬉しいところだ。
手がかりの開示の仕方、脇役たちの多面的な描き方など書きたいことはまだ無数にあるのだが、残念ながら字数が尽きた。最後に強調しておきたいのが、水戸部と新相棒である朝香千津子の関係である。朝香の階級は巡査部長で、捜査一課には配属されたばかり、性犯罪を担当することになっていたという。彼女はそうした事件の犠牲者になった人が身内におり、性犯罪者に対しては極めて強い憎悪の念を抱いている。
男女のペアが協力して捜査に臨むというと、凡百の作家ならそこに恋愛感情を持ち込みたがるが、この二人にはそういうことは起きない。水戸部は妻帯者なのでそういうことが起きても困るのだが、とにかく起きない。二人は職務のために協力し、互いの立場を尊重し合うだけで、互いの人生には一切踏み込まない。朝香には小さい子供がいて保育園に送り迎えをする必要があるという説明があるのだが、水戸部がそのことについて干渉することもまったくない。この距離感が貴重なのだ。中には淡白だと感じる人もいるかもしれないが、性差などの立場の違いを一切意識せずに済む話運びは、現代の読者にはむしろおおいに歓迎されるはずだ。夾雑物など一切なく、ひたすら物語と、それが生み出す豊かな情景に集中できる。『代官山コールドケース』はそんな作品なのである。