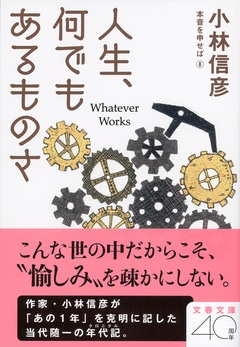この批評に初めて触れたときの衝撃は、はっきりと覚えている。当時の私は現代詩を書きつづけようとして壁にぶつかり、自身の芸能好きや娯楽好きの体質とどう折り合いをつけてよいのかわからない状態だった。打ち明けていうなら、好きなものについては書くことができず、いくらか書けるものがあっても興に乗ることができないという、自分をもてあましたありさまだったのだ。だから、小林さんの指摘は灯台の光だった。そうか、そっちへ向かえば、座礁せずにすむのか。
私的な事情を並べ立ててしまって申し訳ない。すでにお気づきと思うが、『森繁さんの長い影』は『森繁久弥の影』の延長線上にある。つまり小林信彦は、『森繁久弥の影』という「原型」を身体のなかに飼いつづけ、それをひそかに暖めていたのだろう。長い時間をはさんでも、つながるものは無理なくつながる。
小林信彦は『森繁久弥の影』のなかで、フランキー堺、植木等、渥美清といった喜劇人(三人とも巨大な喜劇人だ)の名を挙げ、彼らに差した森繁久彌の濃い影を指し示している。同時に小林信彦は、三木のり平や有島一郎や益田喜頓の名を持ち出し、彼らがどれほど微妙に森繁久彌の影響をかわしていったかを指摘する。一九七〇年代当時、革命的に新鮮だったその視点は、現在も生きている。いや、当時からはっきりしていた森繁久彌の影は、それから四十年ほど経ったいまも、依然として圧倒的な力をふるっているのだ。一例がつぎの文にある。
《ぼくはこの役のキャスティングを考えてみたのだが、一九五〇年代だったら、森繁さんがぴったりである。どう演じても、胡散くさくなる。数年後だったら、ドラマーから転じたころのフランキー堺が向いている。もう少し後だと、植木等がいいかも知れない。しかし、現代では、鶴瓶がぴったりだし、他の役者は考えられない。(中略)テレビでちらちらと見かける風貌からして、人気はあるのだろうが、この人は善人ではない、と思っている。その暗さが、「ディア・ドクター」では、アップの眼鏡の奥の細い目に生かされている》(『心を惹かれる映画「ディア・ドクター」』)
いうまでもないが、鶴瓶とは笑福亭鶴瓶のことであり、彼が演じたのは映画『ディア・ドクター』(二〇〇九)の主人公、にせ医者の伊野治である。これも鋭い指摘だ。なるほど、森繁久彌の『ディア・ドクター』か。これはぜひとも見てみたかった。
森繁さんの長い影は、まだまだ意外なところに差している。たとえば、『欽ちゃん!』と題されたコラムの一節。
《「最近になって二郎さんが役者だということがわかりましたよ。あの人はコメディアンじゃなくて役者なんです」(改行)欽ちゃんは笑った。(改行)「それが良かったんだ」とぼく。「関西の有識者が、成功した漫才は、漫才人間と役者人間の組み合わせだというでしょう(以下略)組み合わせの良さという原則は同じなのかも知れない」》
なんと、坂上二郎と森繁久彌の連結! この抜き打ちも、由って来たるところは森繁さんの長い影ではないか。逆にいうなら、小林信彦は十代の若さで森繁久彌という端倪すべからざる怪物に遭遇し、それと格闘しつつ、観察の基礎、発見の基礎、思考の基礎を築いてきた。原体験などという粗雑な言葉は使いたくないが、この基礎工事があればこそ、そして、その礎石に血を通わせつづける長い戦いがあればこそ、小林さん生得の鋭い反射神経も発達していったのではないだろうか。
ただ、忘れないうちに付け加えておきたいことがある。
すでにほかの場所でも述べたことだが、小林信彦は、鋭敏で、眼利きで、物知りで、冗談好きで、肥沃な文学者だ。だがもうひとつ、小林さんの並外れた折り目正しさ(形容矛盾だろうか)と、驚くほど謙虚な「引きの姿勢」を私は見逃したくないと思う。
森繁久彌は、この本のもととなったコラムが連載されているさなか(二〇〇九年十一月十日)に九十六歳で亡くなった。だが、この本のなかで小林さんが別れを惜しんでいるのは、ひとり森繁久彌のみではない。同年六月に亡くなった翻訳家の永井淳、やはり六月に逝去した映画監督の長谷部安春、七月に他界した歌手の川村カオリ、さらには、二〇〇二年に世を去った脚本家の笠原和夫。
こうした不在の人々に思いを馳せるとき、あるいは、彼らとともに過ごした日々を振り返るときの小林さんの筆は、痛いほど繊細で、みごとなまでに自分を消している。それも、ポーズとしての抑制などではなく、本心からの哀悼と敬意と追慕。
私はその景色に胸を打たれた。小林信彦のことを「才知の人」などと決めつけて満足しているお子供衆は、この美点に眼をみはっていただきたい。こんなことをあらためていうのも野暮な話だが、小林さんは「実(じつ)」のある人だ。実があるとは、本気で他者に思いを寄せる資質に恵まれているということだ。豊かな才知と豊かな情感は、そもそも矛盾するものではない。
だからこそ小林信彦は、森繁久彌の技芸と体質をあれほど的確に射抜くことができた。森繁に対する興味は、複数の共感や疑問を伴いつつ六十年以上にわたって持続し、さらに深い理解へと進化していったにちがいない。
政権交代に対する期待と失望、新型インフルエンザに対する恐れと怒り、クリント・イーストウッドの新作映画、淡島千景や中原早苗をめぐる書物……クロニクルの体裁を取るだけあって、この本にはさまざまな話題が盛り込まれているが、読み終えて身体に残るのは、実があって大声を出さない小林信彦の語り口だ。名著『日本の喜劇人』と合わせてお読みになれば、「小林さんの長い影」もおのずと見えてくるのではないか。