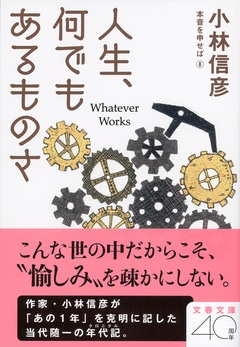息の長い仕事をする人には、どんな共通点があるのだろうか。継続は力なり、などと世間では簡単にいうが、継続するにはなにが必要かという難問については、だれもあまり語ろうとしない。たまに見かけても、日々精進あるのみとか、千里の道も一歩からとか、自己啓発本にでも出てきそうな、毒にも薬にもならぬ同義反復にとどまっている。
現役の映画監督で息の長い仕事をしている人となると、クリント・イーストウッド、ウディ・アレン、ロマン・ポランスキーの名前が反射的に浮かぶ。イーストウッドと同い年のジャン=リュック・ゴダールの名も頭の隅をかすめるが、この人は仕事の流儀がちがうのでここには含めない。
いま挙げた三人はみな八十歳以上で、キャリアも約半世紀におよぶ。イーストウッドだけは一九七〇年代に入ってから監督業に進出したが、俳優としてのキャリアは遠く五〇年代にまでさかのぼる。紆余曲折を経て敷居を超えたときも、清水の舞台から飛び降りたような感じはなかった。むしろ「ここらでちょっと」という感じで、監督第一作『恐怖のメロディ』(一九七一)などは、初陣とは思えぬ落ち着いた気配を漂わせていた。
それはともかく。
三人に共通するのは、「無理をしなくてもつづけられるやり方」を、着慣れた服のように身につけていることではないか。もちろん、そのやり方はひとりひとりが異なる。それぞれが「これならつづけられる」というやり方を自家薬籠中の物にしていて、口をとがらせたり、背伸びをしたり、見栄を張ったりする様子がついぞ見受けられない。
これは、いわゆる自然体とは少し異なる。成り行きまかせとか、天衣無縫とかいった比喩も適切とはいえない。むしろ感じられるのは基礎工事の確かさと、その先にある平叙体の堅牢さだ。彼らは学習や鍛錬になみなみならぬ時間をかけ、「ここぞ」という急所で思い切った勝負に出る。それも一度だけにはとどまらない。
イーストウッドの場合は、『許されざる者』(一九九二)と『ミリオンダラー・ベイビー』(二〇〇四)がギアチェンジの時期に当たるかもしれない。彼はここで踏ん張った。持ち前の資質をもう一段深く掘り下げ、それに応じた行動の形態や色彩を検証している。撮影や照明や編集の仕方がここでいったんリヴァイズされ、語りの基調となる「ペース」も長期使用に耐えうるものが選ばれているのだ。つまり、イーストウッドは目先の勝負にこだわらなかった。服でいうなら、トレンドに気を取られず、十年二十年経っても着飽きないような生地や色味を優先させている。
小林信彦さんのエッセイ集『映画の話が多くなって』を繰っていると、イーストウッドやアレン、あるいはポランスキーといった人たちの仕事の流儀を連想してしまう。紙幅の関係で話を端折ってしまったが、いま述べたギアチェンジは、アレンやポランスキーも通過している。そしてここが重要なポイントなのだが、彼らは、安定したペースを獲得したあとも、「流す」という手抜きには与(くみ)しない。まあ、もともと激しい人たちなのだから、当然といえば当然だろう。加齢によって体力が落ち、とんがっていた部分がやや丸くなることはあっても、生来の鋭さや強さが矯(た)められることはない。
小林さんの映画評にも、同じような事情がうかがわれる。ご承知のとおり、小林さんが一九七〇年代に書いていた映画評論は、衝撃的なほど鮮烈で、気概と戦闘心にあふれるものだった。といっても、イデオロギーがどうとか、ロジックがこうとかいった無粋な話ではない。
当時二十代だった私の眼には、小林さんの姿が「単騎荒野を行くガンマン」のように映った。だってそうでしょう。こちらが、ゴダールだ、ヴィスコンティだ、ペキンパーだなどと野暮ったくのぼせ上がっていた時代に、小林さんは早くも、プレストン・スタージェスやエドワード・エヴァレット・ホートン、果てはノーマン・ウィズダムといった玄人の仕事に親しんでいたのだから。
私が彼ら玄人の存在に注目したのは、八〇年代の後半になってからだった。アメリカやイギリスでビデオを買い漁っているうち、おや、こんなに凄い鉱脈が、と気づいたのだ。ただ、もしかするとこれも、昔読んだ小林さんの『われわれはなぜ映画館にいるのか』が無意識の底に刷り込まれていたためかもしれない。正直に告白すると、七〇年代中盤にあの本を初めて読んだとき、私はその価値を十分に理解していなかった。言及された異才や奇才の名前も、私の頭のなかを素通りしただけのような気がする。俺の眼は節穴だったのか、と私は自分に毒づいた。小林さんの言葉をしっかり受け止めていれば、もっと早くから彼らの仕事に眼を向けることもできたはずなのだ。もっとも、七〇年代の後半だと、ビデオソフトはあまり充実していなかったのだが。
もしあなたが、小林信彦さんの映画評論やエッセイを読みはじめて日の浅い方だったら、私がいま申し上げたことを頭の片隅に留めておいていただきたい。
なるほど、『映画の話が多くなって』はすらすらと読める本だ。八十歳を過ぎた小林さんが、ときには映画館で、ときにはDVDで見た映画を紹介し、その見どころにさらりと触れた本、という風に受け止める人がいても別段おかしくはない。
だが、「さらり」の陰には「ぐさり」が潜んでいる。年季の入った見巧者の鋭い眼はもちろんのこと、幼いころから娯楽の水をたっぷり浴びてきた遊び人ならではの深い洞察を読み流してしまうのは、あまりにももったいない。いくつか例を挙げよう。
《マーティン・スコセッシは……(中略)……「ディパーテッド」でアカデミーの監督賞を得たあたりから、おかしくなった。今年も3D映画で作品賞候補になっているが、3D映画が「夢だった」とは程度が低い。リトル・イタリー物に戻るしかないだろう》
という痛烈な批判。あるいは、二〇一二年に亡くなった淡島千景の魅力を、
《獅子文六が〈キャサリン・ヘップバーンとクローデット・コルベールの間に君の道がある〉と色紙に書いたが、淡島みずから〈日本的でない顔〉を意識していた》
と要約する読みの鋭さ。さらには、新藤兼人の本領が《すぐれた“脚本家”》であることを指摘し、マキノ正博の『鴛鴦(おしどり)歌合戦』に触れて、《要は歌入り喜劇であり、〈ちょっと面白い〉ぐらいなのである。(改行)ひとがミュージカルと軽く言うのがわからない。これはまず〈センス〉の問題であり、役者が歌ったり踊ったりするからミュージカルというわけではない》と苦言を呈するくだり。
どれも的を射ている。昨日今日の映画ファンなら調子に乗って寝言を口走りそうなところで、玄人ならではの一撃を浴びせ、飄然と去っていく。こういう姿を見ると、小林さんには「単騎のガンマン」的な体質がいまなお残っているという気がする。いま紹介した批評以外にも、
《人ぎらいの渥美清が好きなのは、植木等、三木のり平、藤山寛美の三人だったのである》
とか、
《日活には他にも良い監督がいたということだ。(改行)たとえば、「拳銃(コルト)は俺のパスポート」の野村孝や「縄張(シマ)はもらった」の長谷部安春のような監督たちで、これらの作品・監督に目くばりをしておかないと、日活映画という不思議な“もの”は評価できない》
とか、
《校舎のあちこちでおこる出来事を、複数の生徒の視点から眺めた映画が〈桐島〉だろうが……(中略)……カットごとに少年少女たちの言葉や走る意味が変って見える。いわゆる学園物がタイクツになるのは、少年や少女の走る意味が一つだからで、この映画では、それらの行為が一つではない》
とか、思わずにやりとしたくなる言葉が随所にちりばめられている。一階級上の説得力、というべきだろうか。
《いわゆる典型的な美人じゃなくて、ブロンド(?)、そして鼻の先が反(そ)っているのが、もう全く、小生の好みです》
と書きつける稚気の楽しさ。雀百まで、という比喩が適切かどうかはわからないが、マリガン以外にも、『崖っぷちの男』のエリザベス・バンクスや、《柔道女子57kg級の松本薫》に眼をつけるあたり、「さすがは小林さん!」と冷やかし半分の拍手を送りたくなってくる。
こんな小林さんの鋭い味覚と健啖と思いの深さは、映画や書物の世界だけにとどまらない。先に挙げた淡島千景や新藤兼人だけではなく、二〇一二年には、吉本隆明、山田五十鈴、伊藤エミといった多くの人が世を去った。
小林さんは、この人たちを静かに追悼しつつ(吉本隆明氏との淡いがこまやかな交流は胸に沁みる)、少し前に世を去った石堂淑朗や安田南との思い出もぽつりぽつりと語る。露骨な感情表現を嫌う小林さんだが、《ぼくの人生は、いつも、どこかで、人と食い違う》と低くつぶやくときは、自身の心に掘られた深い井戸を覗き込んでいるように見える。読点の数も、普段以上に多い。
こうした印象深い揺らぎをところどころに挟みつつ、小林さんのクロニクルはいままでと同様、安定した走行で読者を独自の世界に運んでくれる。冒頭に私が掲げた理屈に立ち返るなら、それは「無理をしなくてもつづけられるやり方」を身につけた「息の長い仕事」にほかならないと思う。
そう、小林さんの眼前には、幼いころから「映画という大海」が広がっていた。海の水はほぼ無限だ。バケツで何杯汲み出そうと、水が涸れることは考えられない。この特権が存在するかぎり、小林さんのクロニクルが絶えることはないし、われわれ読者の楽しみも尽きることはない。映画に感謝し、映画の海から水を汲み出すことのできる小林さんに感謝しようではないか。