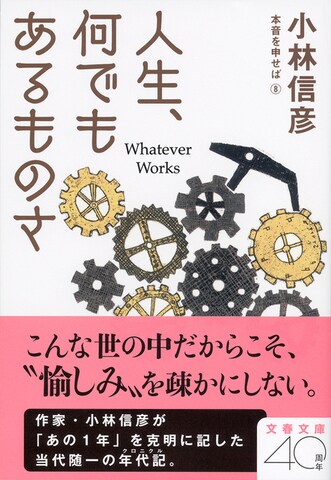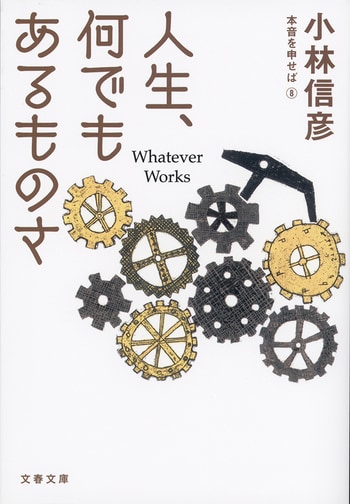二〇一一年は東日本大震災の起こった年だ。日ごろはへらへらと生きている私も、あのときは笑いを失ってしまった。顔のこわばりがしばらく取れず、外国で会った友人に心配をかけたくらいだ。そういえば、二〇〇一年九月十一日にアメリカで起こった大事件のあとも、同じ生理現象に見舞われた。自分が直接の被害に遭っていなくても、ひどい災害とは身体にじかに響くものだ。
小林信彦さんも、つぎのように書いている。
《ぼくはわりに外部の事件を忘れて、自分の仕事に集中できるほうなのだが、さすがに今度の東日本大震災は、そうはいかない。(中略)原稿も書きにくくなった。ある方面からたのまれた、野坂昭如さんについてのわずか三枚の原稿が、どうしても書けない。ダルいというか、目がケイレンするとか、そんなことである。おそらく、眠りが浅いのだろう》(『非常事態 2』)
いま挙げたのは震災直後の記述だが、およそ百日後の同年七月付けのコラムにもこんな一節がある。
《ぼくは戦後の総理大臣をずっと見てきたが、こういう〈人間性のこわれている〉総理を初めて見た。思い浮べるのは、最前線で兵士がバタバタ倒れているときに、酒と肉で談笑していた内地の指導者である。(中略)友人と話していて、必ず出るのは、テレビのニュースは、毎回、初めに福島の第一原発の現状を報告すべきだということ。(中略)そのせいか、ぼくは熱が出て、三日間、ベッドにいた。原発と〈人としての資質〉が欠落した総理のために、寝不足がつづいたからだ》(『「ゴーストライター」と「風の中の子供」』)
様子が眼に浮かぶようだ。寝込むというより寝付くとか床につくとかいう感じ。正直な人だから、もろにこたえたのだろう。それでも、小林信彦さんには映画という味方がある。逆にいうと、映画が小林さんを放っておかない。小林さんの身体も、映画の呼び声に応える。そしてこう書く。
《病院へ行った帰りに、久しく我慢していた映画の試写を観せてもらった》(同前)
映画とは、ロマン・ポランスキーの『ゴーストライター』(二〇一〇)のことだ。
ポランスキーは、小林さんより一歳だけ若い。生きてきた環境は異なるが、同時代の空気を吸っている。悠然とした語りを好むところ、閉所や密室に対して敏感なところ、性愛の嗜好がちょっと風変わりなように思えるところも、共通した資質といってよいか。
『ゴーストライター』は興味深いスリラーだった。舞台は、ニューイングランドの沖合に浮かぶマーサズヴィンヤード島(実際は北ドイツのジルト島で撮影された。淫行容疑者のポランスキーは、アメリカに入国すると逮捕されてしまうのだ)で、落ち着きはらっていながらゆるんだ箇所がなく、ヒッチコック風のサスペンスがときおり顔を覗かせる。アレクサンドル・デスプラの音楽も耳に残った。
夏の盛り、私はこの映画をめぐって小林さんとある雑誌で対談をさせてもらった。ポランスキーの語り口や閉鎖された空間とのかかわり、あるいは彼が得意とする関節技の繰り出し方などは興味深かったが、スリラーのプロットを明かすわけにもいかないので、いつもほどは話が広がらなかった記憶がある。もしかすると、震災の後遺症がまだ身体の片隅にあったのかもしれない。
だが同じ日付のコラムで、小林信彦さんは清水宏の『風の中の子供』(一九三七)にも触れている。あ、すごいタイミングだ、と私は思った。そうでなくとも胸に沁みる映画を、よりによってこんな時期に見てしまうとは。