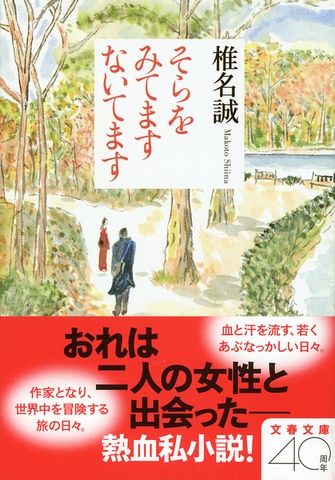「そういう構成にどんな意味があるんだ」と言われたらうつむくしかありませんが、自分の体験したこと、夢に描いていたこと、つねづね考えていたこと─を小説としてまとめるときこのようにして書き進めていくと「やはりつながっているんだなあ」ということをしみじみ感じたのは思わぬ発見、収穫となりました。
作家自身は「あとがき」でこんなふうに記しているが、おそらく彼には直感があったはずだ。人生のクライマックスを描くためのもっとも有効な、というよりもっとも自分の心に適(かな)った方法としての構成。二つのベクトルがぶつかり合って一つに重なるところ、それこそがこの小説の最大のテーマなのだから。
仮に青春ドラマをA、冒険ドラマをBとすると、Aは一九六四年、オリンピック開催間近の東京を舞台にはじまり、Bは一九八八年の、タクラマカン砂漠行から遡る。
Aの「おれ」は、深夜の皿洗いのバイトに励む学生。謎めいた女性イスズミとの官能的な恋愛や、彼女をめぐる凄まじい暴力事件。そのうち大学もやめ、日雇いやセールスや職を転々とするなかで、妻となる女性原田海と出会う。やがてひょんなことから出したエッセイ集がベストセラーとなり、作家の道を歩み出す。
一方、Bの「おれ」は、ベストセラー作家となったことを契機に急速に拡がった仕事の一つとして、憧れの探検・冒険の旅がはじまる。一九八二年夏のパタゴニア行を皮きりに、南海の孤島へ、アラスカへタイガの奥地へ、マイナス七十一度を記録したこともある極寒の北東シベリアへ、そして子どものころからの夢であったタクラマカン砂漠へ。
さまざまな仕事の現場の様子や、想像を超えるスケールの旅の現実がおもしろい。ショート・センテンスを絶妙の間合いで繰り出してゆくおなじみの文体。そこに、椎名流の情熱とユーモアがどくどくと注がれ、読むほどに楽しい。しかし最大の魅力は、時間が前進するAと逆行するBとが交錯しながらクライマックスへとつながる不思議な感覚である。
「力道山が来ているぞ」というバイト先の場面からはじまり、Aの「おれ」は、もしかしたら力道山が残したかもしれないピザをかじりながら夜明けの道を帰る。
いつもと同じありふれた夜明けだ。少し違うとしたら、いつもと少し違うピザパイをかじっている、ということだった。そしてもうすぐ夜明けの時間だった。それを誰かに言いたかった。
このあと、「そうだ。たぶんあのときが人生のクライマックスだったのだろう」を含む数行が突如はさまれ、先ほどのAの「おれ」を受けるように、「おれは歩いていて、やはり目の前に夜明けのきざしがあった。おれは砂だらけになっていて」と、タクラマカン砂漠を行くBの「おれ」が語りはじめる。