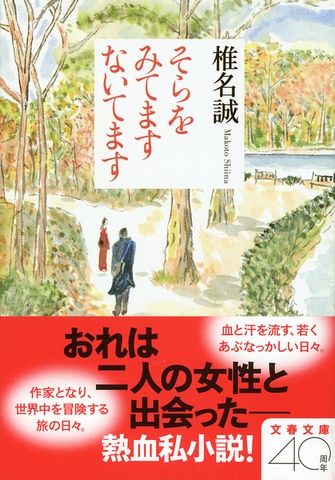いくらか頭がくらくらしながら、第六章までをすっかり読み終わったところで気づく。狂熱的な青春のクライマックスと、途方もない夢に向かって生きる人生のクライマックスとが、ここで同時に描かれていることを。Aの「おれ」とBの「おれ」とは一つであったことを。
「ちゃんと楼蘭に行ってきたぞ。しかも楼蘭故城に一番乗りで入った、おれたち、大谷探検隊から八十年ぶりに楼蘭に入った日本人になったよ」
なぜかパチパチ豆のはじけるような雑音の激しい電話のなかでおれは妻に言った。「あのヘディンのストゥーパの前に立ったぞ。あの『さまよえる湖』に出ていたヘディンのスケッチのストゥーパそのものの前だったよ。楼蘭で最初の夜に君のために道中彫っていた木彫りの鳥を完成させて、楼蘭の月の光に一晩しっかり当てた。だからそれは、楼蘭の『神』になったんだぞ。君の干支(えと)の鳥を彫った。あまりの神々しさにそれを見てひっくりかえるなよ」
「空はどうだったの?」
「星がいっぱい。楼蘭にいるあいだ夜は三日続けてテントから外に顔を出して寝てたんだ。もったいなかったからね。夜空は動いていてね、二千年前の星空と何も変わらないのだろうと思ったけれど、人工衛星が通過していくのがよく見えた。それだけが二千年前と違う風景だったんだ。満天の星の海を渡っていく光る小舟みたいにして、沢山の人工衛星が横切っていくのを見ていたよ」
妻の言葉「空はどうだったの?」に、あとになってはっとする。妻の名前は海。戦死した父がつけた名前である。どこまでも泥の平地だったという戦地で、父は最後に空を見たのではないか。だから自分は海よりも空を思うのだと、出会いのころの妻が語っている。
人生のクライマックスは、空と海の出会いでもあった。それはまた、この世で出会ったかけがえのない人と自分の人生のクライマックスとが、奇跡のように重なる瞬間でもあったのだ。
ロビーのずっと先、殆ど壁ぎわすれすれのところに着物姿の、見覚えのある小柄な体が見えた。表情は影になっていてよくわからなかったが、とにかく妻は一人でちゃんとそこに立っていた。日本を出るときにダッタン人ふうの別れの挨拶をすることができなかったので、勝利したのか敗北だったのかよくわからなかったけれど、でもとにかくおれは帰ってきた。そしてそれを迎えにきてくれる人が目の前に立っていた。そのむこう側に雪を頂いたチベットの山々や、広漠としたタクラマカンの茶色い砂漠が見えるような気がした。
横から入ってくる何台かのカートにぶつかりそうになりながら、おれは壁ぎわのその人にむかってざくざくとかけだしていた。
この小説の最後の場面。つまりBの「おれ」の時間行の源流である。急激に変化した生活の重圧にだまって一人耐えながら、妻には心の病が兆していた。だからこそBの「おれ」は第一章の最後に、楼蘭へ行く夢をかなえた報告を妻にしたのだ。Aの「おれ」とBの「おれ」とは、二十年の歳月をかけて一つにつながったのである。
人の心も、メビウスの帯かもしれない。