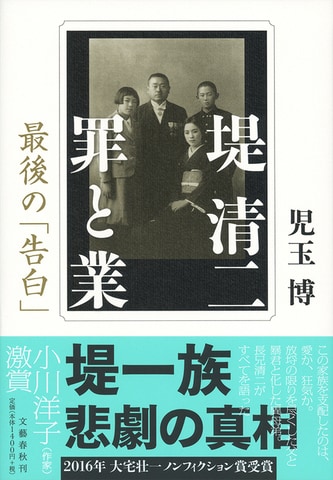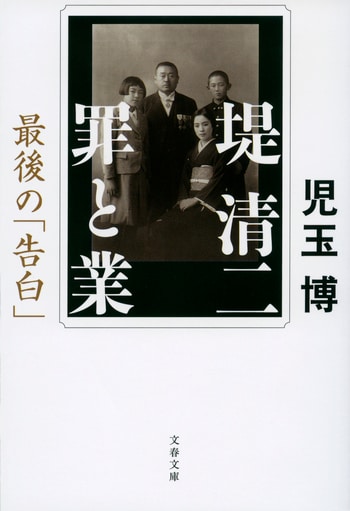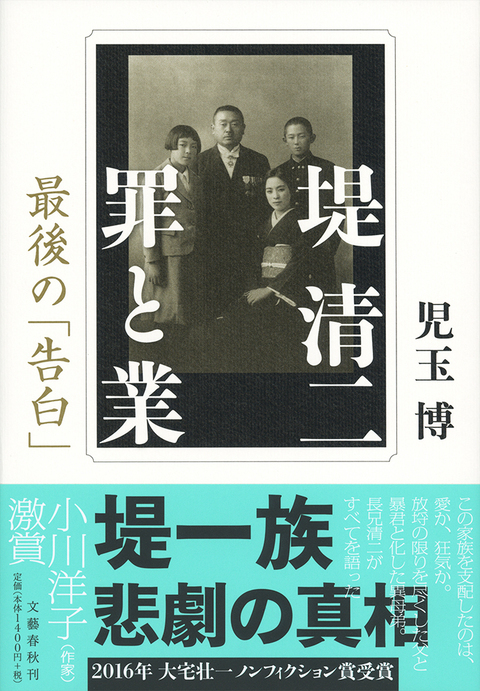
「児玉さん、もう1回やりましょう」
堤清二がこう言って、少しだけ笑ったその表情、その声を今もはっきりと思い出す。
初めて堤にインタビューが叶った2012年7月半ばのこと。場所は、今はもうない、堤が丹精を込めて作った「ホテル西洋銀座」の一室だった。
もう堤家の出る幕ではない。こうした世間の指弾を承知の上で、経済人としては、身を引いていた堤清二が、また西武グループ再編の表舞台に立とうとしていた。

私の最初の目的はこの一点、つまりなぜ再び経済人として表舞台に立つのか、を聞きたいだけだった。
ところが……。
私の率直な問いに、堤はさほど考えた様子もなくさらりと答えたものだった。
「父との約束ですから」
まったく思いもしない答えだった。
堤のこの一言からインタビューの様相は考えもしなかった方向へ向かっていった。
当初、堤が私に与えてくれた時間は1時間。ところが、初回のインタビューは予定の時間を遥かに超え2時間を超えた所で終了した。

その時、堤がかけてくれた言葉が冒頭の、
「児玉さん、もう1回やりましょう」
というものだった。
奇跡だと思った。人を寄せ付けぬ堤から発せられた言葉だったからだ。結局、堤のこの提案はその後、6回繰り返された。
堤は今まで語られることはなかった堤清二自身の胸の内、堤家の秘められた歴史をさながら遺言でも残すかのように語ってくれた。

その中で、堤は時に涙をためながら、父康次郎からかけられた親の恩を語り、父から最も愛された子供は自分なんだと何度も繰り返した。
愛を知らぬ85歳の老人が愛をいじり探す姿は、乳房を探す赤子のようであり、その一方で哀れな姿でもあった。父康次郎、放埒の限りを尽くしたこの父がいたればこそ、堤清二は堤清二であり、作家、辻井喬ともなり得た。
堤の人生は父から授けられた業と運命とに翻弄されながら闘い尽くした一生だったような気がする。それはまた母を異にする弟義明も同じだった。そこには善も悪もなければ、良し悪しなどあろうはずもない。
血族の悲劇を思う時、堤が残してくれた“遺言”は余りに物悲しく、哀れでならない。