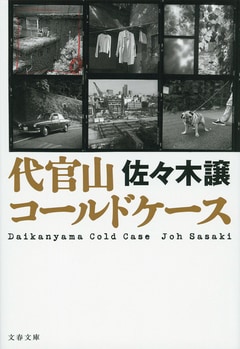――今年1月に文庫化された直木賞受賞作『廃墟に乞う』をはじめ、解きから刑事、犯人を含めた人間模様まで、とにかく読み応え十分の佐々木さんの警察小説に、新刊『地層捜査』が加わります。本作では2010年の公訴時効撤廃を受け、再捜査対象となった未解決殺人事件を2人の捜査員が追いかけますが、舞台となるのが東京・新宿区の荒木町です。まずはこの、小さな飲食店がひしめき合うように並び立つ荒木町を選んだ理由から教えてください。
「警視庁の物語にしたい、でもまだあまり書かれすぎていない魅力的な町を舞台にしたい、と考えていたときに、私の原作を舞台にしてくれた演出家の方が荒木町の出身で、『荒木町は花街だったんですよ』と話していたことを思い出しました。そういえば、深川や向島、浅草などの花街は、幾度となく小説や映画の舞台になっているけれど、荒木町はまだあまり書かれていないな、とも。
ただ、荒木町を舞台にしたとしても、どんな物語にするかまったく見当がついていなかったので、まずは編集者と荒木町に飲みに行きました(笑)。小料理屋で鍋をつついたんですが、その小料理屋の女将から、こんな話を伺ったんです。
『この店の隣は昔は置屋さんで、少し前に改築のために取り壊したんですけど、中を見せていただいたら、不思議な造作が見えてしまいましてね……』
実はその部屋は、芸妓の世界の特殊な一面を示していたんですが、この話を聞いた瞬間、ストーリー全体が見えてきたんです」
――『地層捜査』というタイトルにも示されていますが、この物語では、考古学者が堆積した地層をぎ取るようにして化石を探すように、地道な捜査によって町の記憶=手がかりが徐々に明らかになっていきます。多くの町を舞台にするのではなく、1つの町をぐっと掘り下げていくことで、物語の密度と色合いが濃くなるのですね。
「『警官の血』という作品を、東京・谷中の天王寺を舞台にして書いたんですが、谷中、という土地への興味から本を手にとってくれた読者が多かったんですね。『読んだところを歩いてみました』なんて声も聞きましたし、そもそも地元で幅広く読まれたそうです。町を舞台に、深く物語を掘り下げていくのは作家としてもやりがいがあるし、読者にもその物語が届いた実感がありました。荒木町も、谷中と同様に、とても魅力的な町です。ならば、同じ手法で描いてみてもいいのでは、と思いました。ただ、谷中は以前から馴染みのある町で、取材をしなくても町の様子がわかりますが、荒木町はそうではない。取材を繰り返して、身体に町の地形、たたずまいを馴染ませてから書きはじめました」
――きわめて大雑把に説明すれば、新宿通りと外苑東通りがクロスする四谷三丁目交差点の北東ブロックが、荒木町界隈となります。本作を読むと、読み手の頭の中に、その町の詳細が、大通りの喧騒から坂道の石畳、パリのモンパルナスを思い起こさせるような街灯、階段、町の奥底にある神社まで、その地形の起伏まで頭の中に鮮明なビジョンを結びます。お書きになるにあたって、何度も足を運ばれたのでしょうか。
「そうですね。執筆前に何度となく歩きつめましたし、小説誌での連載が始まってからも、北海道から上京するたびに、町の様子をかなり頻繁に見にいきました」
――では、行きつけの店もできたり?
「そこまではいかなかったけど、いいお店、沢山ありますよね(笑)。雰囲気のある酒場もある。イメージもどんどん膨らんでいきました。ただ、実際に荒木町に行ってみるとお分かりいただけるのですが、花街だった雰囲気というのは、一見して分かり易く感じられるものではないんですね。そうだと知って歩いてみれば、さまざまなところにその名残を見つけることができるのですが……。ちなみに谷中には今でも『お稽古通り』という裏通りがありましてね。色々な芸事の先生がいらっしゃって、三味線の音なども聞こえてくる時があるんです。執筆にあたっては、その通りの雰囲気を思い出しつつ、もう1つ、秘密兵器を投入しました。昭和30年代後半から40年代にかけて撮られた任映画、「日本侠客伝」や「昭和残侠伝」のシリーズを、改めてDVDでひとさらい観たんです。あのシリーズには荒木町そのものは出てきませんが、浅草などの花街のシーンが数多く出てきます。シリーズが撮られた当時、まだ古い東京の雰囲気は残っていたんですね。その空気を身体に染み込ませて執筆に臨みました」
――さて、一方でこの物語は、2人の捜査員が事件を追いかけていく、いわゆる「バディもの」です。ただ、その2人はたいてい、それぞれの得意分野を結集して真相に迫っていくのですが、今回の2人の関係は極めてドライで、独立していて、距離感がある。
「このところ、警察小説、刑事モノ小説や映画が格段に多くなりました。それだけに、今回は多くの警察小説で描かれているような設定の逆を行ってやろう、型をどんどん壊していこう、と思っていました。『バディもの』については、たとえば若い刑事と年老いたベテラン刑事がいい師弟関係を築きながら事件解決に迫ることが多い。もちろんよくできた作品であれば問題はないけれど、ときに鼻につく感じがします。じゃあ、2人は組むけれど、最初から対立していて、互いに出し抜いてやろう、と思いながら事件解決に進んでいく、そんな新しい形を考えてみたんです」
――若い警視庁の水戸部刑事は荒木町を全く知らず、コンビを組む元警官で今は相談員の加納は、荒木町を知り尽くしている。人間性も含めたその凸凹が非常にユニークです。
「年齢の差は、捜査手法の差でもあります。加納は長い時間をかけて築いてきた、個人の人間関係の引き出しを駆使して手がかりを探し、水戸部はデータベースや科学捜査など、最新の知見を取り入れながら、やはり地道に捜査を進めていく。その手法の差にもまた“地層”のようなものが見えてくればいい、と思っていました」
――それにしても、荒木町とその周辺の“地層”は実に複雑です。図らずもこの小説を読むことで、貧富の差をはじめ、現代の町並みが消去してしまった町の陰影を知ることもできました。
「演出家の鴨下信一さんが『誰も「戦後」を覚えていない』(文春新書)で“戦後を知る人はあまり語らないけど、しっかりと記憶しているはずだ”といったことを書いています。それこそ戦後の混乱期に、身内の方も盗みを働いたことがある、なんて告白をしていましたよね。そういった庶民の生々しい、貧困も含めた生活の歴史の記録があるわけですから、そのことを忘れて、“日本は昔から中産階級ばかりの国だった”なんてことを前提に物語を書いていてはならない、と思うのです。こういった問題意識は、何も戦後だけではありません。それこそ戦国時代をテーマにした作品には、何故侍しか出てこないのか。士農工商でいえば、農民が1番多く、商人、職人、そして一番少なかったのが侍ではないのか……。そんな思いもあって、『天下城』という作品では築城時の石積み集団である穴太衆(あのうしゅう)=石職人を主人公にしたんです」
――佐々木さんは歴史小説、冒険小説、警察小説、どんなジャンルであっても、徹底的に資料を読み込み、取材を重ねることで知られています。
「仮説を立てて取材を重ね、それが崩されることもありますし、まっさらな状態で取材地に赴き、自分が想像しているよりもはるかに面白い事実に出会ったりする。たとえば『天下城』の時は、織田信長が安土城築城よりも早い時期に石積みの穴太衆と仕事をしたのでは? と仮説を立て、信長が築城した初期のお城を取材して石垣を目を皿のようにして見ました。が、どうしてもいわゆる穴太積みではないんですね。また、私の執筆拠点の1つである中標津は酪農の町で、農協が町民の資産配分を行っている。しかも、牛1頭でいくら、という堅実さ(笑)。でも、隣の港町である標津を取材したところ、隣町なのに全く違う。漁業の町ですから、仕事は博打のようなもので、大漁だったら釧路で遊ぶのが当たり前(笑)。船と船とで若い衆の引き抜き合いなども行われていて、あちらの筋の方もいらっしゃる。これは面白いなと思って、『廃墟に乞う』の1編「兄の想い」の舞台にしたんです。
取材といえば、今回の『地層捜査』でも、連載を終えて後、最後の確認のために、また荒木町を歩きました。連載開始時と、町の様子も少しだけ変わっている。その変化もまた、ゲラをチェックする時に反映させています。読者の方にも是非、機会があれば荒木町を訪れていただきたいですね」
――実は、すぐにこの続編をお書きになる、と伺っています。
「書き始めた時は、続編のことは全く考えていませんでしたが、時効撤廃を受けて警視庁に設立された特命捜査対策室、という『地層捜査』の設定は、これからも使えるんじゃないかと思うようになりました。また、水戸部刑事をもっと活躍させてもいい。もし評判がよかったら、次もやりたいな、と思っています。『地層捜査2』の連載は、4月中頃から「週刊文春」でスタートする予定です。舞台は荒木町ではなく、別の町にするつもりですが、まだ決まっていません。2月、3月あたりは、東京のどこかの町を歩き回っていると思います。魅力的だけどまだあまり知られていない町か、皆さんがよく知る町に挑戦するか、また取材の日々が始まります」