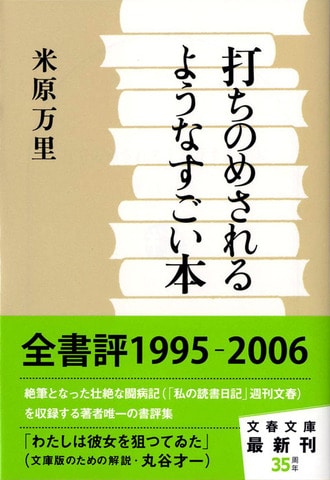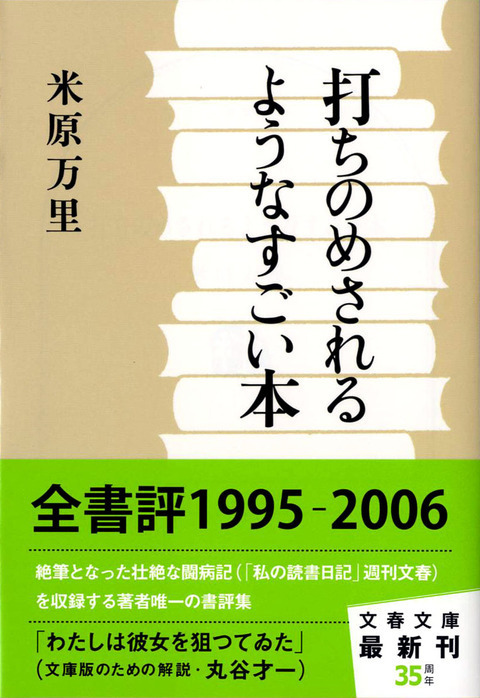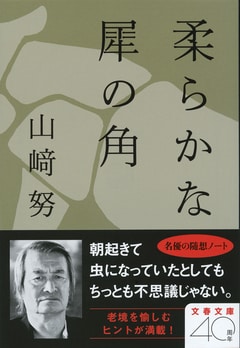私と米原万里さんの間に直接的な面識はない。ただ、米原さんは新著が出ると送ってくれたし、私も米原さんには新著を送ってきた。彼女は拙著『読者は踊る』(文春文庫)の解説を書いてくれ、私は『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』(角川文庫)の解説を書かせてもらった。そのときも担当編集者を介してやりとりしただけである。私たちは(という言い方をあえてさせてもらうけど)互いの読者だっただけである。そして、そんな関係(というのもおこがましいのだけど)が気に入っていた。米原さんもたぶんそうだったと思う。
米原万里と私の接点をもうひとつあげれば、同じ時期に別の新聞や別の雑誌で書評を書いていたことだろう。とかいうといかにも「好敵手」っぽいのだが、そもそもの教養がこちらは遠く及ばない上、彼女のは正面きった誠実な書評(たとえば「週刊文春」連載の「私の読書日記」)、私のはやや斜に構えたインチキ書評(たとえば「週刊朝日」連載の「誤読日記」)。とうてい勝負になるはずもなく、私は彼女の書評を純粋に楽しんできた。ときには、
〈「斎藤美奈子の本は全部読んでる」と自慢したら、友人に、「だって四冊しかないじゃん」と馬鹿にされてしまった〉
なんていう記述に出会い「ヨ、ヨネハラさん(汗)」と思ったこともあったけど。
さて、ワタクシ事はこのくらいにして、本書『打ちのめされるようなすごい本』は一九九五年四月から二〇〇六年五月までの米原万里の「全書評」を集めた本である。半分がくだんの「週刊文春」に載った「私の読書日記」、残りの半分が読書委員を務めていた読売新聞はじめさまざまな媒体に発表された書評と文庫解説だ。
忘れもしない、私がロシア語同時通訳者としてではない、エッセイストとしてでもない、読書人としての米原万里に刮目したのは次の文章を読んだときだった。
〈食べるのと歩くのと読むのは、かなり早い。(中略)ここ二〇年ほど一日平均七冊を維持してきた〉
刮目とは「目をこすってよく見ること」の意味だそうだが、文字通り、私は目をこすったのだった。一日七冊ぅぅ!? 嘘だ嘘だ、そんなの絶対に嘘だっ。本書にも収められているこの文章は九六年五月の「週刊朝日」に載ったもので、エッセイはこの後〈ところが〉と続き、〈二・〇を誇っていた視力がガタリと落ち〉〈読むスピードも急減速していた。悔しい。認めたくない〉という風に展開するのだけれども(そして数年後には私自身も同じことを痛感するのだが)、一日七冊の衝撃は大きく、まさに「打ちのめされた」のであった。
しかし、一日七冊×二十年(毎日七冊とはいっていないのが救いといえば救いである)のバックボーンが、書評家・米原万里の底力だったということに、この本を読むと改めて気づかされる。とりわけ二〇〇一年一月から二〇〇六年五月まで書き続けられた「私の読書日記」は、書評であると同時にすぐれた社会時評であり、読みかつ考え、読みかつ行動する彼女の人生が、そこには凝縮されているといってもいい。
十二歳くらいまでに世界的古典とされる文学作品は『三銃士』はじめ、あれもこれもそれも(悔しいので書名は略す)読破したという彼女だけあって、文学への造詣が深いのはもちろんだが、歴史や地理から政治経済、生物、言語、建築、スポーツ、そして書評欄には珍しい実用書まで、カバーする範囲は森羅万象に及ぶ。が、それ以上に注目すべきは、彼女の書評がいつも「いま」とリンクしていることだ。
ご承知のように〇一年~〇六年は自民党小泉政権と重なる時期であり、米国同時多発テロからイラクへの自衛隊派遣まで、あるいは北朝鮮問題や歴史認識問題など、どう考えるべきか迷う頭の痛い事案が目白押しだった。米原万里はそこにクサビを打ち込むような本を選び、ときには牽強付会ともいうべき手でもって読書ガイドとニュース解説を同時にやってしまうのだ。
そうして読みかつ考える姿勢は〈入院中に発注した癌本が届いていたので片っ端から読む〉日にも当然のように貫かれ、ついには書評と闘病記のドッキングという新手のワザまで開発する。「癌治療本を我が身を以て検証」と題された最後の三回は、連載当時ファンをハラハラさせたのだったが、いま読むと、それが自らの体験を惜しみなく披瀝した迫真のドキュメンタリーであり、医療現場への痛烈な批評であり、読者へのサービス精神にみちたブックガイドになっていることに舌を巻く。
書評とはひっきょうサービス業であることを米原万里はよく知っていた。そして一日七冊とは、こうやって読むことなのだと改めて教えられるのである。