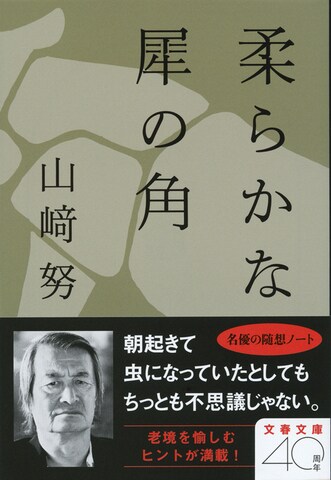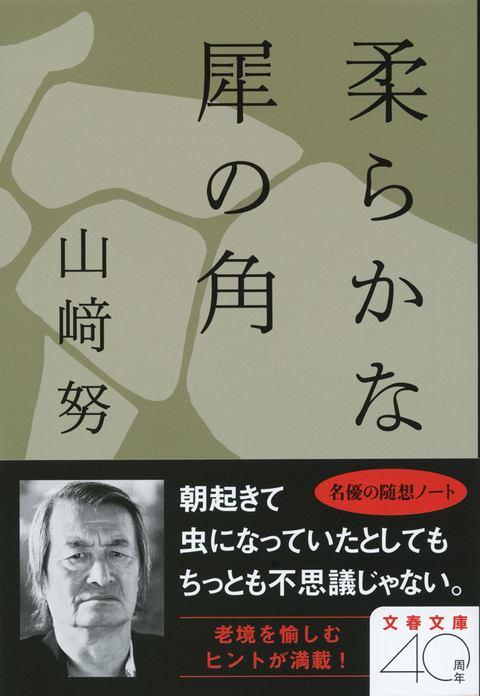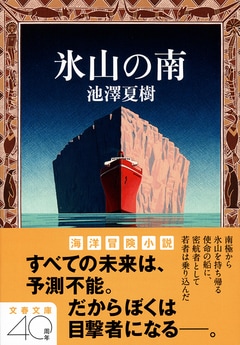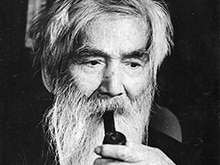先日、ぼんやりとテレビを見ていたら、東京の町をネアンデルタール人が歩いていた。普通に背広を着て普通に歩いている。行き交う人々はその男が自分たちホモ・サピエンスとは別の種であることに気づかない。
よくよく見ればたしかに顔が違う。額が出ていてぜんたいに骨格がごつい。だが、それは人間の顔の範囲内に収まっている。「あいつ変だな」と誰かが言っても、「でも、もっと変な顔の奴、俺は知ってるぞ」と言えるくらい。
で、この都内を歩くホモ・ネアンデルターレンシスの中身は山﨑努なのだ。
番組は地球上の生命の誕生から現生人類にいたる長い歩みの話で、二〇〇四年に作られた科学ドキュメンタリー(ぼくが見たのは再放送)。その中で我々と並行して生きながら三万年前に絶滅したネアンデルタール人を紹介するのに、その顔を一人作って東京の町を歩かせる、というテレビ的な場面が用意された。
化石をもとに彼らの骨格の特徴を山﨑努の顔の上に特殊メークで再現する。その手順のところもおもしろかった。ぼくは山﨑さんを個人的に知る特権的なファンであり一緒に食事をしたことが何度もある。顔は間近に見ている。
しかし彼が本当はネアンデルタール人だったとは気づかなかった。テレビを見ながら、「ずっと特殊メークでホモ・サピエンスに化けていたんですね?」と聞きたくなった。さすが名優だ。
この『柔らかな犀の角』にやはり人類の歩みという話題がある。NHKのプロデューサー高間大介が書いた『人間はどこから来たのか、どこへ行くのか』という本のこと。これとヤマザキ・ネアンデルターレンシスの関係はわからないが、しかしいい書評だ。
生きるということは環境の変化に対して常に対策を立ててゆくことだから「生きている以上、きょろきょろとあちこちに気を配る仕組みは外せないのだ」と見事に核心のところをまとめる。その先の話題の要約も間然するところがない。
「二〇〇九年の時点で発見されている化石人類は二二種。それだけの種が生まれては消えていった」とあるから、あのネアンデルタール人はやっぱり高間プロデューサーの作った番組だったんだろうか。
この本に収められた文章は週刊文春の「私の読書日記」という連載に書かれたものである。基本は新刊の本を扱う書評なのだが、形が緩やかで半分はエッセーのようなもの。その分だけ書きやすくて読みやすい。ぼく自身この欄にもう二十年くらい書いている。つまり山﨑さんのお仲間。
最初に週刊文春でこの人の名を見た時は驚いた。
その前に会った時の会話で読書人であることは知っていたが、それにしてもなんという人選・なんという起用。
しかも一回目からしてうまい。
老人という身近ながらしかしまだ自分自身からは距離のあるテーマを選び、理想の姿という感じで熊谷守一を挙げる。三十年間ずっと家から出ないで絵を描いていたという達観の蟄居に山﨑さんは感心し、こちらはその余慶に与る。困ったことにこの『獨樂 熊谷守一の世界』という本をすぐに読みたくなる。つまり書評として力があるということだ。
かつての新聞書評などには何か誤解があって、書評というのは本の評価だと思っている人がいた。学者などに多いのだが、長所と短所を並べる。時には徹底的にこきおろす。違うのだ。書評というのは本を読む喜びを他の人と分かち合うことであって、だから自分が本当に気に入った本しか取り上げない。そのおもしろさをどう伝えるかに工夫を凝らす。
すなわち山﨑書評は王道である。
それでいて余裕があって、エッセー的な部分がすこぶるおもしろい。熊谷守一について言えば、山﨑さんは「当方は未だ老年への頭のギア・チェンジが完了しておらず」であり、つまり発展途上老人であるから、理想の先達に惹かれる。あるいは集中力を欠く「怠け者」だからきょろきょろしていてもいいのだと知って安心する。読む本への関心と自分がどこかでつながっている。
そう、内的なつながりが大事だ。多摩川べりの河川敷に散歩に行くと初老の男二人がのんびり暮らしている。声を掛けても相手にしてくれない。「猛々しくてなかなかいい」と思いながらその場を去る。
と、思っていたら、二十ページ先でまた同じような連中に会う。鬼海弘雄の写真集に同じ河川敷があって、それをきっかけに山﨑さんはそこにあったラーメンとおでんとビールの屋台のことを思い出す。地元の不良おやじがいつもたむろしている。
「あれは何ですか」
「――あれは太陽です」
というようなちぐはぐな会話がおかしい。ちょっといかれた八八歳がふらふらと迷い込んで、たぶん居心地よくその場に溶け込んだのだ。