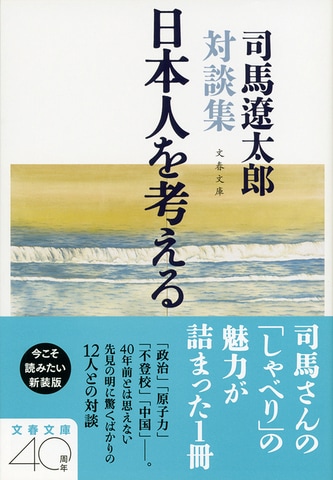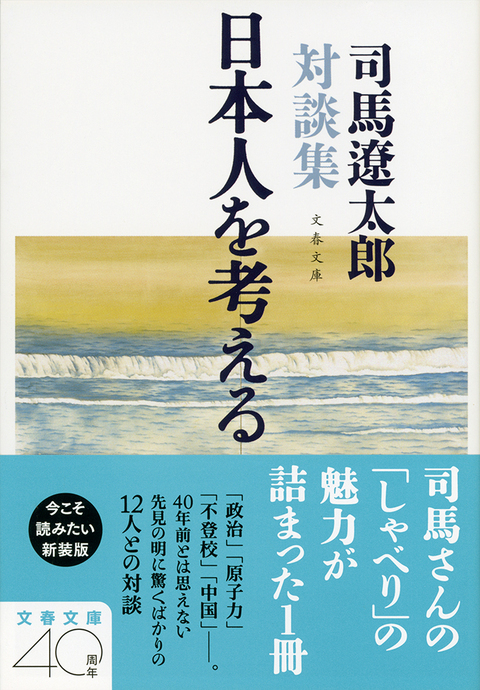司馬さんはこうした三島の思想と行動に組しない。「対談集」の民族学者・梅棹忠夫さんとの対談の中で「戦争をしかけられたらどうするか。すぐ降伏すればいい。戦争をやれば百万人は死ぬでしょう。レジスタンスをやれば十万人は死にますね。それより無抵抗で、ハイ持てるだけ持っていって下さい、といえるぐらいの生産力を持っていればすむこと。向うが占領して住みついたら、これに同化しちゃえばいい。それくらい柔軟な社会をつくることが、われわれ社会の目的じゃないですか」と発言し、梅棹さんも「いいヴィジョンですな」と同感している。つづけて「無思想・無帰属人間をわんさとかかえた無階層社会――人類が初めて経験する社会に、われわれは踏みこんでいる」と言うのに司馬さんも「まさに世界の先兵ですな」と合槌をうっている。三島由紀夫スタイルの堅い日本像と対照的な司馬遼太郎流儀の柔軟な日本・世界像が読みとれる。
私はスポーツ総合誌「ナンバー」の編集を経験してから、スポーツを補助線に使って世の中を見るクセがついた。この「対談集」の対談が行われた一九七〇年を、私は一九五九(昭和34)年から一九七四(昭和49)年まで十五年の大枠の中で考えてみたい。この十五年間に戦後日本の大きな転換期があった、と思うからだ。一九五九年はいまの天皇・美智子皇后のご成婚の年であり、それにあわせてテレビが爆発的に普及した。また週刊文春をはじめ、出版社系の週刊誌が次々に創刊され、大衆情報消費社会の幕明けとなった。
この年、もっとも忘れられないのは六月二十五日。後楽園球場の初めての天覧試合で、巨人・長嶋茂雄が阪神の村山実投手からサヨナラホームランを打ったことだ。巨人に入団したばかりの王貞治もホームランを打ち、ONアベックホームラン第一号となっている。天皇はサヨナラホームランに身をのり出し、大きく拍手して喜こばれた。退席予定時間の午後九時十五分ギリギリのホームランで、チャンスに強い“燃える男”の面目躍如たるものがあった。長嶋は戦後日本の最後の、唯一人の「公僕」だと私は思っている。王貞治が「空前絶後の人」とあきれるぐらい寝ても醒めてもファンを喜ばすことだけを考えつづけた人が、昭和天皇の前で武勲をたてたのである。神としての純粋天皇を考えつづけた三島由紀夫に対して、長嶋は象徴としての人間天皇を肯定し、共に生きることを態度で示したのである。後に長嶋は私のインタビューにこう話してくれたことがある。
「自分の頃の東京六大学野球は黄金時代で、秋山、土井、近藤和、森、杉浦、本屋敷……とキラ星のような選手の中で、ただ一点、私が彼らとちがったところは、砂押監督から徹底的にアメリカ野球を叩き込まれたことです。つまり、私くらいアメリカナイズされた人間はいないんです」と実にうれしそうに話してくれたのである。自称ナショナリストは掃いて捨てるほどいるが、こんなにアメリカナイズされた人間であることをうれしそうに話す人はいない。つまり、もっともアメリカナイズされた人間が、右手にバット、左手に戦後民主主義を持って、天皇に真正面から向かいあい、心から慰めたのだ。三島由紀夫型の愛国主義、ナショナリズムではなかった。