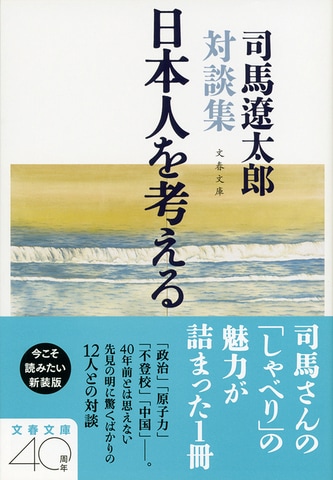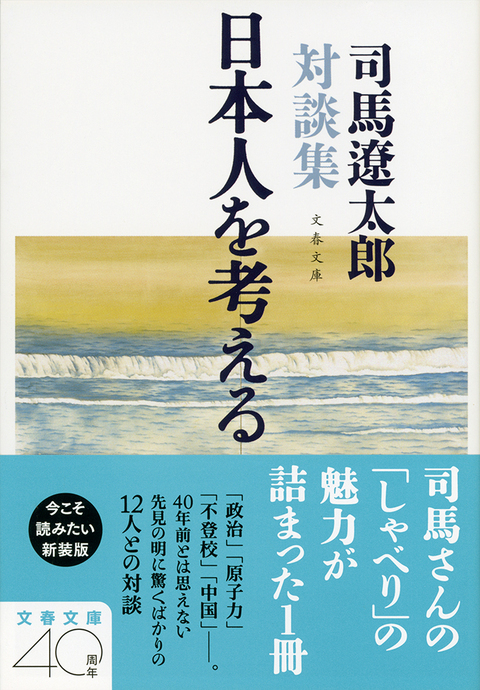司馬遼太郎さんは座談の名人である。何よりもあの温(あたたか)く柔かい、しっとりとした声が体にしみ通る。語られる内容も、筋張った論理や鋭い観察に基づいた予見が、乱反射するような多彩な人間的なエピソードにくるまれて、スルスルと体の中に入り込み、あとで何度も反芻して楽しめるのである。私が出会った座談の名手は三人。小林秀雄、宮本常一、司馬遼太郎。批評家の小林秀雄は麻糸の手ざわり。どこかサッパリと清潔な感じ。民俗学者、というより足で歩く旅の達人・宮本常一は木綿の手ざわり。ほっこりと土や草の匂いがして、古風ななつかしい生活感が漂う。司馬遼太郎は練り絹。光沢のある柔らかさに包まれる感じだ。こう書きながら、私は昔、司馬遼太郎さんと立花隆さんの対談「宇宙飛行士と空海」の席に同席したときのことをなつかしく思い出す。
「伊勢物語に、やんごとなき家の深窓のお嬢ちゃんが、強盗にさらわれる話があります。人さらいが少女を背中に負ぶって、月夜の浅茅ヶ原を走って逃げる。それまで、そんな夜中に外出したことのなかった少女は、すすきの葉先に夜露が宿って、月の光でキラキラ光っているのを見て、あれは何?、と夜露の美しさにうたれるのですが、宇宙飛行士が遠い宇宙から見た青い地球は、さながらその少女が見た、キラキラ光るすすきの葉先の夜露のようなものだったんでしょうね」
司馬さんは詩人だな、と思っていると、突然停電になり、部屋はまっ暗になった。料亭の仲居さんがあわてて蝋燭を取りに走ってくれたが、その間も二人の話は静かに続いた。目が慣れるにつれて、司馬さんのみごとな白髪がぼんぼりのように淡く光り、柔かくしっとりとした声が遠い宇宙のかなたから届くような不思議な感覚にとらわれた。
こんど四十数年ぶりに、この「司馬遼太郎対談集 日本人を考える」を読みなおして、まざまざと司馬さんの声が甦えるような気がした。
この対談は一九六九(昭和44)年から七一(昭和46)年にかけて行なわれている。一九六〇年、一九七〇年代はまさに日本の高度経済成長の時代で、その目覚しい発展ぶりは“世界史の奇跡”といわれ、“ジャパン・アズ・ナンバーワン”と称された。敗戦の痛手もようやく癒えて、日本人が自信を取り戻した時代であった。一九七〇年三月から半年間開かれた大阪万博には六〇〇〇万人を越す人々がつめかけ、六年前の一九六四年の東京オリンピックにつづいて、日本の国力の充実を世界に見せつけた年である。と同時に、同じ一九七〇年十一月二十五日、作家の三島由紀夫が楯の会の森田必勝他三名と自衛隊市ヶ谷駐屯地に乱入、一〇〇〇名近い隊員にクーデター決起を呼びかけ、直後に割腹自決するという前代未聞の事件が起きた年でもあった。そのとき三島は次のような檄(げき)文をまいた。
「われわれは戦後の日本が、経済的繁栄にうつつを抜かし、国の大本を忘れ、国民精神を失ひ、本を正さずして末に走り、その場しのぎと偽善に陥り、自ら魂の空白状態へ落ち込んでゆくのを見た。政治は矛盾の糊塗、自己の保身、権力欲、偽善にのみ捧げられ、国家百年の大計は外国に委ね、敗戦の汚辱は払拭されずにただごまかされ、日本人自ら日本の歴史と伝統を瀆してゆくのを、歯噛みをしながら見てゐなければならなかった。……」
三島は一九六一年に短篇小説「憂国」を書き、つづいて二.二六事件を描いた戯曲「十日の菊」、そして六六年に太平洋戦争を描いた小説「英霊の声」を書き上げ、いわゆる天皇三部作を完成させていた。戦争責任を問われることなく、昭和21年元旦に「人間宣言」をした天皇に対して、「などてすめろぎは人となりたまいしや」と問い詰め、鋭く刃をつきつけたかたちだ。どんな屈辱があろうとも、アメリカのいいなりになろうともそれは構わない。しかし、天皇が人間になられては困る、日本人、日本文化のためにあってはならないことだ、と主張するのである。もちろん、アジ演説を聞いた自衛隊員はそれにまったく反応せず、世の中の大半の人々も信じがたい妄動として無視しようとした。しかしこの事件は経済的繁栄の下、天下泰平に酔う日本人の虚を衝き、みんなの心に一抹の不安の影が走ったのも事実である。