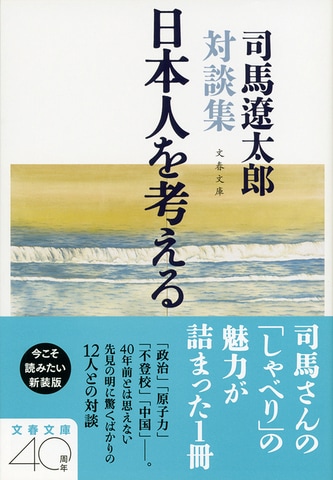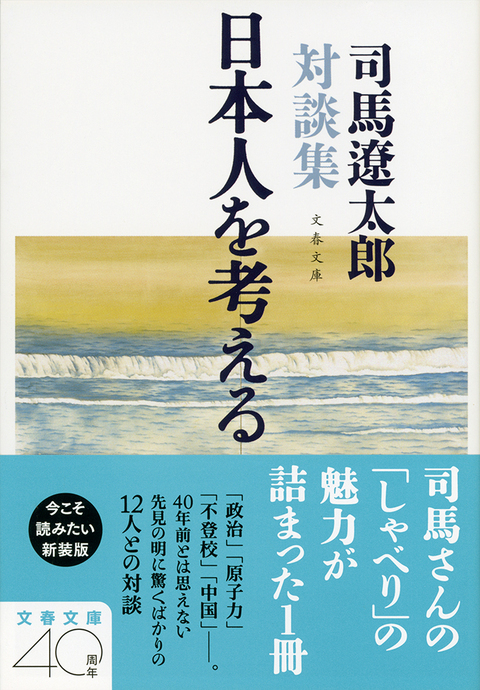精神医学の辻悟さんとの対談で司馬さんは「若い人が全員、個々に生きる目標を持たなければ生きていけないような時代も、今はじめての経験です」と未来を予知している。政治学者・高坂正堯さんとの対談では「日本歴史の中で政治家を四人あげよといわれたら、私は信長、秀吉、家康、それに大久保利通をあげますね。大久保はステーツマンであって、しかも陰謀政治もできる稀有の人物。長期のヴィジョンをもっていたし、それを実現するための権力についても、内科的所見も外科的処置もちゃんと知っていた」と歴史的知見を披露し、高坂さんが「大久保はシラフで二つのことができた珍しい例」「正論は官僚の議論で政治家の議論じゃない。正論というのは直線の上をずっと走るようなもので。しかし人間というのは千鳥足にいくんです」と受ければ、司馬さんが重ねて「政治に教科書はない、人生に教科書はない、そこから出発せんといかんということですな」と結論を出す。この丁々発止、打てば響く関係を瞬時にして出現させるところに座談の名人芸がある。あらゆる話題に対応できる引出しの多さ、どんなに不安・失望を語ってもどこか窓があいていて風が吹き抜けるような開放感がある。それが対談を読むいちばんの楽しみなのだ。
戦後日本の原子力利用の草分けである向坊隆さんは対談の中で「(原発のコストは安い)ところが、原子力発電には安全性の絶対確保という重大問題がある。広島に落とされた原爆は重さにして二~三キロの“死の灰”をばらまいたが、原発にはその灰がトン当りで溜っていく。これを絶対にばらまかない、漏らさない工夫、設備が必要です」
「原爆をつくるのに要する核物質の量なんて、原子炉を動かす量にくらべればほんのわずかで、いわば誤差みたいなもの」と言い切っている。二〇一一年三月の東日本大震災で爆発、メルトダウンしたフクシマ原発の大惨事が、四十数年前に予言されているのである。恐ろしい予言である。それをうかうか読みすごしてきたのだ、とつくづく思う。
日本の碩学、英知といわれる人たちのほかに、竹林の七賢人を思わす作家・富士正晴さんとの人を食ったような対談も脱線しているようでハッと思わせるところがある。富士さんは「全共闘の運動をはじめはおもろいと見ているが、そのうちに、一つも前と変ったことせえへんやないか、陳腐やないか、もうちょっとおもろいことやらんかいなという気になってくるんやな。退屈してしまうんや。同じことばかりやって、しょむないやっちゃ、全共闘は。そういわれて、もう終いや。けったいな国やな、日本は」と言い、司馬さんも「戦争に負けた当座は、これから面白い日本人が出てくるだろうと思ったし、そのきざしもたくさんあったけど、しかし負けたことを知らん若い衆が出てきたら、また元通りになってしまった」と言う。日本人への失望、不安を卒直に語っている。司馬さんは作家独特の嗅覚で、日本の薄闇を見透している。根底にどこかニヒリズムがあるように思えてくるが、しかしそれは明るいニヒリズム、透明なニヒリズムのように感じられるのはお人柄のせいだろう。
「対談集」の最後に日本サル学の創始者、今西錦司さんとの対談で司馬さんは「人間は手ざわりで、肉体でさわらなければ教育はできないものでしょうね」「このままでいくと人類は滅びるのも、それはやむをえないと思っています」と言う。人間の未来に関して、楽観的な見方をしていないことが分かる。それでもどこかに希望がひとはけついている。
「対談集」を読みながら、あらためて「温故知新」を思う。古きを温めて新しきを知る。古いもの、過ぎ去ったものを自分の体温で温めながら、そこから英知を汲み取っていくしかない。司馬さんは自由自在の話術を駆使しながら、そのことを読者に教えてくれるのである。四十数年前に語られた言葉が、今の時代に読まれることによって、新しい生命がふきこまれるのだ。それらの言葉によって読者は元気づけられ、はげまされる。すぐれた対談には、まるでその場に居合わせたかのような臨場感がある。