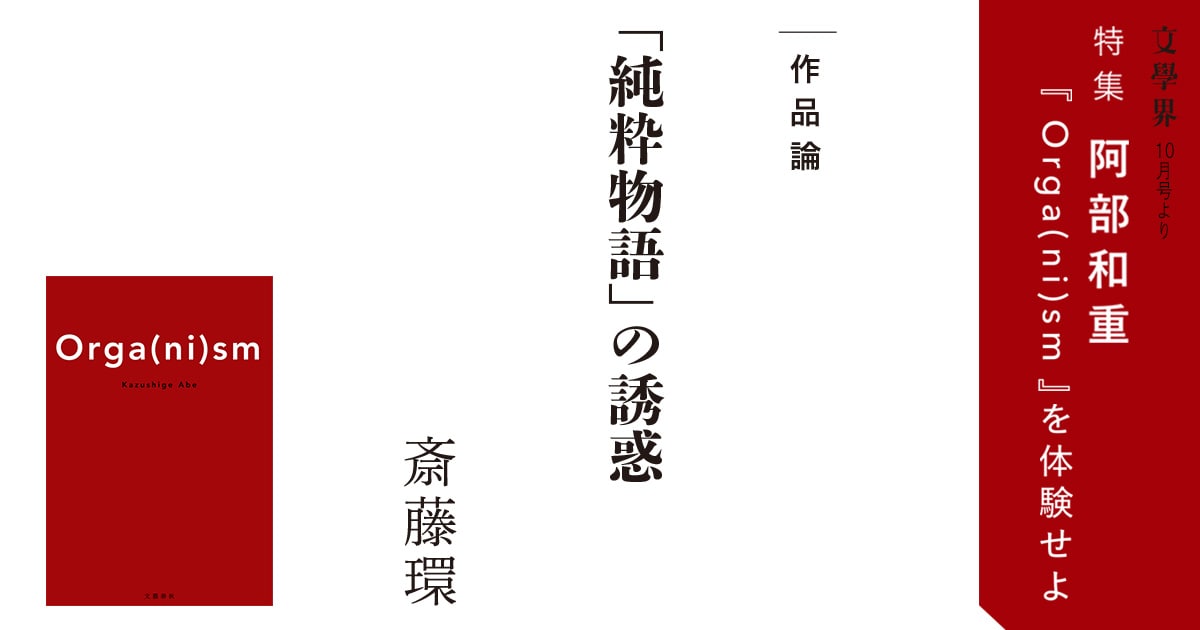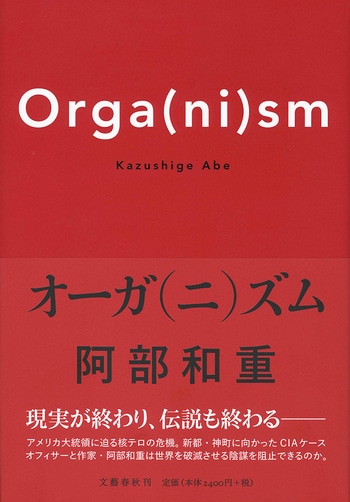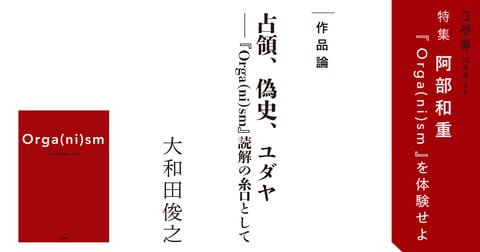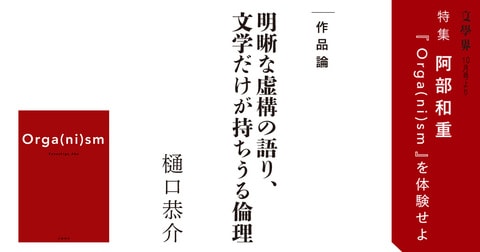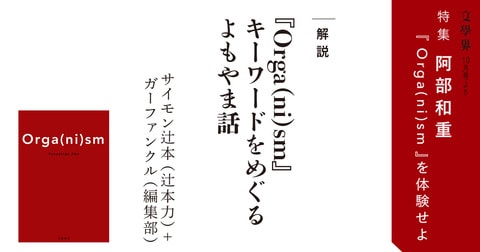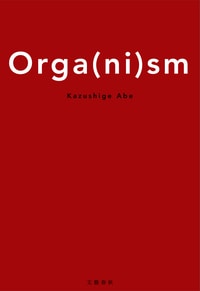
スタイルの変遷
これはまたなんという企みか。阿部和重による「神町(じんまち)サーガ」三部作の掉尾を飾る大長編は、期待を上回る問題作として完結した。奇しくも阿部のパートナーである川上未映子が、長編『夏物語』を発表したばかりというできすぎたタイミングである。決して大げさではなしに、二〇一九年という年は、さまざまな意味で対照的なカップルによる二つの傑作が、日本文学の幅を押し広げた年として文学史に刻まれることになるだろう。
私は「文學界」二〇一〇年五月号において、当時出版されたばかりの『ピストルズ』をテーマに、阿部和重と対談している。当時、彼は次のように述べていた。
「一作ごとにガラッと全部手法を変えていくというスタイルに、憧れをずっと持ってたところがあります。小説に限らず、たとえばポップミュージックの世界だとか、まあ映画でもそうですけど、そういうふうに作品をつくっている作家やアーティストは結構いるわけですよね」。ここで阿部が挙げる固有名詞は、ゴダールとデヴィッド・ボウイだった。
神町サーガの一作目『シンセミア』の連載が「アサヒグラフ」で開始されたのが一九九九年。サーガ完結にちょうど二〇年が経過したわけだが、その間も阿部はめまぐるしくスタイルを変遷させてきた。本作の主人公である作家・阿部和重の形容として「テロリズム、インターネット、ロリコンといった現代的トピックを散りばめつつ、物語の形式性を強く意識した作品を多数発表している」作家、という半ばは自嘲的な決り文句(Wikipediaからの引用)が繰り返し登場するが、まさに阿部はスタイルと形式を意識的に変容させてきたのだ。
『シンセミア』において際立つのが、土着性と暴力性を強調したフォークナー=中上健次的スタイルであるとすれば、『ピストルズ』では一転して、少女たちが花とたわむれるファンタジー小説風の文体が採択されている。そして本作『Orga(ni)sm』では、驚くべきことにエンターテインメント小説とみまがうスタイルが採用されているのだ。おそらくここには、本作の連載が開始する直前に発表された長編、伊坂幸太郎との合作『キャプテンサンダーボルト』の影響があるだろう。いやむしろ、『キャプテン~』が、本作のための一種の文体練習として書かれた可能性も勘ぐってみたくなる。
先述した通り、本作の主人公は作家・阿部和重本人だ。二〇一四年三月三日の夜、彼の自宅をニューズウィークの編集者を名乗るアメリカ人、ラリー・タイテルバウムが訪問する。脇腹に裂傷を負い血まみれのラリーは、阿部に手当を請い、半ばパニックに陥りながらも阿部はかいがいしく彼の世話をするはめになり……というのが、とりあえずの導入部だ。
ただし本作の世界線は、われわれの現実社会とは微妙にずれている。阿部和重本人についていえば、デビュー二〇周年を迎えた落ち目の小説家、ということになっており、落ち目はともかく二〇周年というのは正しいし、『ニッポニアニッポン』や『ミステリアスセッティング』への言及はあるから作品歴もある程度一致する。しかし芥川賞受賞作の『グランド・フィナーレ』への言及はなく、当然なのかもしれないが、神町サーガへの言及もまったくない。「シンセミア」という単語は出てくるが、これは実際の大麻を指す言葉として用いられているのみ。さすがに神町サーガの書き手が神町を訪れたりしてはまずいという配慮があったのだろう。「シン・ゴジラ」の世界に「ゴジラ」という単語が存在しないのと同様に。
ちなみに本作の阿部和重は、著名な映画監督であるらしい妻の「川上さん」が四作目の映画撮影で神町に長期滞在中のため、息子の映記(えいき)とともにお留守番中という設定になっている。フィクションにするのであれば映画評論家でもある自身を映画監督にしそうなものだが、あえて妻にその役目を設定した「配慮」は興味深い。
しかしそれ以上に、本作における阿部和重の扱いがけっこうひどいのは自虐の一種とみるべきだろうか。なにしろ物語の冒頭で、いきなり知人に足の生爪を剥がされるわ、息子の映記(三歳)からは舐められっぱなしだわ、妻のマネージャーである「山下さん」からは「撮影中だから邪魔すんな」みたいな扱いをうけるわ、さんざんである。
以上からもわかるとおり、本作のスタイルは、『シンセミア』とも『ピストルズ』ともまるで似ていない。本作の文体は、ギャグとユーモア満載のエンターテインメント小説のそれである。信じられないという向きには、以下の引用をお読みいただきたい。
「阿部和重は『怪獣総進撃』のゴロザウルスみたいに凱旋門をまっぷたつにすると……」
「ベスト・ファーザー賞受賞者ならこんなときにどうふるまうのかとアベレージ・ファーザーが考えているうちに静けさは終わりを告げた」
「これ以上の楽観が浮かぶようならそいつは正常性ダイモスだか闘将バイアスとかいうやつだから、自分の考えを決して信じちゃならないと阿部和重はみずからに言いきかせる」
こうした文体の軽さも相まって、本作は異様なまでにリーダブルである。さらに前二作と決定的に異なるのは、本作においては「誰も死なない」点であろう。重傷を負う人物は何人かいるが、オバマ大統領の神町訪問に際して持ち込まれたとおぼしいスーツケース型核爆弾をめぐる攻防、というぶっそうなテーマの割には、まったく殺人が描かれないのだ。これはたまたまではなく、阿部が本作を書く際に自らに課した制約の一つだったのだろう。ついでに言えば本作では男女間のセックスも描かれない。それこそ、禁欲的なまでに。
いかに「小説」を構築するか
「制約」といえば、阿部の小説作法は、一般の作家(なる存在があるかどうかは知らないが)とはかなり異質だ。再び私との対談記事から引用しよう。
「キーワードとなる言葉が浮かんでくることもあれば、物語の大まかな流れがそのままアイディアとして生まれるということもありますし、あと、場面だったりもしますね。それらのうちのどれかがいきなり断片的に降ってくる感じです」
「ストーリーを作ることに関しては苦労はまったくないですね。そういう意味では、『シンセミア』のような群像劇を考えるのは僕にとっては全然難しくない、むしろ気持ちよく楽にできちゃうんです。その分、アイディアを文章化していく段階でいろいろと細かい工夫をほどこさずにはいられなくなるので、辛い修行になってしまうんです」
「一ヵ所でも何かどこかでキャラクターに勝手な動きをされると、成り立たなくなってしまいますから。だから、予め細かいところまで設計図をきっちり作った上で、それを見ながら書くんです」
このように、阿部はきわめて構築的に小説を書いている。とりわけキャラクターの自律性を許さないという点には驚かされた。素人考えに過ぎないが、これは相当にきつい制約ではないだろうか。まして『Orga(ni)sm』では、登場人物がいちいち「キャラが立って」いるのだ。主人公の阿部和重はもとより、その子であるわがままいっぱいの三歳児・映記、トビー・ジーグラー似のCIAケースオフィサー、ラリー・タイテルバウムや、ユマ・サーマン似でチョコの「小枝」を愛するCIA職員エミリー・ウォーレンなど、かつてないほどのキャラの立った面々が登場する。ちなみにトビー・ジーグラーとはNBCのドラマ「ザ・ホワイトハウス」に登場する広報部長の役名で、俳優リチャード・シフが演じている由。
漫画であれ小説であれ、キャラが立つということは、通常はキャラが自律性を獲得することを意味する。かの小池一夫理論によれば、ストーリーよりもキャラクターが重要であり、キャラが立てばストーリーは勝手に生まれてくるはずではなかったか。そうなると不可解なのは、阿部がなにゆえキャラの自律性を抑圧し、いかにしてストーリーに従わせることに成功したか、という点になる。そんなことが果たして可能なのか。