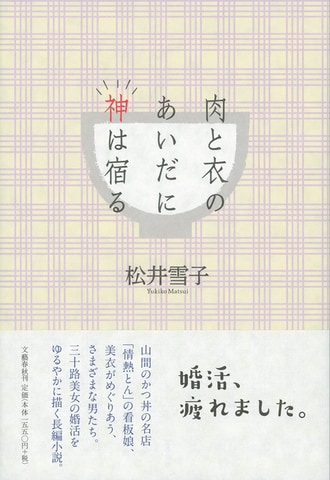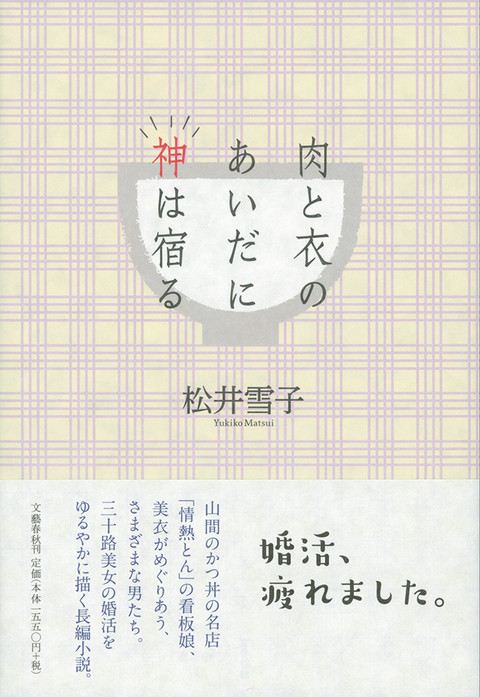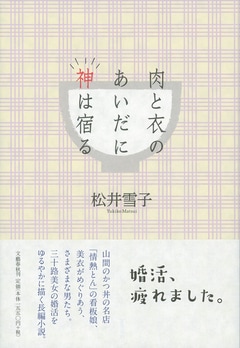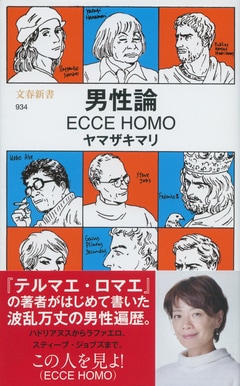少しはにかんで言う彼女の声を聞いたときに、恥じらいながら、でも真剣に、服を脱ぐ女性のイメージがわいた。と同時に、昼間のとんかつを思い出した。
人間の肉と衣のあいだにも、なにか大切なものが鎮座しているのではないだろうか。服を脱ぎ、肌をすりあわせるときまで寄り添う神様のようなものが、きっといるに違いない。
それが何であるのかを知りたい一心で、とんかつの神様のことはだれにも告げず、小説を書くことにした。
数日後、都内の飲食店でYさんと打ち合わせをした。
とんかつの神様を胸に秘めている私に、コンカツ、コンカツ、コンカツ、と彼女は三時間近くにわたって婚活にまつわる話をしてくれた。その熱い語りっぷりは、スポットライトを浴びたオペラ歌手が愛のアリアを熱唱しているように見えた。婚活の話は雑談だったかもしれない。でも打ち合わせ時間の95パーセントは占めていた。
帰りの特急電車に揺られながら、わたしの頭のなかでは、とんかつとコンカツが追いかけっこを始めていた。
駄洒落はさておき、このふたつはどこか似ている。
とんかつの油をまとった衣。食欲を満たすだけならば、肉を食べるだけでいいのではないか。その衣はなにゆえ必要なのか。
なぜ結婚を前提とした相手を探すのか。交際相手を見つけるだけでは、物足りないのか。
とんかつとコンカツは、理屈では説明のつかない要求に支配されているように思えた。そこがどこか切実で人間味にあふれ、魅力的だった。たくましく生きていくためのエネルギーに満ちていた。
小説を書きながら、近所のとんかつ店を巡り、たくさん食べた。単行本の作業中も食感を再確認するために食べ続けた。もう仕事にかこつけて、思う存分とんかつを食べられないのかと思うと、少し残念だ。
せめて今後は『肉と衣のあいだに神は宿る』を読んで食欲をそそられた読者が、とんかつ店に駆け込んで、存分にとんかつを食べてくださいますように。
そしてちょっとだけ、好きな人のことを考えながら、みそ汁をすすってほしいと願っている。