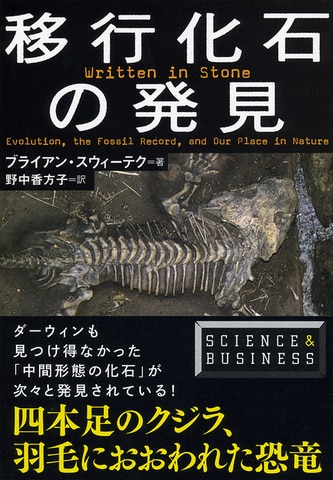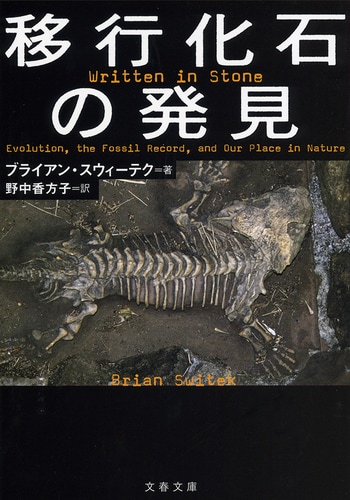著者ブライアン・スウィーテクは古生物学の研究者であるとともに、さまざまな雑誌やメディアで活躍する気鋭のサイエンス・ライターでもある。「訳者あとがき」でも触れられているように、教育実習で小学生に進化論を教えようとしたときに、校長から横やりが入って中止させられたことが、本書執筆の動機だったらしい。
日本では、学校で進化論を教えることに抵抗はないが、福音派を中心としたキリスト教原理主義者の多い米国では、進化論は久しく政治的・宗教的論争の対象となってきた。聖書に書かれたことが唯一の真実だと信じる人々は進化論がその教義に反するもので、学校で教えることは信仰の自由を侵すものだという言い分である。これまで進化論と宗教の対立は米国だけの特殊事情だと思われてきたが、近年では、進化論教育批判は英国やドイツなど、西欧諸国にもひろまりつつある。というのは、それらの国で人口比率を増大させつつあるイスラム教原理主義者も、キリスト教原理主義者と同じように、進化論を学校で教えることに反対するからである。
進化論がキリスト教に与えた最大の衝撃は「種が変わる」という事実である。種は神が個別に創造されたものであり、不変のものであるというのがダーウィンの時代における圧倒的多数の人々の共通認識であり、種の不変性の否定は神の全能性に対する否定にほかならなかった。もう一つの衝撃は、進化論の論理的な帰結として、人間も他の生物から進化したのであり、もはや神に愛される特別な存在ではなくなったことである。
極端な原理主義を支持しない多くのキリスト教徒は、進化論を宗教と切り離して、科学的な学説として受け入れているが、そうした人々のあいだでも、進化論についての不信感や誤解は根強く残っている。インターネットで「進化論はまちがっている」という類の意見を述べているサイトは無数にある。そのほとんどは、キリスト教原理主義者のものであるが、ごく少数ながら科学理論として欠陥を論じているものもある。宗教的なものを含めて、進化論批判の根拠としてもっとも頻繁にもちだされるのが、本書の主題である中間種(移行化石、ミッシングリンク)の不在である。とくに頻繁に言われるのが、サルから人間が進化したのなら、どうして中間種が見つからないのかという批判である。
進化が突然変異と自然淘汰(自然選択)によってA種からB種やC種を経てD種へと漸進的に進行したのであれば、その中間にあるはずのB種やC種の化石(ダーウィンは「移行段階にある化石」と表現している)がいっぱい見つかっていいはずなのに、中間種の化石が存在しないのは、進化が起きなかった証拠だという論法である。しかし、ダーウィンはA→B→C→Dといった直線的な形で進化が起こるとは考えていなかった。直線的な進化のイメージを定着させた責任は、トマス・ハクスリーやハーバート・スペンサーらにある。ダーウィン自身が想定していた進化の系列は、『種の起源』でたった一葉だけ挿入されている進化の模式図(第四章、同じ図が第一三章で種の系統的類縁関係を示すのにも使われている)に明らかである。それは、種が木の枝のように分れていく樹状モデルで、今日生き残っている生物種はその先端の葉っぱに相当する部分なのである。したがって一枚の葉っぱは枝を通じて木の根元までつながっているが、葉っぱどうしは孤立していて直接のつながりがないのと同じように、現生種のあいだをつなぐ、生きている中間種が見つからなくとも何の不思議もない。
こうした観点からすれば、「中間種」は現生の種と種のあいだを直接につなぐものではなく、進化の中間段階を示す化石ということになる。そうなれば、両生類や爬虫類は、魚類から哺乳類に至る進化の中間種だともいえる。チンパンジーとヒトは、直接につながってはいないが、それぞれの進化的な系譜をさかのぼっていけば、どこかで合流する。その地点からサルとヒトに至る無数の中間種が存在するわけである。
とはいえ、キリンのような首の長い動物が首の短い種から進化したのなら、中間的な首の長さの種の化石が見つからなければおかしいのではないかという疑問は検討に値する(実際には首の短いキリンの仲間としてオカピが現存する)。ダーウィンはそのことをよく理解していて、自らの理論が抱えるいくつかの難点について論じた『種の起源』の第六章で、この問題を検討し、一応の答を出している。第一に、化石はごくまれな特別な地形的条件でしか形成されないので、化石の記録は完璧なものではなく、さらにこれまで発見された化石はごく一部でしかないから、今後発掘調査がすすめば中間種がもっと発見されるだろうということ。第二に、種が分岐するとき一般に中間型は分布が狭く、個体数も少ないので、化石として残りにくい、といった理由をあげている。
ダーウィンの希望的な予測は、その後のさまざまな移行化石の発見によって実現されていった。アウストラロピテクスや多数の初期人類化石は、類人猿とヒトのあいだをつなぐ移行化石である。「サルと人間をつなぐ化石は一つとして存在しない」という、キリスト教原理主義者の常套句は、まったく事実無根の偽りである。それ以外にも、本書に述べられているように、あらゆる生物に関して無数の中間化石が発見されている。たとえば、絶滅した海生爬虫類のモササウルスはヘビとトカゲの中間型であり、漸新世に絶滅した陸生哺乳類のメソニクスはクジラ類の祖先グループである。魚類から両生類への進化的な移行について決定的な証拠となるティクターリクの発見物語(ニール・シュービンの『ヒトのなかの魚、魚のなかのヒト』参照)は、こうした化石探しが単なる運まかせの偶然によるのではなく、地球と生物の歴史についての深い考察が前提になっていることを明瞭に示している。
本書は化石学、古生物学の歴史を描いたものとして、非常によくできている。単なる事実の羅列ではなく、化石の発見から、その意味の解明にかかわった多様な人々の営みが歴史的な背景の中で生き生きと語られている。そして、ありきたりのサイエンス・ライターではなく、現役の古生物学者でもあるところから、進化に関して明確な立場を表明していることも強みである。冒頭の「序章」で化石イーダの発見をサルと人間のミッシングリンク発見として大騒ぎしたマスコミを痛烈に批判し、結びの「終章」で進化の偶然性を強調するスティーヴン・ジェイ・グールドの進化観を詳述しているのなどはその真骨頂である。
幼い頃にニューヨークの自然史博物館で恐竜の化石に心を奪われたという記述は、まるでグールドの話とそっくりに思われ、彼のグールドへの傾倒ぶりも納得がいく。ただしグールドのライバルであるリチャード・ドーキンスへの対抗心が過剰になりすぎているところもある。「序章」でドーキンスの「化石がなくても進化の歴史について多くを学ぶことができる……化石はボーナスのようなもので、なくてはならないものではない」という記述を取り上げて、「古生物学を見下している」と非難するのは勇み足だろう。ドーキンスが言っているのは進化の証拠は化石以外にもどっさりあり、そうした証拠だけでも進化は証明できるという意味であり、古生物学を蔑む意図はまったくないはずだ(ただし、私自身がドーキンス派だからと言われるかもしれないので、読者はそれを割引して、もっと客観的に判断していただきたい)。
いずれにせよ、本書は現時点における中間化石の宝典であり、これを読んでもなお、中間種がいないから進化論はまちがっていると言い張る人がいるとすれば、その人は神の国の住人ではあるかもしれないが、科学の国の住人でないことだけは確かである。