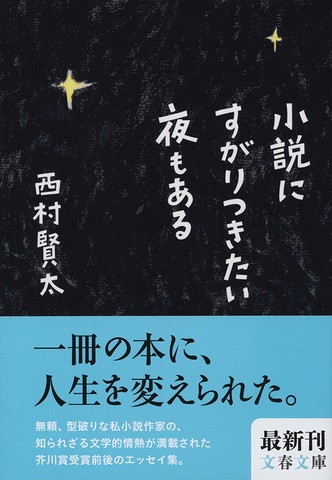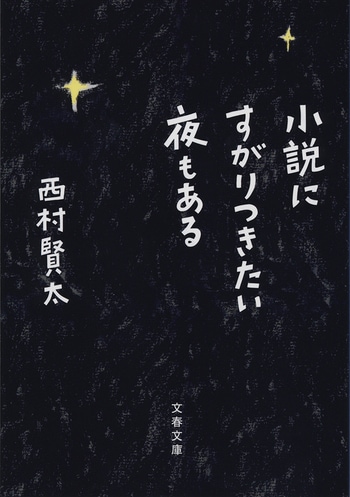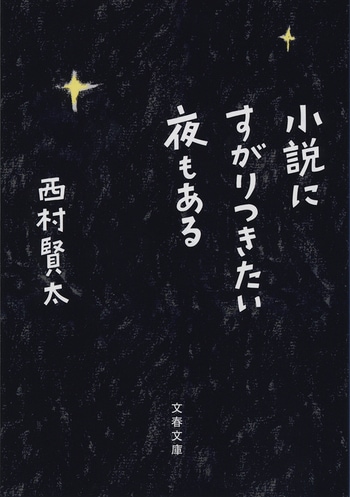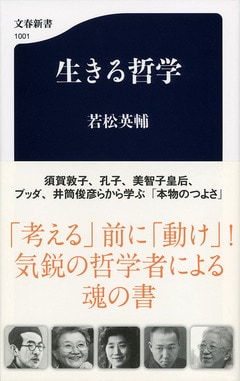偉業とともに眠る故人に自分を重ね合わせると、人は墓荒らしに近い心持ちになる。故人を礼賛することに酔って、威光をくすねていることには無自覚になるのだ。そうした無礼を軽蔑し警戒する西村さんの心情は、芥川賞の受賞のあと、『清造忌』に能登へ墓参をした際の行動にも表れている。感動的な“西村賢太、墓前での受賞報告の図”を期待して東京から訪れた取材者の思惑に、西村さんは応えない。「傍目にどう映ろうと、歿後弟子たる私の、師藤澤淸造への思いは、かような芝居がかったものへは断固反発を覚えるようである。」(『この人あっての私小説――芥川賞受賞の弁』より)とあるように、やはり師への敬慕は一途な墓守のそれなのであった。
私小説とはなんであるかを、西村さんは『私小説書きの自信――芥川賞を受けて』でこう書いている。
「主人公はどこまでも自らの分身である以上、(中略)一作ごとにメインたる人物の性別や生い立ち、基本的な思考回路を都合に合わせて取っかえ引っかえなぞできぬ、ある種、窮屈な制約を伴う種類のものである。」
「過去の優れた私小説書きは、皆その作品造形の自己模倣性を批判されながらも、変節することなく書き続ける行為により、今も読み継がれる存在となり得ている。」
そうとしか書けない(書かない)、という私小説の苦しみは、そうとしか生きられない私たちの苦しみでもある。私はなぜこうでしかないのかという問いを、あてもなく訴え続けて人は死ぬ。けれどそれではあまりにも辛いので、あなたには答えがあると言ってくれるいろいろなものが用意されているのだ。宗教や文学や、お金や恋愛や。ああそれらを受け取って、「私は知っている」と言えたらどんなにいいだろう。どうしてこんなに生きることは辻褄が合わないのか、なぜオチもなく見せ場もなく、進歩のないしょうもなさと暮らして行くしかないのか、私はそのからくりを知っている、と言えたら。でもやっぱりいくら物語を手にしても、行き場のない身体を与えられてほったらかしにされている理由は、分からない。そんな不自由な自分を、ただ観察するしかないのだ。
おそらく、「私は知っている」とも「ほんとはそうじゃないんです」とも言わない人が、私小説を書くのではないかと思う。それを一切言わずに生きていくのは、過酷なことだ。こうとしか生きられないことに恐れもがきながら、その醜態を記録するのは、なんと孤独な営みだろう。
『凶暴な自虐を支える狂い酒』の中で、西村さんは葛西善蔵や田中英光や藤澤清造の私小説を、川崎長太郎や嘉村礒多のそれと比較している。
「前三者と云えば、その加虐さ、他虐性を作中でも遺憾なく発揮した“被害者ぶった加害者”の文学と古くから見透かしたような評をなされ続けてきた私小説作家だが、一見他虐にみちたその本質は、実はどこまでも自虐の中より生じていたものなのである。一方の嘉村や長太郎は深い内省の自虐を作中に横溢させる反面、意外とそこには他者への加虐性を内包している。」