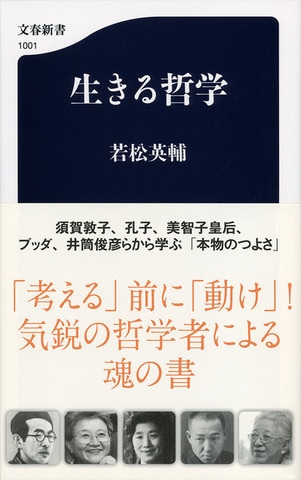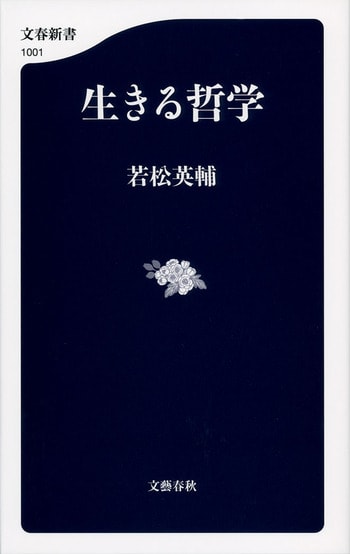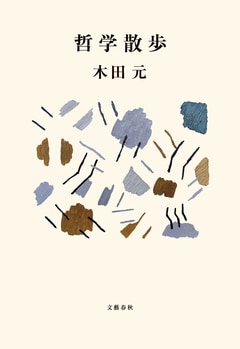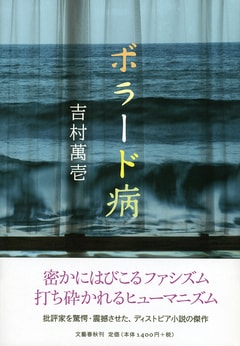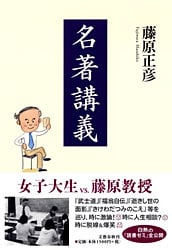もしもあなたが哲学を知らず、孔子もブッダもリルケも原民喜も須賀敦子も舟越保武もよく知らない、あるいは全く知らないのなら、あなたこそこの本を最もよく読める人である。私もまたその一人としてこの本を読んだ。
もしもあなたが悩みも悲しみもなく、他人の気持ちに関心もないのであれば、あなたは幼子のようにこの本を読める。最も本質的な読み手として、誰よりも多くの言葉を聞くことになるだろう。
読むこと、書くこと、言葉にふれること。著者曰く、食べることも読むことであり、織ることも書くことであり、彫刻もまた言葉である。池田晶子やプラトンに触れ、言語は言葉の一形態に過ぎず、意味の塊であると説く。井筒俊彦が形の定まらない意味の顕われをコトバと呼んだように、それはあらゆる芸術や宗教にも、それだけでなく辰巳芳子の料理や志村ふくみの染める糸の中にもあるというのだ。
これらの人名が、たとえあなたに親しいものでなくても、それは問題ではない。この本のタイトルは「生きる哲学」である。何かを学ぶことと、何かを生きることは違う。概念の認識ではなく、実在の経験こそが人を動かすのだ。そう繰り返し話した井上洋治は神学者であり宗教家であり、詩人だった。詩人も宗教家も、彼方から来るコトバの道に過ぎないと著者はいう。その彼方から来るコトバは、ここに名の挙げられた賢者や求道者たちだけでなく、おびただしい数の無名の人のなかにも通じているのだと。
私も彼らを殆ど知らない。聞いたことがあるだけの名や、人物に対する僅かな情報や曖昧な印象しかない名ばかりだ。かくももの知らずの私がなぜこの本を読めたのかと言えば、私には私なりの悲しみがあり、祈りがあるからである。あらゆる人の体験はその人固有のものであり、全ての固有の体験は等価で無二であると、著者は繰り返し述べる。そのたった一つのメッセージがいかに普遍であるかを知らしめるために、著者はいくつもの事例を引いて、読者に気づきの機会を与えるのだ。
気づくことが橋を架ける

ある人は初めて名を知った先哲の言葉に、自分が認められたような気がするだろう。ある人は著者が出会った市井の人の問いに、自分が問われているような痛みを覚えるだろう。それはコトバとの出会いである。それは外からやってくる啓示ではない、と著者はいう。私たちは聞くのだ。すでに私たちの中にあるものがふとかたちを現す瞬間を、彼方から来たコトバを聞くように私たちは体験する。
あなたにもないだろうか? あ、そういうことだったのか! という気づきが、世界とあなたの間に橋を架けたことが。虹のように束の間光って消えてしまうその気づきが、しかしあなたに、誰かに話しかけられたようなほの温かい承認を残して去るのを、懐かしく見送ったことはないだろうか。私にはある。その一瞬において、わたしは道であった。
わたしが渡しの意を持つのかは知らない。けれどたしかに、自己は孤独のうちに留まり得るものではなく、隣人を希求する。誰も他者の気づきを経験することはできないけれども、その訪れに絶えず感応するなにかが、全ての人の中にあることを直感している。
他人から見たらどうでもいい理由で死のうと思ったとき、私は初めて人の尊厳が無名であることを知った。無名の尊厳を生きることにおいて、私は他者と等しい。それは、特別な自分であらねばならないという呪縛をとき、私を自由にした。誰がこんなことを教えてくれたのか、わからない。きっとこれは思い込みに過ぎないけれども、思い込みでも人は生きていけるのだと思った。そして著者は、それは孤独な思い込みではないと、私の肩を抱くのだ。そこに生まれるものが、コトバである。
苦しみにも悲しみにも優劣大小はない。喜びに序列はつけられない。生きることは、なぜではなくどのように生きるのかという問いに応える営為だ。それは光であると著者はいう。今読まれるべき、労りと励ましの書である。