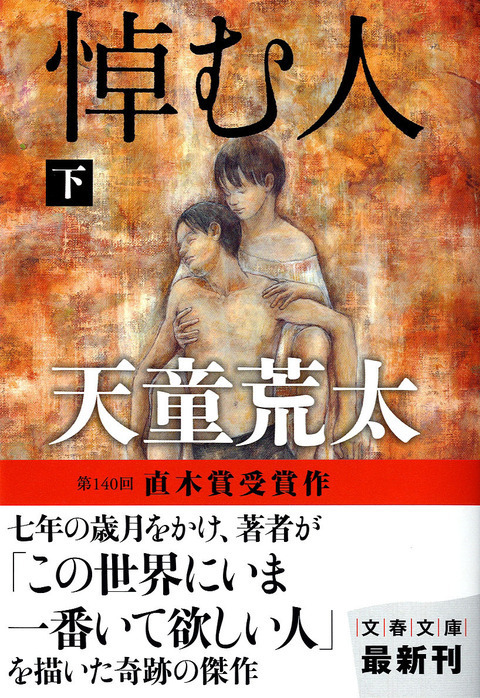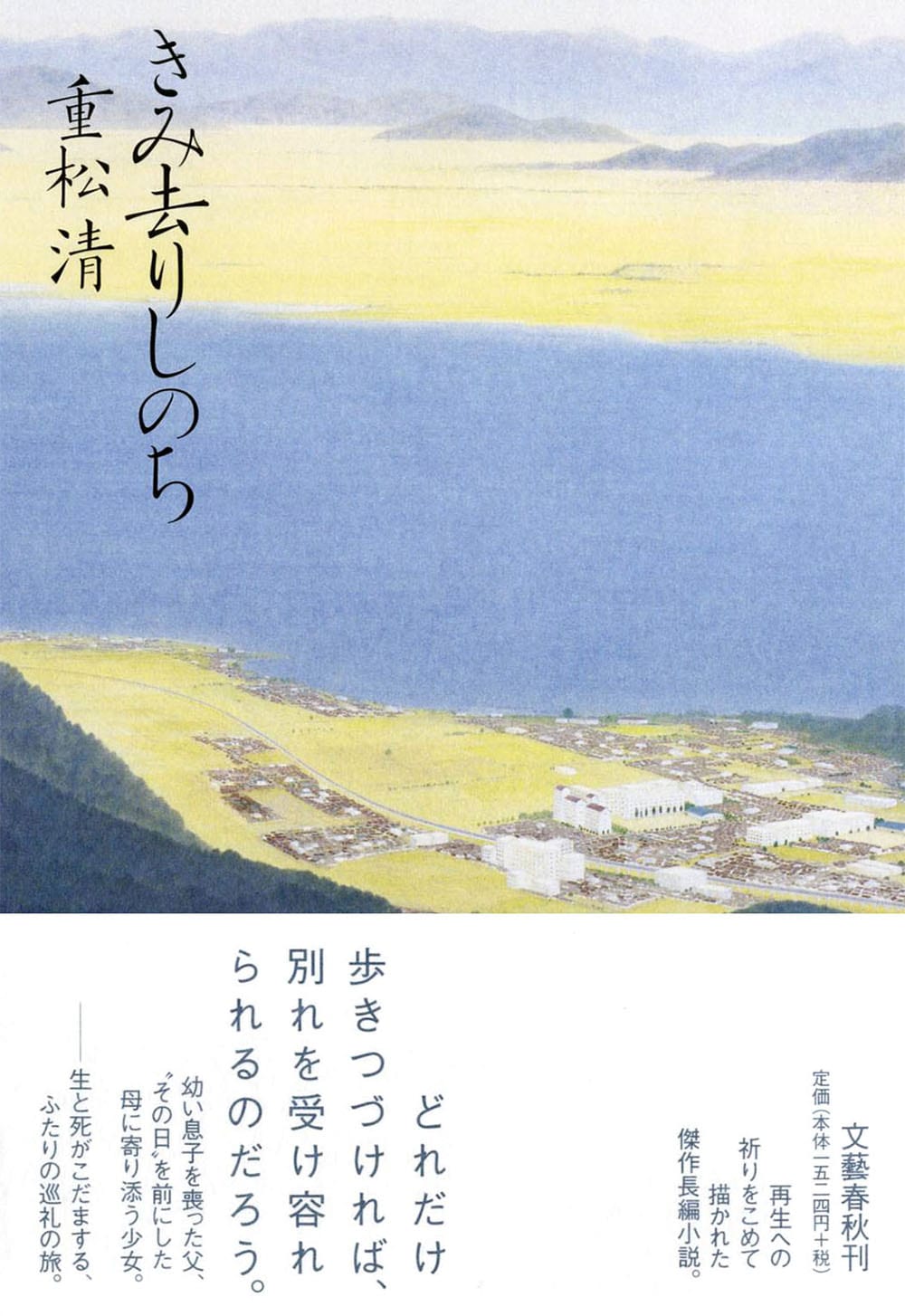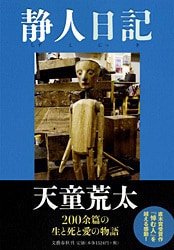天童 多くの人は、時が流れていくことで、それこそ7回忌、13回忌と重ねることで落ち着いてくるのだろうと思います。節目節目で、死者の位置を心落ち着くものに後退させてゆく。それは先人の知恵だったんだろうと思うんです。でないと生きてゆくことが難しくなりますからね。でも一方で、そこからもれている人っていうのかな、「おれは時間がやがて解決するなんてことは信じない」とか、あるいは「自分の子どもが忘れられていくことはどうしても我慢できない」という人はきっといて、そうした人に向けての言葉はあまりなかったと思うんです。僕の立場としては、大勢の人より、そこからもれる少数の方たちに言葉を届ける表現者でいい、という想いがあるんです。
重松 なるほど。「立ち直る」という言葉は、じつは残酷なものかもしれない。元に戻るなんて、厳密な意味では不可能なのに。
天童 『きみ去りしのち』は、死の「扱い」ということを、真摯に、一途に表現された出色の作品ですけど、作中の幼い子を亡くした夫婦は、立ち直るということの、自分たちに最もしっくりくる「あり方」をなかなか見つけられずに苦しんでいましたね。
重松 人が立ち直るときに、何の思い残しもなく立ち直っているかといったら、実はそうではなくて、立ち直った人たちの根っこには何かが残っているのではないかと思います。時おり、まだ早いんじゃないか、ほんとに悲しみ尽くしたのか、という感情がわきあがってくる。それが罪悪感のような気がするんですよ。まだ足りない、いずれ立ち直るにしても、それは明日でもよくて、きょうはまだ泣いてよかったのかもしれないという思いです。

天童 遺された人が、これまでのステージから1つ上のそれに上がるときに、何が支えとなるのでしょうか。
重松 そもそも僕は、「遺族」っていう言い方がいつまで続くんだろうと疑問を持っているんです。極端にいったら、僕たちはみんな遺族なわけですよ。たぶんいつの間にか、何とかさんのご遺族という言い方でなくなるときがある。喪中で1年間、年賀状が出せないという習慣も、いわゆる「喪の期間」にわかりやすい縁取りを作ってくれている。
それを過ぎると、ふと忘れる瞬間がちょっとずつ増えてくる。もちろんいつでもそこには戻れる。だから、何か忘れる瞬間があるというのと、忘れ去るというのは別なんですよ。最初は四六時中も忘れちゃいけない、この人のことだけ考えていなくちゃいけないっていう思いで亡くした人を見送り、そこからだんだん時間がたって遠くなり、遠くなるけれどもいなくなるわけじゃないんだという、この距離感をつかむことができるかどうか。
さっきのカルピスの原液じゃないけど、1回もう原液は入っているんだから、どんなに水を入れたってもう真水に戻らないわけです。だから、自分の人生の中でこの人が確かにいたんだということは絶対に消えない。だけど、薄れてはいく。薄れてはいくことは、肯定してあげたいと思っていますね。
天童 なるほど。ときどきは忘れ、だんだんとほどよい距離感もとれてゆくだろう。初めはそれさえ罪のように思って悲しむこともあるだろう、けれどそれはゆるされることであって、人はそうやって生きてきたということですよね。罪悪感や悔いもひっくるめて「その後」を生きてゆくことを受け入れられたとき、ステージが上がっているのかもしれませんね。
小説の登場人物たちは、重松さんのなかで、その後も生きているんですか?
重松 生きていますね。
天童 たとえば『その日のまえに』で、妻を亡くした夫は、どうしてますか。もう再婚したんでしょうか。
重松 再婚はしていないでしょうね(笑)。最初は子どもたちも、毎朝仏壇でお母さんに手を合わせて話しかけていたのが、だんだん学校に遅刻しちゃうからって、急いで家を出るようになる。お父さんが「おまえ、水替えてないじゃないかよ」と子どもを叱る。お母さんの死と向き合うときにはちょっとしんみりするけれども、忘れているときもあるだろう、という感じじゃないでしょうか。
重松 清×天童荒太 「命をめぐる話」
第1回:物語から歴史へ
第2回:罪悪感の正体
第3回:生と死を意識させるもの