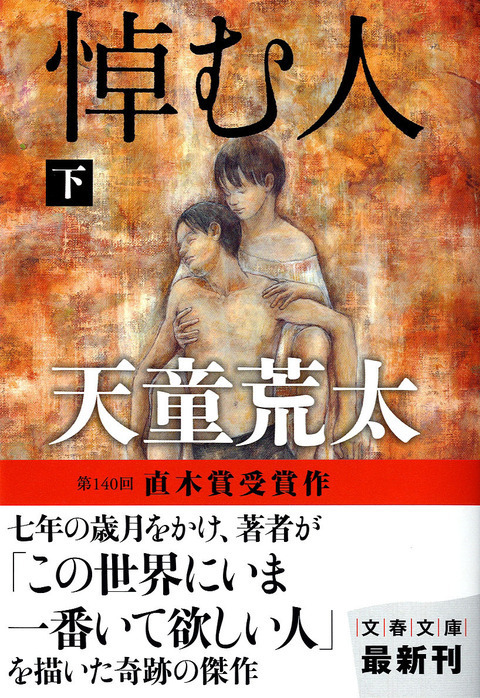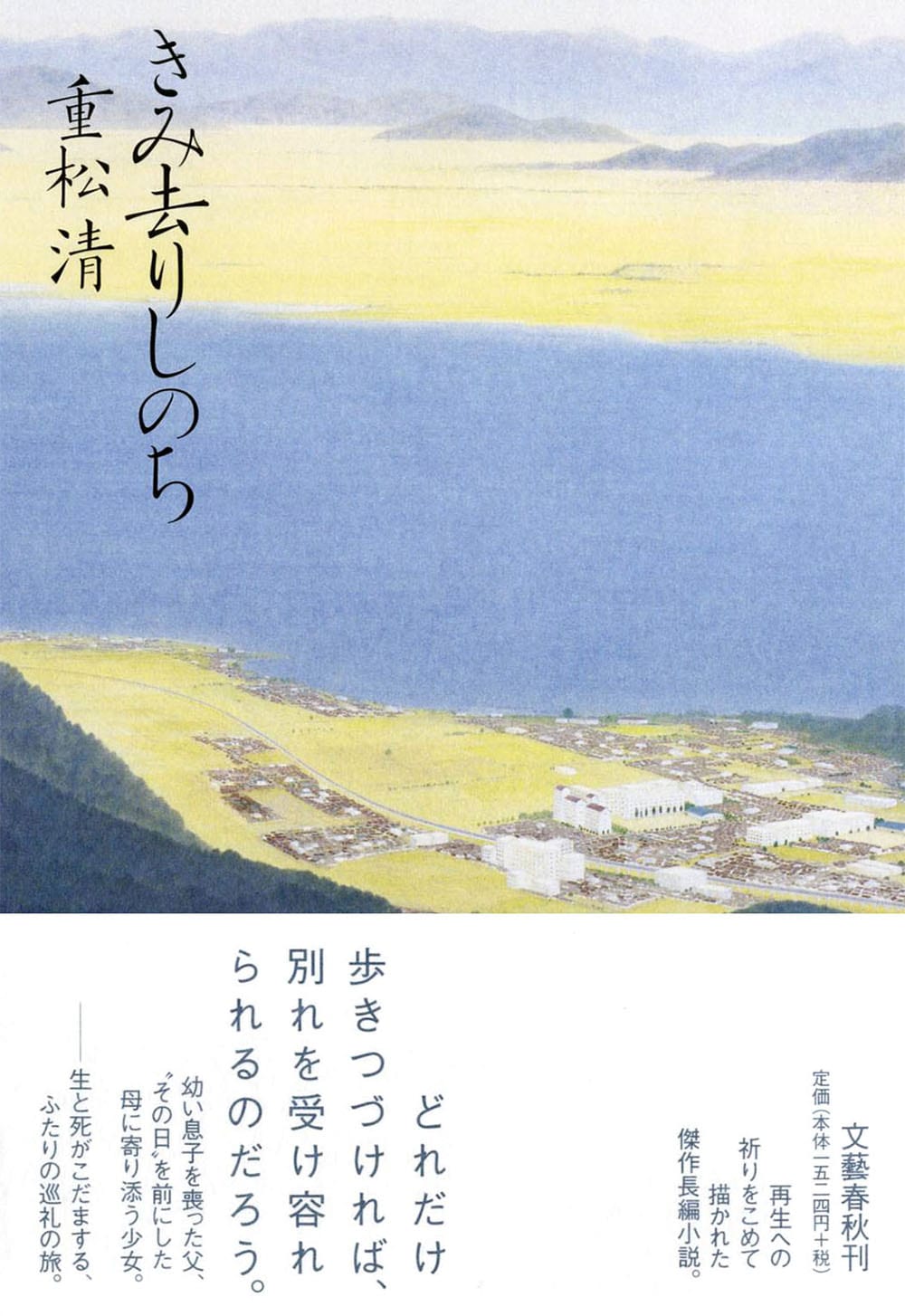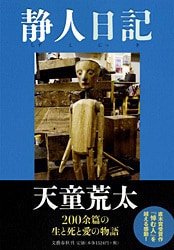重松 今日は「生と死」について、天童さんにお話をうかがいたいと思います。新年号にはちょっと重たいテーマですが(笑)。
天童 確かに、胃にもたれるかもしれない(笑)。でも、これだけ死の扱いに軽重のバランスがいびつになっている時代だからこそ、年の始めに語るべきテーマでもあると思います。
重松さんとは一度ゆっくり話をしたかったので、いろいろと刺激を受けられると思って、今日は楽しみです。
重松 その期待を裏切ってしまう前に、まず僕から聞かせてください。2009年の1月に、天童さんは『悼む人』で直木賞を受賞されました。そしてこの11月には受賞第1作として『静人日記』が刊行されています。すばらしい作品でした。
天童 しょっぱなからなんだか怖いなあ(笑)。でも素直に嬉しいです。ありがとうございます。
重松 僕は『悼む人』の書評も書かせていただきましたが、本を読んだ人から天童さんのもとに、さまざまな反響があったと思うんです。おそらくそれは、単純に面白かったとか、あるいは泣けたとかいうレベルじゃなくて、もっと読者1人ひとりの実存にまで迫ってくるような受け止め方をされたものだったんじゃないでしょうか。
天童 読者の声として最も印象に残っているのは、多くの方が、自分の身近な人の死に対して、罪の意識を持っていたということです。もっと何かしてあげられたんじゃないか、死をくい止めることもできたんじゃないか、と苦しんでおられる。死者のことを、涙や後悔ぬきでは思い出せない人が、実際にはとても多いということにあらためて驚きました。
重松 読者からの反響に対して、天童さんはその答えとして、『悼む人』の主人公である坂築静人(さかつき・しずと)の日記を提示された。作家が読者へ示す答えとしては最良のかたちだと思いました。どうしてこれを書かなくてはいけないと思われたのですか。
天童 死者を善きことで覚える、という悼みの実践を、どのような死に対してもあてはまる形で示しておきたかったんです。
そして、そのような行為を繰り返す「この男がわからない」ということも大切にしたいと思ったんですね。悼みをわかったつもりで書いたら、たぶん死そのものに対して傲慢になる。どうすれば、静人のことをわかるだろうか、悼みの本質を伝え得るだろうかと、いろいろ試した末に、日記という形にたどりつきました。
重松 書き続けて、静人という人間がわかりましたか?
天童 いや、今でもわからない(笑)。
重松 『悼む人』の書評では「静人とは鏡である」と書きました。ある種の狂言回しみたいなもので、「人は静人という人物と出会った時にどんな反応をするのか」が『悼む人』の眼目ではないかと思ったのです。
天童 『悼む人』の構想を編集者に伝えるとき、よく口にしていたのが、静人は真空な人だということです。彼の周囲の人物を描くことで、中心にぼうっと円が浮かんでくるような形を目指していました。こんなことを作者が言うのはどうかと思うけど、ああいう男は、浮世離れというか、まあ現実にはいないわけです。
重松 いたら怖い(笑)。
天童 わりとウザいじゃないですか(笑)。
重松 そうかも。
天童 でも、もし、現実にこんな男がいるってことになったら、やっぱりちょっと嬉しいというか、生きてゆく上での遠くの灯のような存在になるんじゃないかと思いながら、『悼む人』を書いたんです。
重松 執筆の時系列で言うと、『静人日記』のほうが前だったとか。
天童 はい。作品内の時間もそうだし、作品としての成立時期も、もともと『静人日記』は、『悼む人』を発表する前に、そのバックボーンになるようにと、毎日つけていたものでした。
つけ続けているうちに『悼む人』では届け切れなかった人間の死、生、そこから炙(あぶ)りだされる人間の真の愛情みたいなものが、坂築静人という触媒を通して現れているのではないかと、『悼む人』とは別の作品として読者に届けたほうがいいのではないかという気持が芽生えてきたんです。
重松 『悼む人』の終盤で、静人の母が死を迎えます。もし、静人が母の死というものを体験していたら、彼の意識は変わりますか?
天童 大いに変わると思います。
重松 それを聞いて、ほっとしました。母の死によっても静人のありようが変わらないのであれば、彼は聖書の中の人間になります。文学ではなくて、むしろ宗教的な存在になってくる。静人だって、母の死を経験すれば、変わりますよね。ということは、『静人日記』は物語の時系列としても『悼む人』の前にあるわけですね。あくまでも前日譚、プレストーリーとして。