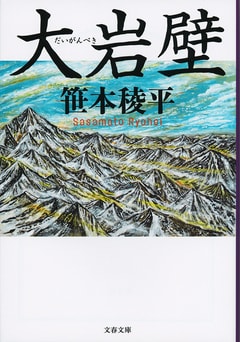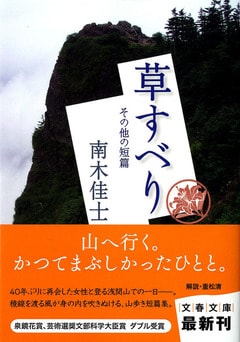本来、文庫本の解説に解説者の個人的な記述はいらないとわきまえてはいる。そうお断りした上で、あまりにも符合するいくつかのことがあるので、少しだけ個人の情報を書くことをお許しいただきたい。
私の父は南木氏と同じ医師だった。代々続く医家の家柄を支えに生きているように子どもからも見えた。「父親が早世した後、六人も子がいたのに誰も跡を継がなかったから、次男なのに自分が継いだ」と、苦学して医師になったことを繰り返し、子どもに話して聞かせた。そうして継いだ家業を、兄弟の子孫も自分の子も孫も継がなかったことを、口では「人は自ら選んだ人生を歩むべし」と言いながら寂しそうだった。勤務医から、大病院の院長、開業医、六十五歳から退職までは船医という異色の経歴で、高齢になって生まれた私という娘のために、つまりは生活のために八十歳直前までの約六十年間を現役の医師として捧げた。
二十数年前にその父が病に倒れ、病床で医療を間近にした。登山の道を開いてくれた医師はそのときの主治医だ。父を八十四歳で見送った後、この十数年、残された母を介護する中で、再び様々な医療関係者に支えられている。いま自分が、介助者として医療や介護の世界に分け入るようになって、しみじみ跡を継いでおけば良かったと思うようになった。後の祭りである。
南木佳士氏の『信州に上医あり』に描かれる若月俊一先生は、地域に根ざして地元の医療に貢献した医師として、後輩の医師たちが遥か高みに仰ぐ先人だ。母の闘病を通して、若月氏の流れをくむ医師たちからその理念の恩恵に浴して高名を知った。これもまた縁としか思えない。
そして父は、若月先生とほぼ同時代を生きた(父が六歳上)。昭和二十五年に地方の中規模病院の院長として赴任するも、その後病院が統廃合され、医師の少ない地域だからと請われて小さな診療所の主(あるじ)となった。自分がもう少し若かったら、この地域に広がる郷土病を研究したのにと残念がっていたのを覚えている。おそらくせめて継いでくれる子がひとりでもいたらとの思いもあったのだろう。父もまた学究肌の人間だった。戦前戦後を波乱のうちに生き、理想を掲げながらも生活に追われて、一介の医師として生涯を閉じた父。若月氏のまとう時代の空気が当時の父と重なり、飴色の小さな診療所に座る白衣の父がまぶたに浮かぶ。
若月氏はあの時代としては理想を実現するための強い熱量を持つ稀有な存在だったのだろう。その魅力を、南木氏は、小説の修業は彼を書くに足る文章力を養うための修練だったとまで言っている。