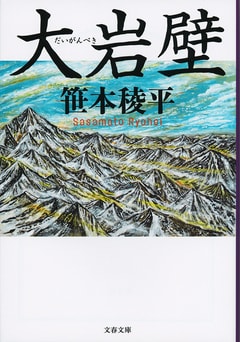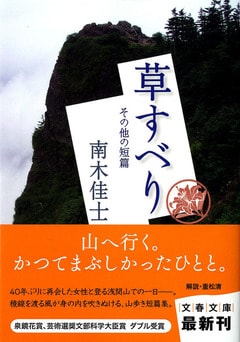かなり脱線したが、南木氏の著作はそれぞれに呼応し合う部分もあるので、この脱線も許されるのではないかと首をすくめる。
さて、本題に戻そう。『山行記』はたった四章からなる。北アルプスの「ためらいの笠ヶ岳から槍ヶ岳」。地元浅間山については文字通り「何度でも浅間山」。南アルプス「つれられて白峰三山」。そして「山を下りてから」と題した章で終わる。
もうこの章のタイトルだけで山好きはこころがときめく。笠ヶ岳から槍ヶ岳……、“ためらいの”とつけたくなる気持ちは痛いほどわかる。もちろん読めばもっと、「そうそうそうなのよ。なぜ私の気持ちがわかるの」という記述に満ちている。さすがに語り口は小説の味わいだ。その魅力にすっかり入り込んでしまって一気に読みすすめた。
欲の炎が、「五五リットルのザック、シュラフ、シュラフマット……。(中略)テント泊に備えた装備が増えるにつれて大きく燃えあがるようになり、ついには(中略)消火不能になった。」
そうだろうなあと、重い荷物を担いで歩いた過去のテント縦走を振り返り、胸が熱くなる。そして、こころの鬱屈を抱えながら、周囲に遠慮、配慮する感覚も、そこを表現する言葉選びもこれは同世代だからなのかと推察せざるを得ないほど、南木氏の文章からは、同じ時代を生きてきた人の匂いが立ちのぼり、そこにまた共感を強くする。
遠く笠ヶ岳の山容を見ながら道がなだらかになると元気が戻り「あるこう あるこう わたしはげんき」と著者は鼻歌を歌う。いきなり、震災のときに、歩いて家に帰りながら頭の中で繰り返し唄った歌がよみがえってくる。あのときも、自らを鼓舞し、歩ける幸せをかみしめたものだ。
憧れるけど怖い気持ちや、それでも憑かれたように行ってしまう気持ち。怖いけど、だからこそ乗り越えなくてはならないような、誰から課せられたわけでもない枷(かせ)を自らに課してしまう。そんなないまぜな気持ちが伝わってくる。
医師という職業、こころの鬱屈、山によって晴れるこころ模様。自分という「こころ」と、そのいれものである「からだ」が、乖離したり寄り添ったり、そのすべてが揺れ動き、かすかにゆがんで気づかぬうちに形を変えていく。
南木氏はこころの鬱屈を取るリハビリとして山に登ったようだが、私の場合はほぼ同時だった。原因は別にあり、それが解決できなければ、何ひとつ前に進めないような局面に立ったころ山に出合った。そして、南木氏と同じように山という圧倒的な自然に包まれて、自分の内面を試され、その深い屈託から解放されていった。その内面を探る描写を、こころのいれものとしてのからだと表現し多用している。
うちなる「わたし」、「わたし」をおおういれものとしての「からだ」を寄り添わせたり、突き放して眺めたりしながらえがく。これは俳優も時折感じる感覚である。いれものである、「わたし」の「からだ」を借りて、作り上げた役の目で、その人が見る世界を見つめる。なぜそんなことを知っているのとどきっとする。
小説を書いた理由を問われて、南木氏はこう語る。「研修医になって、いきなり重症患者を担当させられ、亡くなっていく人を見ていく精神的な負担が、どうにもならなくなったことがあり、ものを書くようになった」。「書く、という行為は、内面の浮き揚がろうとする足を大地につけさせるための作業だったのかもしれない」と。
南木氏の著作はほとんどが信州の山の自然と、医療の世界が軸となって、そこに生きる人々の暮らしやこころを静かに見つめる。静かに、あくまでも美しく綴られる文章に読者は惹きつけられる。そして、こころ模様をえがく視点が縦横無尽に揺らぎながらいつの間にか形を変えるので、知らず知らずのうちにこころの中に入り込み、まるで自分のことのように感じてしまう。そんな作家のマジックにかかったのかもしれない。おおいなる魅力にあふれた山域を、著者の揺らぎとともに歩かせてもらった。