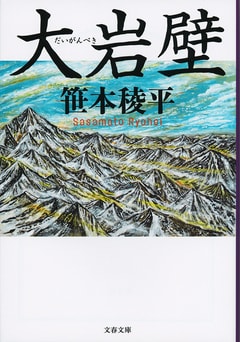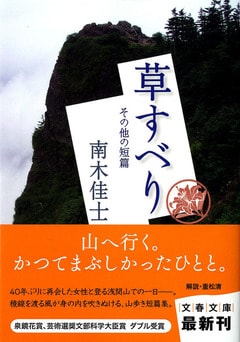読書好きなら、誰もが経験することのひとつに、本を読んでいて、なぜか自分のことを書かれているような気がすることがある。その都度ジャンルも描く世界も違うはずなのに、なぜこの作家は私のことを知っているのだろうと、いったい何度思ったことだろう。
この『山行記』では、その感覚がいきなりだった。ページをめくりはじめてたった四ページ目に「そう、そう、そうよね」と思う描写に出くわした。「晴れた日の午前の針葉樹林の香りが、それまでに服用したあまたの精神安定剤よりもはるかに深く心身をリラックスさせてくれる作用があるのを知ったのも、山にのめりこんだ大きな理由だった。岩をつかんで登るとき、手指とはキーボードをたたくために備わっているのではなく、本来こういう用い方をするものだったのだと悟り、下り路で石車に乗らないように足もとを注視していると、これまでまったく使われていなかった脳の一部がフルに活動しているのがリアルに体感できた。」
そこからもずっと、いやはや呆れるほどに共感は続く。それは、私が山好きだからだろうか。それも決して若くはない時期にはじめて登り、のめり込んでいった過程が似ているからだろうか。また、自分でも鬱かと思うこころの深みに捉えられた経験があるからだろうか。書かれているすべての、あらゆるところから、これは、私のことだろうかと思う描写が続き、自分を探るような気分になった。
医師に物書きは多いと良く言われている。それは生死を見つめる場から心のバランスを保つために必要だからではないかと想像している。実際思いつくまま挙げても著名な文学者だけで軽く十指が折れてしまいまったく足りない。そこに連ねるのはいささか恐縮ながら、私の父も医師だった。そして和歌俳句のたぐいを含めて文章を書くことを愛していた。ついでに言うと、医師に山好きが多いというのは私見だが、初登山に導いてくれた恩人も医師で、山好きで、文章を書く人であり、そのときの仲間も、医師・看護師たちだった。この初登山がこころに深く刻みつけられ、おかげでいまに繋がる新しい人生のはじまりとなった。