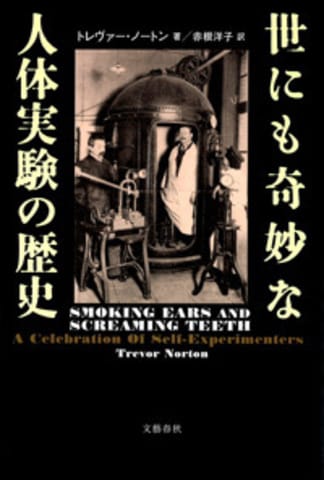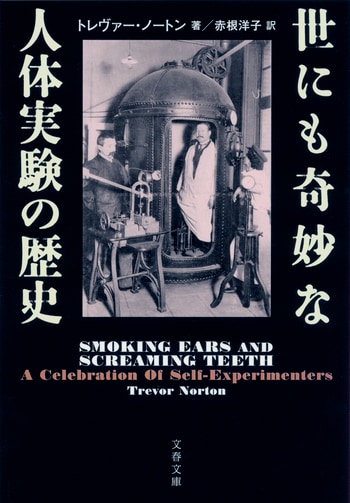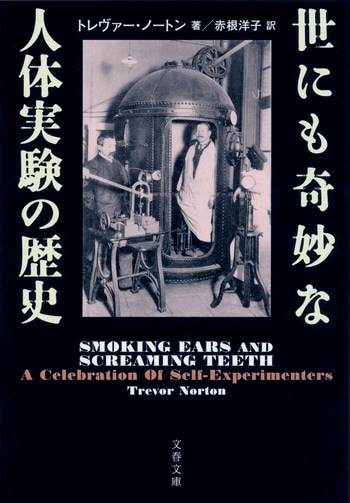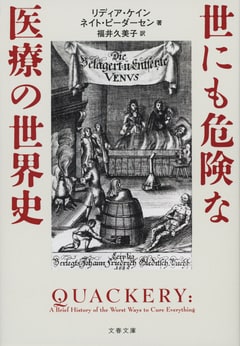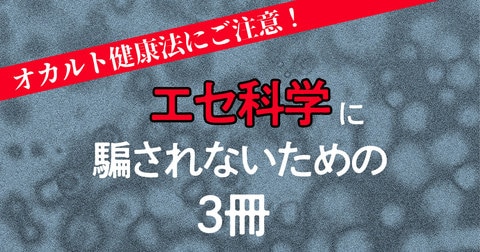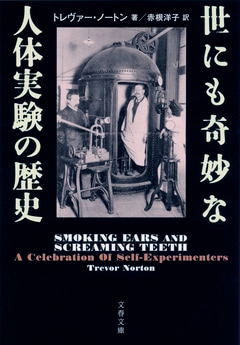「人体実験」ほど、きわどい話はない。「人体実験」と聞くと、誰もが穏やかならぬ気持ちに襲われる。ナチス・ドイツによる強制収容所での毒ガス実験や日本軍の七三一部隊による外国人捕虜への炭疽菌兵器の実験などが思い浮かぶからである。
もちろん現在は、1964年に世界医師会が採択した「ヘルシンキ宣言 人間を対象とする医学研究の倫理的原則」において、被験者の福祉が最優先されている。しかし、現実はそんなきれいごとですむのだろうかという疑問がわく。病原菌やウィルスを探したり、新薬を開発したりするためには、動物実験だけでなく、最後は人間の体で確かめなければならない。
本当のところはどうなのだろうか。医療の倫理問題と絡んで最も興味をそそられるテーマである。そして本書に思わず手が伸びてしまったのは、そのせいであろう。
本書は、18世紀の解剖学者ジョン・ハンターの話から始まる。まさに近代の幕開けとともに、医療も実際の人体解剖の積み重ねによって飛躍的に進歩する。ハンターは臓器移植やバイパス技術や人工授精などの先駆者であるが、結局、彼は、梅毒は淋病の進行したものだという自らの仮説を証明するために、自分のペニスに傷をつけて淋病を感染させる自己実験を行い、淋病と梅毒に感染してしまう。
本書では、こうした事例がつぎつぎと登場する。麻酔薬についてエーテルやクロロホルムやコカインなどを自ら人体実験して中毒になった医師たち。ダイナマイトの原料となるニトログリセリンが薬になることを発見したイギリス人医師のフィールド。ゲテモノ喰いの最初の挑戦者フランク・バックランド。自らの心臓にカテーテル手術を施したドイツ人医師フォルスマン。寄生虫やマラリア研究で試みられた自己実験の数々。動物は発症せず人間に発症するがゆえに、コレラや黄熱病など菌やウィルスをめぐる壮絶な自己実験の歴史等々。
たしかに本書には刑務所や貧民を使った人体実験の事例が豊富に出てくるが、基本に貫かれているのは、自らの探求心に動かされて、自分の体を使って人体実験を行った「マッド・サイエンティスト」たちの歴史である。
本書は、この自己実験の歴史を描くことで、「人体実験」に絡む倫理問題を巧みにすり抜けていく。自己実験する多数の科学者たちの「マッドさ」は、実は計算と熟慮のうえに初めて成り立っている。仮に犠牲が出るとしても科学者自身であり、一般人ではない。この話は、自己実験によって毒ガス・マスク開発や潜水艦開発を行い、ナチス・ドイツと闘ったホールデン親子の話で頂点に達する。本書を読むと、科学者の探求心の凄まじさに驚かされ、感動すら覚えるのである。
だが、評者には一つだけ不安がよぎる。今の日本に、このように強い倫理に支えられたマッド・サイエンティストがどれだけいるのだろうか。
多くの放射線「研究者」たちは、福島第一原発事故から1年経っても本格的な除染をせずに、健康調査とメンタルケアを続けていくという。これが巨大な「人体実験」でない保証はどこにあるのだろうか。