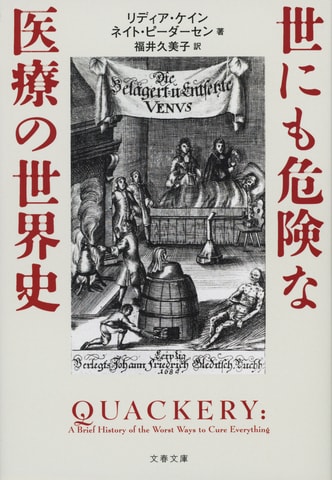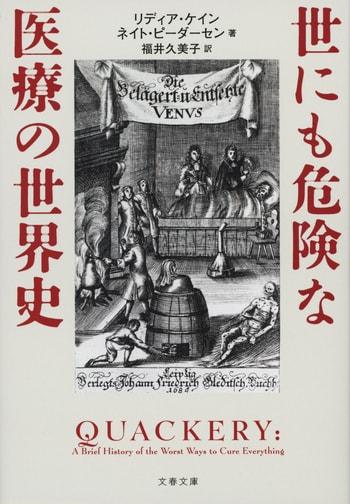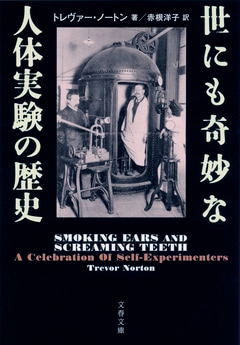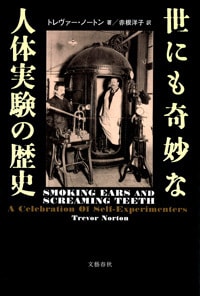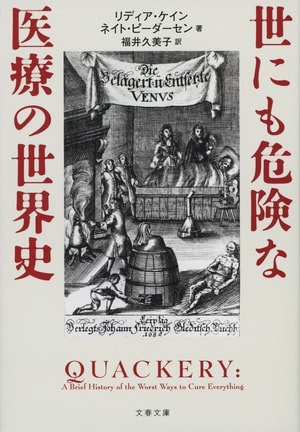
現代でもインチキ医療、危険な医療はいくらでも見つけることができるが、過去の医療の多くは現代の比ではなく危険で、無理解の上に成り立っていた。本書『世にも危険な医療の世界史』はそんな「何でも治ることを売りにした最悪の治療法の歴史」を、元素、植物と土、器具、動物、神秘的な力に分類し、語り倒した一冊である。
たとえば、ペストを予防しようと土を食べたオスマン帝国の人々もいれば、梅毒の治療のために水銀の蒸し風呂に入るヴィクトリア朝時代の人々もいる。剣闘士の血をすする古代ローマの癲癇患者たちに、アヘンを子供の夜泣き対策に使用した親たち──現代的な観点からすると、こうした医療行為はどれをとっても常識に反しているのだが、当時の人々だって、けっしてネタや冗談でやっていたわけではない。
本気で治そう、治るんだと信じてやっていたのであって、そこには彼らなりの真剣さと理屈が存在している。そう、本書で紹介されている治療法には、結果がともなわないにしても理屈があることが多いのである。だからこそ当時の人々はそれを信じたし、我々は今でも知識がなければ似たような理屈や治療法を信じる可能性がある。かつてのトンデモ医療に驚かされるだけでなく、「今でも身の回りにこうした最悪の治療法は根付く可能性がある」と危機感と猜疑心の眼を育たせてくれる本なのだ。
本書で読める驚くべき治療法の数々
本書でどのような危険な治療法が紹介されているか、いくつかピックアップして紹介してみよう。最初は「元素」から「水銀」だ。『水銀製剤は、何百年もの間万能薬として利用されてきた。気分の落ち込み、便秘、梅毒、インフルエンザ、寄生虫など、どんな症状であれ、とりあえず水銀を飲めと言われた時代があったのだ』といい、ナポレオンもエドガー・アラン・ポーも水銀製剤を愛用、または一時期使用していたという。
一六世紀から一九世紀初頭まで愛用されていた「カロメル」は、水銀の塩化物のひとつだ。服用すると胃がムカつくことがあり、強力な下剤効果を発揮し、物凄い勢いで腸の中身がトイレに流れていく。それだけではなく、水銀中毒の症状によって、口からも大量の唾液が分泌される。一六世紀の医学者パラケルススは、唾液が一・五リットル以上分泌された状態を水銀の適度な服用量とみなしていた。現代的な感覚からすると完全にマズい症状であり、なぜそんな明らかに体に悪そうな水銀を当時の人々は愛用したのだろう? と疑問に思うかもしれない。だが、当時の人達は唾液に混じって大量の毒素が流れ出していると考えていたので、唾液がたくさん出るのは、体に良いことだと判断していたのだ。
当時はまだ古代の医学理論(特にギリシャの医者ガレノス)からの影響を受けていた時代で、体内を流れる四つの液体(血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁)のバランスが保たれることで健康になるとする説が真面目に信じられていた。下剤の効果は、当時の病人にとっては体内の液体のバランスを調整してくれる歓迎された効用であり、医者も患者も真剣に水銀を服用して病気を治そうとしていたのである。類似の発想の治療法に、体から悪い血を抜いて治す「瀉血」があるが、こちらは紀元前一五〇〇年頃から行われ、天然痘や癲癇、はては失恋した際のメンタル不調にまで用いられてきた。ただ、現代でも瀉血は多血症やC型肝炎など一部症例では行われることがある。
水銀や瀉血などは当時の人の理屈も想像しやすいが、一八世紀頃に流行したタバコ浣腸と呼ばれる(一見したところ意味不明な)治療法も存在する。もともとタバコは万病に効く薬だと思われていたが、中でも水難者のお尻にタバコ煙を注入すると、体を温めて呼吸器を刺激することができると唱えた人物がいたのだ。水難者が多かったテムズ川では、タバコ浣腸キットを備えた人々が土手を歩き回っていたという。無論何の効果もないし、窒息している時にタバコの煙を尻から入れられて死んだら死にきれないだろう。浣腸を行う側も、誤って吸い込もうものなら大変なことになる。
続いて「植物と土」の部から紹介しておきたいのは「アヘン」。アヘンってドラッグだし、疼痛の管理など医療目的で使うのはありじゃない? と思うかもしれないが、長い期間にわたってその使われ方は広く、雑であった。たとえば泣きやまない子どもにはケシとスズメバチの糞で静かにさせよと紀元前一五五〇年の古代エジプトの医学文書に書いてある。さすがに古代の話でしょと思うかもしれないが、二〇世紀に至るまで、教科書にも子どもの夜泣きや歯ぐずりにはアヘンとモルヒネの調合薬が効くと記載があったのだ。たしかに子供は静かにはなるのだが、眠ってばかりで栄養不足になるし、病気になっても泣いて訴えることもできないしで、死者も多く出たという。
おそらく本書中もっともえぐいのは「ロボトミー」について語った第一三章で、これは統合失調症患者や幻覚症状のある精神疾患患者の頭蓋骨を開き、前頭葉の一部を切り離す手術のことをいう。手法には変遷があるが、最終的には錐状の金属製の棒を眼球の上部から差し込んで脳を直接傷つける「アイスピックロボトミー」に辿り着く。
これを行うことで脳が壊れ大人しくなることもあるので、体や発声の制御がろくにできないレベルの精神病患者などについては当時の基準で有効といえる側面もあるのだが、多くの患者は術後に死んだり障害に悩まされることになる。人類史の中でもトップレベルで愚かな治療法といえるが、当時は精神病の患者が多すぎて家族と社会の重荷になっていて、誰もがその問題の解決方法を模索していた状況があり、ロボトミー手術を推し進めた人たちも、なんとか患者と家族の苦痛を低コストかつ素早く治療できないか、と悩み、求めた結果だったといえるのだろう。
第四部「動物」の中では「食人」の章がとりわけ印象に残る。ここでもパラケルススが出てくるが、彼は人体の一部が含まれた治療薬には魂やエッセンスが仕込まれており、その薬効で病が治ると考えた。また、これは今でも似たことをする人は絶えないが、元気な人間の血を飲むと健康が手に入るという考えが昔から根強く残っている。癲癇の患者たちは剣闘士の血を飲み干したし、一七世紀でも罪人が斬首されると、壺を片手にかけよってそれをそそぎこみ、新鮮な血を浴びるようにして飲んだという。
危険で間違った治療法がなくなることはない
読み通すと、「医療」の難しさがわかってくる。何しろ、人間がかかる病の大半は放っておいても治ってしまうから、インチキ療法であっても、自然治癒してしまう可能性は高い。「治療を受けたのだから」というプラシーボ効果が発揮されることもある。そうすると、インチキ療法と本当の治療の判断をするのは難しくなるし、それは治療を受ける側だけでなく、施術する側もそうである。
たとえ効果がなかったとしても、時代を考えれば他の手段をとりようがないケースも多く、そうした時代においては治療を受けたという精神的な安定だけであっても意味のあるものだったのかもしれない。本書は現代人からすると危険な医療の歴史だが、なんとかして患者を助けようとした医師たちの、悪戦苦闘の歴史でもあるのだ。
依然として完全な治療が存在しない以上、人はこれからも「なんでも治してくれる、まだ見ぬ医療」を期待し続けるし、それに応えようとする最悪の治療法もなくなることはない。「血液を飲んだり、入れ替えると健康になる」など、人が信じやすい情報にはいつの時代も変わらない特定の型があるから、本書を読みそうしたケースについて知ることは、現代の危険な医療にたいする防御策にもなるだろう。
人の愚かさが克明に記されていると同時に、「それでも人類は少しずつ最悪な治療法を潰してきたんだな」と未来への希望を持たせてくれる一冊だ。
トンデモ医療史を深掘りできる類書
医療史ノンフィクションに興味を持った人向けに、類書を紹介しておこう。ひとつは、同じく文春文庫から刊行されている、トレヴァー・ノートン『世にも奇妙な人体実験の歴史』。人体解剖の草分けである医師ジョン・ハンターが淋病のメカニズム解明のために患者の膿を自分の性器に付着させたエピソードなど、自他を問わず人体実験に邁進した人々の歴史を綴っていて、本書と重なる面も多い。
柏書房から刊行のサム・キーン『アイスピックを握る外科医 背徳、殺人、詐欺を行う卑劣な科学者』は墓泥棒から動物の虐待まで、主に科学的探求や功名心から悪徳に手を染めてきた科学者たちのエピソードをまとめた一冊。先に名前を出したジョン・ハンターが、人体解剖をしたいがために、墓泥棒から死体を買い取っていたエピソードなど、倫理と科学的探求のせめぎあいが見事に描き出されている。同じく柏書房から刊行のトマス・モリス『爆発する歯、鼻から尿』は、余興で何本もナイフを飲み込み腸がボロボロになった男など、奇妙でバカバカしい医療の実話を集めている。
本職の外科医であるアーノルド・ファン・デ・ラールによる『黒衣の外科医たち 恐ろしくも驚異的な手術の歴史』(晶文社)は、広い医療分野の中でも外科手術(脂肪切除や去勢、痔、虫垂炎など)の驚異的な歴史とエピソードに絞って取り上げた一冊だ。本書(『世にも危険な~』)とテーマは近いが(さらに訳者も同じ福井久美子氏だが)、「瀉血」など一部を除いて内容はほとんどかぶっていないので、次に読む本としてもちょうどよい。
最後に著者らの本書刊行後の仕事に触れて締めとしよう。感染症学においては、集団内における最初の患者となった人物を英語でpatient zero、日本語で「ゼロ号患者」と呼称するが、二人は再度タッグを組んで、アウトブレイクの歴史──どこで、なぜ起こったのか、どうすれば再発を防げるのか──と、ゼロ号患者たちのエピソードを描き出すノンフィクション『Patient Zero: A Curious History of the Worldʼs Worst Diseases』を刊行している。本書に劣らぬ魅力的な筆致でタイムリーな話題が綴られているので、翻訳・刊行を待ちたいところだ。