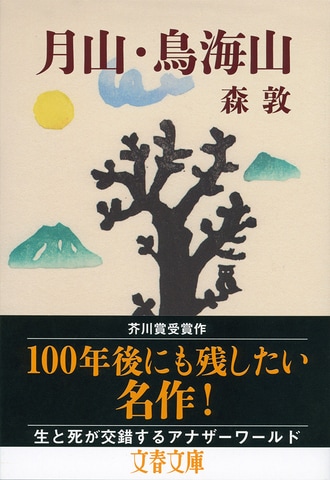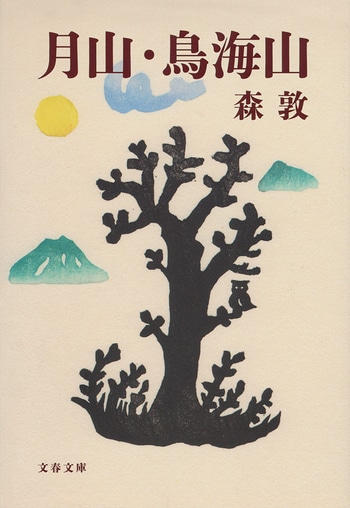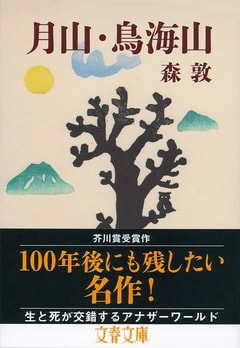セロファン菊、モンペをはいた後家の女。この女と「私」とのあでやかなふれあい、遠慮がちで大胆で、許されているようで許されていない事実。事が起りそうで起らず、すべて無事であって、色が漂う有様。老人たちのうたう御詠歌とみだらな酒宴との対比。老人がかえってみだらであり、若さとまちがうと見えて、それが老いの証拠であり、みずからの酒宴であるように見えて、「私」へのサービスであり、サービスであることによって彼らが満足し、しかも後家女を「私」に結びつける企てのようにさえ見える。いや企てであるわけではない。後家とちぎることは、後家への功徳であり、その一個の女に対してだけでなく一般人間に対しても功徳であるかもしれない、と「私」はよく寺の住職がそうするということを弁解の言葉にもする。その後家に豈はからんや男がいたのであった。男は酒宴のときにもいたダミ声の先達で、男は「私」の前で笑っていた。彼女がこの先達に打擲されている音がきこえる。ところが男は源助じさまの家であったか、ニセ物の応挙の絵などを前にして、何事もないかの如くしたり顔で諸国の経験談をしたりする。ニセ物は寺の先代の和尚からつかませられたのだが、ニセ物であっても、それはそれで……このように一つの貌(かお)は別の貌であることによってそこに存在しているというぐあいに、変転きわまりない。勿論逆説というようなものではなくて、清らかなものは俗なものとのつながりや裏打ちを離れるわけに行かないどころか、俗なものであるが故にこそ清と現われたり、清であることは俗を呼び起し、俗の力を借りずに清は清たる所以を満足に充すことも出来ない。こうして登場人物は自然と同じように作者の力によって安穏な物語の道を進むことを許されずに、実に強力に作者の意志によって多忙に作者の仕組みに参加して、そうして作者の愛情の恵みを受けている。
実に強力なる組立てだからこそ、ともいえるかもしれないが、あるいはこの組立てそのものの内容がしからしむるのかもしれないが、物いわぬ自然が謙虚な態度でおのずから言うようなぐあいにして、人々の相貌はたとえ一見彼らが狡猾であるとしても、それはそれで、おのずから現われるようにして現われる必要がある。そうなるためには、作者は「私」という人物が見聞する形をとることが賢明であったに違いない。つまり発見の形だ。一つの新しい論理に包みこみ、いかなることも日常と見ることからくる色つやという内容の発見。
ここで私の家人が、深沢七郎「楢山節考」に似ているが……といった。ああ、そうか、深沢七郎さんね、そういえば誰かそんなことをいっていると耳にきこえてきた。「だから、あれは恐ろしい物語なのだよ」「でも『月山』も美しいが空恐ろしいわねえ」といった。「だから、恐ろしさの意味も違うのだね。ああいう『楢山節考』のような物語は、あれはあれで恐ろしい。それにあれは傑作だろう。だが、『楢山節考』の物語は『月山』ではただの破片なのだ。そういうつもりで書かれて
いるのが『月山』だ」
夢の扉をあけるようにしてバスに乗って別世界に入った「私」は夢さめるようにして友人と市井へ戻る。現に別世界は彼が友人と戻って行く市井よりも市井的なものに変化しようとしている。源助じさまの花畑であった場所が遠くに見える。彼は牝牛に種つけする冷凍の種を求めて雪の中へ出て行った。じさまが四、五日たっても帰らねば、探しに行くという言葉は語られているが、生きていたことが噂の中でそっと語られ、“遠方”の都からやってきた友人(遠方などというものであろうか)によって眼ざめさせられる。源助は月山に召されたように見える。もともと生を産み出す“種つけ”の目的で出発した元気ものの老人は、死の中に姿を没したかに見えた。それは見えただけである。何も書かれていないが、彼は思い出の中に生きる人物に違いない。そうは行くまい。たとえ残っても所詮それはいわゆる“物語”に過ぎない。こうしてじさまも作者の語る物語となる。それにしても源助じさまと、そして、あえていえば、後家の女は、作者のこの「別世界」にあたえたハナムケのように思われる。勿論“直接的”にという意味ではあるが。「未だ生を知らず、焉ぞ死を知らん」と、この二人は呟いているようでもある。
部分と全体という言葉をつかって私はこの文章を進めてきた。部分が、その背後にある全体をあかすという意味においてである。私自身もそういうことを口に出していったことは一度もなかったとはいわないが、正直いうと、これは森敦さんが私と話しているときに口にした言葉だ。私の小説にふれてだったか、それとも森さん自身の過去の小説についてだったか、その両方であろう。私はそこで、その言葉をつかって、私ふうに解釈して、一応の分析の糸口を示してみた。これはその「死者の眼」で森さんのいう内部外部という言葉をつかって説明した方がよかったかもしれない。こういう言葉をつかうと眉唾と見る人がいないとも限らない。そういう人はもう一度、「月山」を読み直して貰いたい。
それはそれとして、私は「月山」は以上のような分析など要せず、美しくて空恐ろしいものを、そして墨絵のようなもの、その奥からきこえてくる親しみのあるそして恐ろしい声(それは吹雪の音なのか、紅葉の色合いから来るものとも無関係ではないが)をきけば、それで十分ではないかとも思わぬではない。
第一、この作品は何故だか、分析を拒否するところがある。強力な論理と意志によって貫かれていながら、分析を拒否するというように感じられる。私はここで、森敦さんが昔から一、二度、口にしたことのある「幽玄の論理」ということを思い出した。一、二度でしかないというのは、あまりにも森さんがひたすら追究してきたものであるから、それに私とは直接つながりのないことだからというので、それに私の誤解を招くことを恐れたり、そうだったら阿呆らしいと思い、あまり度々は口の端に上せることがなかったのであろうか。だが、お前の世界と自分の世界と違い得るものであろうか。少くとも自分の論理は、説得力をもち得ないだろうか。小島のやつを包み含んでしまうことは出来ないだろうか。そのようにも思ったことがあるかもしれない。「幽玄の論理だよ」と森さんはいうであろう。幽玄の世界を書くのではなくて、「幽玄の論理」によって書くのだ。幽玄化するのだ、と。そして思うに日夜、森羅万象、諸事万端も論理化し組立てに置き戻そうとする彼は、(この態度がどうして“変って”いる、などといえよう)「幽玄の論理」の中味を肥やし、何物にも堪えられるように旅に出させたようでもある。しかしこの論理は度々危険にさらされそうになった。いったい市井にあることが旅ではないのかと。そしてこの論理は生命を得た。それはそれとして先きほどから「月山」を一口で、幽玄の世界を求めて別世界にあこがれ入った話といってしまえば、それですむことであった、とむしろ私は後悔に似たものさえ感じはじめている。まあ、しかし、それですまぬ人は、私の説明がいくらか役に立つかもしれない。
最後に、この作品は、一年間のベスト何とか、五年間の、十年間のベスト何とかいうような枠から外れた、いわば、劃期的なところをもったものだ。二十年、三十年、五十年、何百年(読者よ、笑うなかれ)というふうに、たとえば過去にレインジをのばしてそういう長い期間の中に置くことを許されるのにふさわしいものを本質的にもったもののように思える。勿論、未来に向ってでも同じことである。二十年、三十年によっては変らぬ、という人間の姿を根柢に考えるという姿勢だからである。「月山」がほかの山ではなくて月山であることが果して今後、直接的に花鳥風月であることが果して今後……というようなことを考えさせるかもしれない。それに類したさまざまのことは、つきまとうのが当り前で、それがないものなら、何も作者は「月山」を書く必要もなかったとさえいえる。何しろ「月山」は、もともとあらゆる可能性を含むはずのものなのだから。
したがって今後も山は作品の中で出現するだろうが、月山でないこともあろうし、山は全く出てこないかもしれない。そうしてそれはそれでほほえましく優しい物語であるかもしれない。といっても、その物語はいわゆる物語を消す物語と思われる。どんなことも日常と見なすような、強い意志と愛情に貫かれたものだろう、と思う。