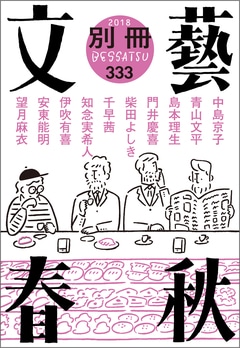同じように乗り込んできた地域課の巡査も聞いているが、日常茶飯事なので顔色ひとつ変えない。それは、沙月にとっても同じだった。何しろ、二日に一度は変死体の見分に臨場するのがここでは当たり前なのだ。
ホテルなので、高層ビル街へ行くものと思っていたら、筒見は正面玄関から出て青梅街道を渡った。沙月が場所を尋ねると、聞いたことのないホテルの名前を口にした。チェックシャツに黒のスキニーパンツ、ソフトモヒカンに固めた筒見の外見は、ファッション量販店の店員さながらだ。
新宿駅方向に歩き、すぐ左に曲がった。寺の境内に沿って進み、ふたつ目の角を右にとった。墓地を囲む塀を右に見ながら、公園の手前を左に曲がる。
「そこのホテルだよ」
筒見が、少し先にある細長い建物を指さした。
「部屋はオートロックで、荒らされていなかったみたいだ」
「病死ですか?」
「たぶんな」
「ひとりですよね?」
「うん、男。わりと若いみたいだ」
そこからぐるっと回り込み、北側にあるホテルの正面玄関にたどり着いた。署を出て徒歩六分。「レコルシア新宿ホテル」と小さな看板が見える。
フロントは二階にあり、その手前に制服を着た四十がらみの細身の男が立っていた。胸元に野沢と書かれた黄金色の名札。筒見が警察手帳を見せると、男はマネージャーですと言いながら、エレベーターに案内する。
三階まで上がり、野沢が三〇六号室のドアを開けた。そのまま左手でドアを支え、半分ほど開いた隙間に筒見が身を滑り込ませ、沙月もそれに続いた。
思ったより広い部屋だった。オートロック方式で、ドアの横のスロットにはオレンジ色のカードキーが収まっていた。差し込むことにより、部屋の電源が入るタイプだ。
水回りのある通路の先に、テレビの載せられたデスクがある。半分ほど開けられたカーテンから差し込んだ陽が、ソファセットに当たっていた。その椅子に緑色のリュックサックが立てかけられ、登山靴が脱ぎ捨てられている。
茶色い絨毯の敷き詰められた床を恐る恐る進む。左サイド、大きめのベッドがふたつ、ヘッドボードを左に向ける形で並んでいた。手前のベッドに白いシーツに身をくるんだ死体が、腹這いになって横たわっていた。太めの体格だ。首が横を向き、目は閉じられている。体はやや斜めになり、左手がだらりとベッドから垂れていた。もみあげから、顎にかけてうっすらと無精ひげが生え、短く刈り上げた頭髪は癖毛らしく、手で掻きむしったように乱れている。
筒見は近づいて、頸動脈に指を当てた。固く閉じた目を無理やり開いて、瞳孔をチェックし、においを嗅いだり、肌の色を観察しだした。
「ご常連様なんです」
遅れて入ってきた野沢から耳打ちされる。
彼は両手をぐっと握りしめ、まるで幽霊を見たように青ざめている。
「見つけたのはどなたが?」
筒見が小声で尋ねる。